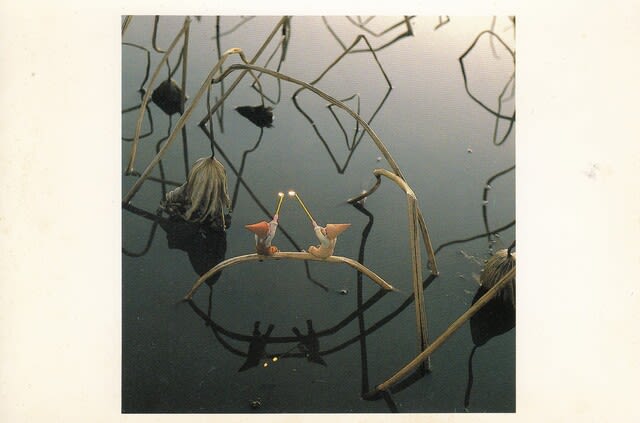誰でも生きることを求めているのであって、死ぬことを求めているのではない、[i]とアランは「幸福である法」の中で述べている。憲法13条には、全ての人が個人として尊重されることが謳われている。「人格の尊厳」あるいは「個人の尊厳」とも言われる。「生命、自由」に続いて「幸福追求に対する国民の権利」とあるが、これを「幸福追求権」といい、人格の担い手である個人が自らの幸福を追求する権利であり、自分の生き方を決める自己決定権を含む。幸福を求めない人はいないはずだ。私たちは希望を抱き幸福を求めて生きる。幸福は到達さるべき目標としてあるわけではなく、あくまでも実現されるべきものとして求められる。[ii] 幸福という言葉から私たちが思い浮かべるものは千差万別であろうが、幸福でありたいと願うのは万人に見られる自然の性情といえるだろう。
経済的自立なくして真の自立はないと述べる 松原惇子は幸福について繰り返し記述している。幸福って心の持ち方一つだ、本当に考え方一つだ。幸福の形ってないような気がする。幸福って内なるもの。自分で感じるもの。自分でつくるもの。[iii] こう述べる 松原は、自らが創造した46歳の独身OL麻子にこう言わせている。「こういう生き方をすれば幸福、なんてものはないのよ。それを幸福と思えるか否か、それだけのことじゃないの。条件で人は幸福になんかなれないのよ。本当に大事なのは、自分の考え方なのだ。人と比べるのはよそう。人は人だ。外見的なもので、幸、不幸を判断するのはよそう。わたしはわたしだ。わたしは46歳のOL。それがわたしなのだ。わたしはもっと自分に自信をもって生きなくちゃ。ひとりのOLとして見事な一生を送らなければ。誰も評価してくれなくてもいいではないか、自分が満足なら。わたしはがんばる。毎日、積極的に心の勉強をするわ。幸福な人生を送りたいもの」。[iv] シングルだから淋しい、結婚しているから幸福という方程式はない。結婚できても、幸福だと感じなければ幸福ではない。淋しさというのは、結局、自分自身の心の問題で、人や条件が取り除いてくれるものではないのだ。大事なのは、今の自分を生き生きと生きているかどうか。そして、自分で決めたこと、行動したことに、責任を持つこと、[v]であり、「会社」「結婚」というノアの方舟に身を任す人生ではなく、自分自身がノアの方舟の主であるべき、[vi]なのだ。
ヒルティは『幸福論』の中で次のように述べている。苦しみのときにあっても、少なくとも心の奥底では、つねにできるだけ自信をもち、またいかなる場合にもつねに、大いに勇敢であり給え。そうすれば、経験に照らしても、いつも神の助け給う日がやってくる。しかし、万一、神の助けがまったく現われず、われわれを圧迫し不安にする悪条件がとり除かれなかったとしても(とりわけ苦しい時にはしばしば、ほとんど怪しいばかりの説得力をもってそう思わせられやすいが)、それでもなおわれわれは「気晴らし」の享楽や厭世観や、怒りや無気力におちいるよりも、自分自身の勇気と善良さをもって戦うほうが立派に凌いでゆくことができるであろう。なぜなら、われわれは結局、絶え間なく-そしておそらく永遠に-ただ自分自身でもって生きていかなければならないし、他人ではなく、まさしくわれわれ自身がどのような人間であるかというその在り方が、つまるところ、何よりもわれわれの幸福を決定するからである。[vii] 幸福には、意志の力が強く働いている。何か特別な甘美な薔薇色の状態が幸福なのではなく、日々の生活の中での在りように幸福は潜んでいる。実際には幸福であったり不幸であったりする理由はたいしたことではない。いっさいはわれわれの肉体とその働きにかかっている。[viii] 要はそこに、存在することだ。
精神世界への目覚めから年収2千万円を捨てた元キャリアウーマンの48歳の女性は、「野心から解放された私はやっと自由になれたんです。ただ、存在するだけでいいんだ、と今やっと思えるようになったんです」と言う。[ix] 何もない彼女の顔は輝いている。その対極にいるのが「高価な服やバッグを買い、毎日タクシーを使い、おいしいものを食べ、お金を使ってもちっとも幸せじゃないし、ちっとも心が晴れません」[x]という28歳のOLだ。巨大な消費者集団としての顔をもつOLは、「モノ語り」の人々を代表する。「モノ語り」の人々は、人そのものの描写は苦手だがモノを媒介にした人物描写になると雄弁になる。[xi] 産業社会から私たちが今どっぷりと浸っている高度消費社会へと移行するなかで、私たちは、生活必需品を買うためではなく、新たな快楽を求めて商品の集積をうっとり眺めるようになった。ブランドものなどの「付加的な消費」へと誘われるようになったのである。ブランドを身につけることで、それなりの自分を簡単に演出することができる。顕示的消費においては、たくさん「持つこと」によって、自分の存在を確認することができる。生きるためには物をもたなければならないが、そのうえ物を楽しむためにはますます多く持つことが目的となる。自分がもっているものにたよることは私たちを強く誘惑する。持っているものはわかりやすいので、私たちはそれを固守して、それに安心することができるのだ。しかし、持っているものは失われうる。失われたときの私は何者だろう。[xii] フロムは「持つもの」に自我を含めて考察している。マイスター・エックハルトは、何も持たず自分を開き「空虚」とすること、自分の自我にじゃまされないことが、精神的富と力を達成するための条件であると教えた、[xiii]とフロムは述べる。生産的な内的能動性の状態は、あらゆる形の自我の束縛と渇望を乗り越えることだ[xiv]というのだ。
自我の実現とはなんであるか。観念的な哲学者は、自我の実現は知的洞察だけでなしとげられると信じていた。彼らは、自分のパーソナリティを分割することを主張し、人間の本性が、理性によって、抑えられ導かれるようにしようとした。しかしこの分割の結果、人間の感情生活ばかりでなく知的な能力もかたわになった。理性はその囚人である人間性を監視する看守となることによって、自分自身が囚人となった。そして人間のパーソナリティの両面、すなわち理性と感情はともにかたわとなった。我々は自我の実現は単に思考の行為によってばかりでなく、人間のパーソナリティの全体の実現、かれの感情的知的な諸能力の積極的な表現によって成し遂げられると信ずる。これらの能力は誰にでも備わっている。それらは表現されて始めて現実となる。いいかえれば、積極的な自由は全統一的なパーソナリティの自発的な行為のうちに存する。我々はここで、心理学のもっとも困難な問題の一つである自発性の問題に近づく。自発的な行為は、個人が孤独や無力に寄って駆り立てられるような強迫的なものではない。またそれは外部から示唆される型を、無批判的に採用する自動人形の行為でもない。自発的な活動は自我の自由な活動であり、自らの自由意志のということを意味する。我々は活動ということを、「なにかをなすこと」とは考えず、人間の感情的、知的、感覚的な諸経験のうちに、また同じように人間の意志のうちに、働くことのできる創造的な活動と考える。この自発性の一つの前提は、パーソナリティ全体を受け入れ、「理性」と「自然」との分裂を取り除くことである。なぜならば、人が自我の本質的な部分を抑圧しないときにのみ、自分が自分自身にとって明瞭なものとなったときにのみ、また生活の様々な領域が根本的な統一に到達したときにのみ、自発的な活動は可能なのであるから。[xv] これ以上、この論文で、自我とは何かという問題に立ち入ることはしない。自分らしく立つことはどういうか、自分の能力や才能、自分に与えられている人間的天賦を表現するとはどういうことなのか。今後の課題としたい。自分さがしについて黒井千次は、「私」をさがすぼくと、ぼくにさがされる「私」とが円環をなしてぐるぐると堂々めぐりをしてしまうのか、抜き抜かれつしているうちに、どちらがどちらを追い、どちらが捜されるのかすらわからなくなってしまうのかもしれない。もしそうだとしても、どこか虚しい、それでいて激しく熱いそのような運動の中からしか、「私」は出てこないのではなかろうか、[xvi]と述べているが、このようにして、自分とはなにかという問いかけは今後も続いていくであろう。
ここで記しておきたいのは、繰り返しになるが、自分で意志決定すること、能動的に生きること、自分の人生の責任を自分がとる覚悟をもつことが「あること」である、ということだ。和辻哲郎は、人間存在を主体的実践的な連関としての主体的なひろがりと呼んだ。[xvii]自分のした決心、自分で選んだことについて責任をもつこと、アランの言葉を用いれば、「喧嘩せずにうまくやること」[xviii]なのだ。いつでも発奮するのに遅すぎるということはない。自ら意欲し創り出していくことこそ、幸福へとつながるだろう。前向きに生きて入ればほしいものは自ずと手に入る。私たちは他人との競争や比較で自分を相対的に評価することで、自分自身の存在意義を実感しがちだが、持っている知識、積んできた経験が異なるのだから、自分と他人は違って当たり前だ。自分を愛すること、自分と仲良くし受け入れることだ。年齢や生活環境で自分の可能性を制限してしまうことなく、自分が心地いいと思える方向でがんばればいい。正解は生きている人の数だけある。重要なのは、自分の正解を実行に移せるかどうか。何をどう組み合わせたら自分のビジョンに近づくのか自分で料理する時代[xix]なのである。
私たちは、妻、母という性役割の前に自分との葛藤を避けて通ることはできない。他人にかまけて一生を終えられる時代ならばよかったが、今は子育て後に45年という年月が横たわっている。いつしか心にポッカリとあいてしまう穴はとても他人が埋められるような大きさではない。自分で埋めるしかないのだ。夫に子供に軸を置いた生き方をしているとその穴を自分で埋める力がなくなってしまう。自分にとって余分なものを削ぎ落とし、「これだけは絶対に捨てられない」テーマを掘り起こしていく姿勢が求められる。自分のテーマが見つかれば、年齢を重ねることの恐怖も減っていく。自分の中に蓄積されていくものを実感できるようになると、年齢は自分の味方になるのだ。[xx]
能動的であることは、アランの記述に沿えば、次のようにも言えよう。われわれはどんなことも、腕を伸ばすことさえ、自分で始められない。誰も神経や筋肉に命令を与えてそれらを始めるわけではない。そうではなく、運動がひとりでに始まるのだ。われわれの仕事はその運動に身を委ねてこれをできるだけうまく遂行することである。だから、われわれは決して決定はせずに常に舵を取るだけである。猛り立った馬の首を向け直す御者のようなものだ。しかし、猛りたつ馬でなければ首を向け直すことはできない。そして、出発するとはこのことだ。馬は活気づき、走り出す。御者はこの奮起に方向を与える。同様にして、船も推進力がなければ舵に従うわけには行かない。要するに、どんな仕方でもいいから出発することが必要なのだ。それから、どこへ行くかを考えればいい。[xxi] 出発しさえすれば、辿り着く港は自ずと見えてくる。大切なのは、自分を生きることだ。
人生では旅人のように、病気に出会ったり、失意に出会ったり、いろいろなことに出会って、その駅で停車したり、あるいはまた進んだりしながら、最後にみんな平等に「死」という終着駅につくのだと思います。死ぬことは、それまでの人生がどんな内容のものであっても、その人なりに精一杯生き、完全燃焼した死であれば、安らかであると私は思っています。現世で起きることがどんなに辛くても厳しいとしても、最後には死という永遠の安息がある。永遠の平和があると、私はいつも思っています。
**************
引用文献、
[i] アラン著、串田孫一・中村雄二郎訳『幸福論』274-275頁、白水社、1990年。
[ii] 山岸健『日常生活の社会学』109頁、NHKブックス、1978年。
[iii] 松原惇子『いい女は頑張らない』210-211頁、
[iv] 松原惇子『OL定年物語』200-201頁、PHP研究所、1994年。
[v] 松原惇子『クロワッサン症候群 その後』119頁。
[vi] 松原、前掲書、56-57頁。
[vii] ヒルティ著、草間平作・大和邦太郎訳『幸福論(第三部)』156頁、岩波文庫、1965 年。
[viii] アラン、前掲書、21頁。
[ix] 松原、前掲書、183-185頁。
[x] 松原、前掲書、241-242頁。
[xi] 大平健『豊かさの精神病理』8-9頁、岩波新書、1990年。
[xii] E・フロム著、佐野哲郎訳『生きるということ』33頁、151頁、紀伊国屋書店、1977年。
[xiii] E・フロム、前掲書、34頁。
[xiv] E・フロム、前掲書、99頁。
[xv] E・フロム著、日高六郎訳『自由からの逃走』284-285頁、現代社会科学叢書、昭和26年。
[xvi] 黒井千次『仮構と日常』28頁、河出書房新社、1971年。
[xvii] 山岸健『人間的世界と空間の諸様相』641頁、文教書院、1999年。
[xviii] アラン、前掲書、75頁。
[xix] 『日経ウーマン 2003年6月号』57頁、日経ホーム出版社。
[xx] 松永真理『なぜ仕事するの?』41-42頁、角川文庫、2001年(原著は1994年刊)。
[xxi] アラン、前掲書、74-76頁。