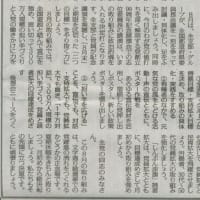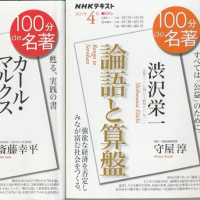東日本大震災後、再生可能エネルギーの必要性が高まった!
しかし、安倍政権は!?
停止していた原発を再稼働させている!
日本経済のため!地域の暮らしのため!
だが地震・火山・津波対策に対する国民の安全安心は?
再生可能エネルギー=太陽光発電で電力が余ったので
危険極まりなし原発再稼働を止めるのではなく
安全安心の再生可能エネルギーの大本を止めさせる!
クロをシロと!シロをクロと考えろ!?
優先順序がさかさまだ!
大丈夫ではない政府自民・公明党!
先生は
子どもの安全をよくよく考えれば・・・・!
どんな屁理屈をつけても、危険なものは危険!
国民の命と暮らし安全安心を切れ目なく守る!
国民の幸福追求権を切れ目なく守るのは
首相である私の責任!
日本最大の「嘘つき」ショーが始まった!
愛媛新聞社説 再生エネ出力制御 普及拡大を止めない対策が急務 2018年10月14日(日)
https://www.ehime-np.co.jp/online/editorial/
九州電力が、再生可能エネルギーの事業者に一時的な発電停止を要請する出力制御を、離島を除き全国で初めて実施した。
東京電力福島第1原発事故を機に、太陽光や風力などの再生エネが急速に普及拡大し、供給過多となる事態となった。出力制御は事業者の導入意欲の減退にもつながりかねない。普及拡大にブレーキをかけないためにも、他地域と電力を融通する体制の拡充や蓄電技術の開発といった対策が急務だ。
出力制御は、供給過多により電力需給のバランスが崩れ、大規模停電(ブラックアウト)が起きるのを防ぐために行った。九電管内は、晴天で太陽光の発電量が増加する一方、冷房の使用が少なく、休日で工場が休業するなどして需要が減ると見込まれていた。他地域へ送電しても調整がつかず、今回は約9800件を対象に出力制御に踏み切った。
供給過多となった要因の一つは原発だ。九電では、鹿児島県の川内原発と佐賀県の玄海原発の計4基が営業運転しており、供給力が底上げされていた。再生エネが原発に追いやられた格好だ。多くの国民が原発に頼らない電力を望んでいるにもかかわらず、安全性に依然として懸念が拭えない原発の稼働を優先させる国や電力会社の方針には異議がある。
再生エネの電源構成比率は、2016年度14.5%で、事故前の10年度の約1.5倍に増えている。7月に閣議決定した国のエネルギー基本計画では再生エネを「主力電源化」すると明記した。原発に固執したエネルギー政策を転換し、再生エネを優先した供給体制を構築することこそ国や電力会社の責務だ。再生エネに軸足を置くことで需要の少ない時期は、計画的に原発や火力発電所を止めるなど、出力制御する前にできることはあるはずだ。
他の電力会社でも出力制御が実施される可能性は高い。四国電力では、秋と同様に需要が低迷する今春5月、伊方原発が停止する中、再生エネの発電量が需要を超えた時間帯があった。猛暑の今夏も原発ゼロで乗り切っている。四電は今月27日にも伊方3号機の稼働を目指しているが、供給面では必要なく、他電力会社への売電目的の色合いが濃い。再稼働を急ぐ理由は乏しいと言わざるを得ない。
エネルギー基本計画で、再生エネの30年度の電源構成比率22~24%とした目標は、達成の可能性が高く、さらなる普及拡大へ導入を滞らせてはならない。ただ、事業用の買い取り価格は大幅に引き下げられ、家庭用も高く買い取る期限が切れる。企業や家庭の負担を抑える制度改革が欠かせない。不安定な出力や太陽光への偏り、自然環境に与える影響といった課題も山積しており、「主力電源化」は、息の長い取り組みとなるが、国や電力会社は、技術力や知恵を駆使して本気で立ち向かわなければならない。(引用ここまで)
朝日 太陽光発電、九電が停止要求の可能性 原発再稼働も一 2018年9月3日08時21分
https://www.asahi.com/articles/ASL8X6QCYL8XTIPE02F.html
東京 九電、太陽光発電を出力制御 原発優先 再エネ後退懸念 2018年10月13日 夕刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201810/CK2018101302000268.html
 |
九州電力は十三日、太陽光発電の一部事業者を対象に、発電を一時的に停止するよう指示する出力制御を実施した。太陽光の発電量が増える日中に、電力供給量が需要を大きく上回ることで大規模停電が起こるのを回避するためで、実施は離島を除き全国初。国が定めたルールでは、原発などの稼働が優先される。今後も電力需要が下がる春や秋の休日に出力制御が頻発する可能性がある。再生可能エネルギーの導入意欲が後退する恐れもあり、政府の再エネ政策が岐路を迎えそうだ。
政府が東京電力福島第一原発事故を踏まえ、二〇一二年に再エネ導入を促す固定価格買い取り制度(FIT)を導入して以降、太陽光などの導入が進んだ。出力制御が頻発すれば事業者収支への影響は必至だ。
電力の需給バランスが崩れると、機器の損傷を防ぐため発電設備が自動停止し、最悪の場合は大規模停電に至る。出力制御は、北海道の地震時に発生した全域停電(ブラックアウト)のような事態を防ぐため、調整順を定めた「優先給電ルール」に基づき実施。先に火力発電の稼働を最大限抑えたり、他の電力地域に送電したりしても供給過多が見込まれる場合に行われる。
出力十キロワット以上の事業者約二万四千件から対象を選ぶ。十三日は四十三万キロワット程度を制御する計画で、熊本を除く九州六県の九千七百五十九件を対象とした。九電の担当者はこれに先立つ記者会見で「対象事業者の選定は公平性に配慮する」と説明した。今回は風力発電の制御は見送った。
一六年度の日本全体の発電電力量に占める再エネ比率は7・8%(水力発電を含めると15・3%)。このうち九州では太陽光発電の導入が進んでおり、送配電網接続量は一八年八月末時点で、大型原発約八基分に当たる八百七万キロワット。
◆導入拡大へ環境整備急務
<解説> 九州電力が全国初の本格的な再生可能エネルギーの出力制御を実施した。再エネ事業者にとっては売電収入が減少することになり、打撃となる。温室効果ガスの排出削減が世界的な課題となる中、導入拡大の基調を後退させないためにも、負担を回避できるような環境整備が急務だ。
東京電力福島第一原発事故以降、政府は固定価格買い取り制度を整備し、再エネ導入を推進。国のエネルギー基本計画では再エネの主力電源化を打ち出し、二〇三〇年度の電源構成比率で22~24%を目指す。一方、買い取り価格を二〇年代半ばには現在の半額以下に引き下げる方針だ。
出力制御とのダブルパンチとなれば、再エネ導入の機運は急速にしぼみかねない。広域で電力融通をしやすくする送電網の増強や、太陽光発電の余剰分を取り置ける蓄電池の増設など、出力制御を最大限回避する仕組みづくりが重要だ。蓄電池の増設などには費用もかさむが、政府や電力会社には、こうした課題解決に向けた取り組みを加速する姿勢が問われそうだ。 (共同・久保実可子)