(1)に引き続いての内容になります。

こちらが基本方針について書かれた資料になります。ここでの注目点は「(4)計画策定のための推進体制及び市民参加」のところです。
第5次総合計画において、公募市民による検討委員会で素案を作成するという点が、鈴鹿市にとっての注目点のひとつでしたが、今回の新しい中・長期計画策定において、市民参画がどれだけ成熟するかもしくは広げられるかが問われていると思います。この点については、このブログの次に体制図を掲載してそこで取り上げます。
「計画策定アドバイザー」について、第5次策定の際は四日市大学の岩崎教授と小林准教授がその任に就かれていました。今回の計画策定においては、資料にあるように慶応大学から迎えることになるということです。
玉村氏は40代で、総合計画が形骸化するのではということから、どのような計画がよいのかをマネジメントのあり方も含め研究されているということです。長瀬氏は60代で、藤沢市OBで政策推進部長を経験していたという経歴をお持ちということです。
同年代である玉村氏には、オープンガバメントの手法を取り入れての計画策定に取り組んで頂くように期待するところです。

こちらが基本方針について書かれた資料になります。ここでの注目点は「(4)計画策定のための推進体制及び市民参加」のところです。
第5次総合計画において、公募市民による検討委員会で素案を作成するという点が、鈴鹿市にとっての注目点のひとつでしたが、今回の新しい中・長期計画策定において、市民参画がどれだけ成熟するかもしくは広げられるかが問われていると思います。この点については、このブログの次に体制図を掲載してそこで取り上げます。
「計画策定アドバイザー」について、第5次策定の際は四日市大学の岩崎教授と小林准教授がその任に就かれていました。今回の計画策定においては、資料にあるように慶応大学から迎えることになるということです。
玉村氏は40代で、総合計画が形骸化するのではということから、どのような計画がよいのかをマネジメントのあり方も含め研究されているということです。長瀬氏は60代で、藤沢市OBで政策推進部長を経験していたという経歴をお持ちということです。
同年代である玉村氏には、オープンガバメントの手法を取り入れての計画策定に取り組んで頂くように期待するところです。
7月8日の市議会各派代表者会議で、現在の第5次鈴鹿市総合計画に続く新たな中・長期的計画の策定についてが、執行部から各派代表者に報告されました。この中・長期的計画については、私自身、第5次総合計画策定時に関係していたこともあり関心の高いところです。また、市議になってからの市の動きを考えても、このような計画の策定はやはり重要だと考えるところです。
今回のブログでは、各派代表者会議で提供された資料から、全体の流れがおおよそ見えると考えるものを取り上げます。
まず、計画策定の背景について。

ここに書かれていることは、ここ2~3年で特にクローズアップされていることが、特に人口減少の面から記述されているといえます。
このグラフを見て頂くと、第5次総合計画の計画期間である平成18年から28年と次の計画期間とでは、次の計画期間は生産年齢人口が坂の下り坂に入っていることがわかります。つまり世の中が大きく変わっていると考えられるのです。
ということは、第5次総合計画策定時よりもより厳しく将来リスクを把握する必要があります。
次に体系のイメージです。

このピラミッドの図は第5次総合計画においても同じもので表現されています。ここで注目したいのは、計画期間を10年ではなく8年としたところで、首長選挙などの政治と実際の行政運営のギャップを小さくするという意味で評価できるのではないかと思います。
一方で、今回は策定についての資料なので仕方がないのかもしれませんが、策定部分についての市民参加だけが記述され、進行や成果のチェック部分にどのように市民参画を取り入れるのかという点が気になります。
ともかく、今回の計画は市民・市議会・行政のすべてに重要なものになると考えています。人口減少社会の中でなにを選択していくのか、より深い部分での住民の合意形成も意識すべきだと考えるところです。
今回のブログでは、各派代表者会議で提供された資料から、全体の流れがおおよそ見えると考えるものを取り上げます。
まず、計画策定の背景について。

ここに書かれていることは、ここ2~3年で特にクローズアップされていることが、特に人口減少の面から記述されているといえます。
このグラフを見て頂くと、第5次総合計画の計画期間である平成18年から28年と次の計画期間とでは、次の計画期間は生産年齢人口が坂の下り坂に入っていることがわかります。つまり世の中が大きく変わっていると考えられるのです。
ということは、第5次総合計画策定時よりもより厳しく将来リスクを把握する必要があります。
次に体系のイメージです。

このピラミッドの図は第5次総合計画においても同じもので表現されています。ここで注目したいのは、計画期間を10年ではなく8年としたところで、首長選挙などの政治と実際の行政運営のギャップを小さくするという意味で評価できるのではないかと思います。
一方で、今回は策定についての資料なので仕方がないのかもしれませんが、策定部分についての市民参加だけが記述され、進行や成果のチェック部分にどのように市民参画を取り入れるのかという点が気になります。
ともかく、今回の計画は市民・市議会・行政のすべてに重要なものになると考えています。人口減少社会の中でなにを選択していくのか、より深い部分での住民の合意形成も意識すべきだと考えるところです。
先日ブログに少し書いた7月8日の敦賀市での勉強会「予算をいじってみよう」ですが、その主旨は予算案に対して修正案を自分たちから出すことで、それを政策提案につなげようというものでした。
講師役は奈良県生駒市の塩見議員で、生駒市議会での減額修正の取り組みを取り上げながら、実際に減額修正案としたときの資料を演習問題形式に構成したものを記入するなど、非常にわかりやすく腑に落ちる説明を頂きました。また名古屋市議会の玉置議員からは名古屋市会における増額修正についての事例説明も聞くなど、非常に有意義な勉強会でした。
さて、予算修正の流れについて、塩見議員作成の資料から掲載させていただきます。
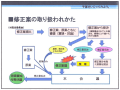
これは修正案に関係する流れの模式図になりますが、おおよそ鈴鹿市議会でもこの流れに近いと思います。
鈴鹿市議会では予算や決算の審議のために予算決算委員会を設置することになっていて、これには議長や監査委員をのぞいた全議員が委員となる全体会と、各常任委員会で担当する分科会があります。そこに通常の本会議に流れもあることになります。
定例会の流れでおおまかに書くと・・・
「 議案説明 → 議案質疑 → 一般質問 → 予算決算全体会(分科会付託)→ 分科会審議・採決 → 予算決算全体会(分科会報告・質疑・採決)→ 本会議最終日(予算決算委員長報告・質疑・討論・採決)」となります。
ということは議員として修正案を出すには、(1)予算決算委員として提案する、(2)3人以上の議員で発議する、の2通りがあり、以前、すずか倶楽部で修正案を発議した際は(2)の流れで行ったといえます。
今回の勉強会で考えたことは、自分で減額修正案を作成できるのであれば、一人の議員としてより直接的に論点を議会に投げかけられるのではないかということです。
ここでも塩見議員の資料から。
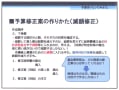
予算としてあがっているけれども事業に疑問があるとき、その予算をカットするということではなく一度財政調整基金などに戻す形を取り、執行部側に再提案を求めることは非常に意義があると思います。どうしても「修正」という言葉に抵抗感を持つ人もいらっしゃったりしますが、このような動きが普通になれば、その報が議論が深まりやすくなると思います。また、市民の方々にも論点がわかりやすくなると言うメリットもあるのではないでしょうか。
どのように自分の活動に活かすのか、また議会としての動きも含めて、しっかり検討しながらできる機会を見つけて実践したいと考えています。
講師役は奈良県生駒市の塩見議員で、生駒市議会での減額修正の取り組みを取り上げながら、実際に減額修正案としたときの資料を演習問題形式に構成したものを記入するなど、非常にわかりやすく腑に落ちる説明を頂きました。また名古屋市議会の玉置議員からは名古屋市会における増額修正についての事例説明も聞くなど、非常に有意義な勉強会でした。
さて、予算修正の流れについて、塩見議員作成の資料から掲載させていただきます。
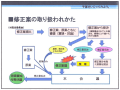
これは修正案に関係する流れの模式図になりますが、おおよそ鈴鹿市議会でもこの流れに近いと思います。
鈴鹿市議会では予算や決算の審議のために予算決算委員会を設置することになっていて、これには議長や監査委員をのぞいた全議員が委員となる全体会と、各常任委員会で担当する分科会があります。そこに通常の本会議に流れもあることになります。
定例会の流れでおおまかに書くと・・・
「 議案説明 → 議案質疑 → 一般質問 → 予算決算全体会(分科会付託)→ 分科会審議・採決 → 予算決算全体会(分科会報告・質疑・採決)→ 本会議最終日(予算決算委員長報告・質疑・討論・採決)」となります。
ということは議員として修正案を出すには、(1)予算決算委員として提案する、(2)3人以上の議員で発議する、の2通りがあり、以前、すずか倶楽部で修正案を発議した際は(2)の流れで行ったといえます。
今回の勉強会で考えたことは、自分で減額修正案を作成できるのであれば、一人の議員としてより直接的に論点を議会に投げかけられるのではないかということです。
ここでも塩見議員の資料から。
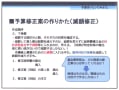
予算としてあがっているけれども事業に疑問があるとき、その予算をカットするということではなく一度財政調整基金などに戻す形を取り、執行部側に再提案を求めることは非常に意義があると思います。どうしても「修正」という言葉に抵抗感を持つ人もいらっしゃったりしますが、このような動きが普通になれば、その報が議論が深まりやすくなると思います。また、市民の方々にも論点がわかりやすくなると言うメリットもあるのではないでしょうか。
どのように自分の活動に活かすのか、また議会としての動きも含めて、しっかり検討しながらできる機会を見つけて実践したいと考えています。
















