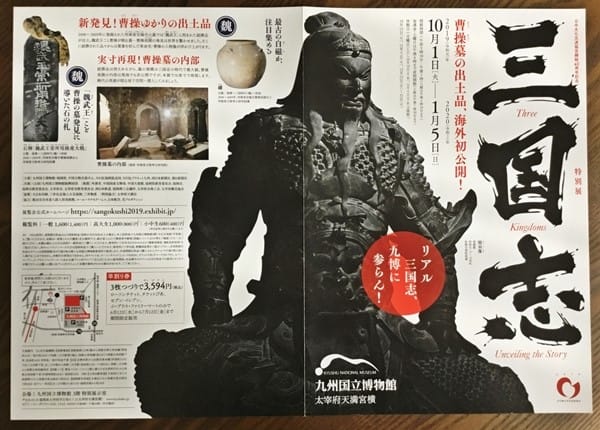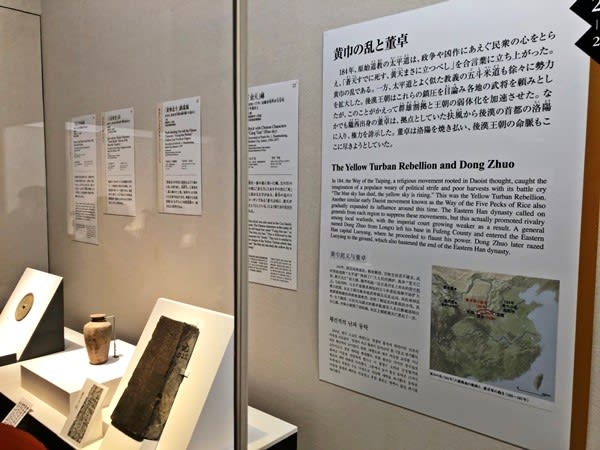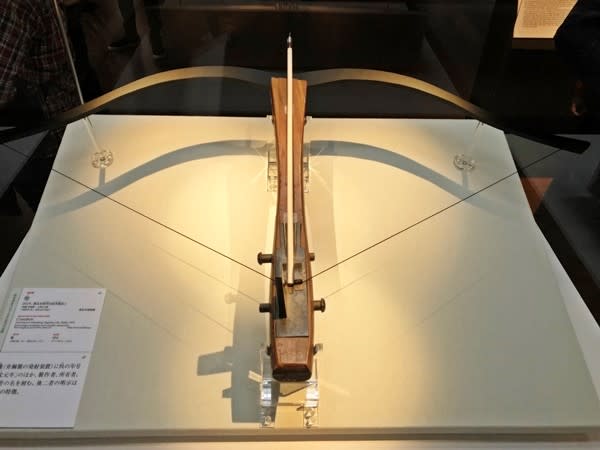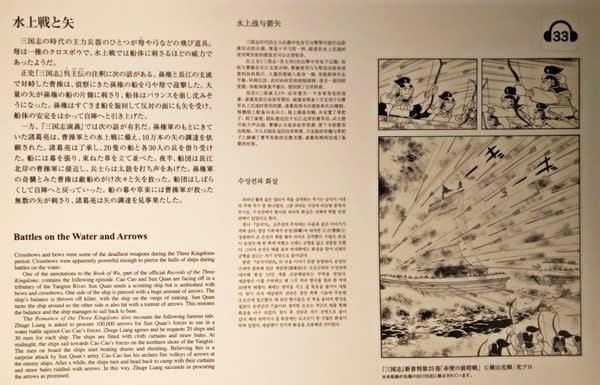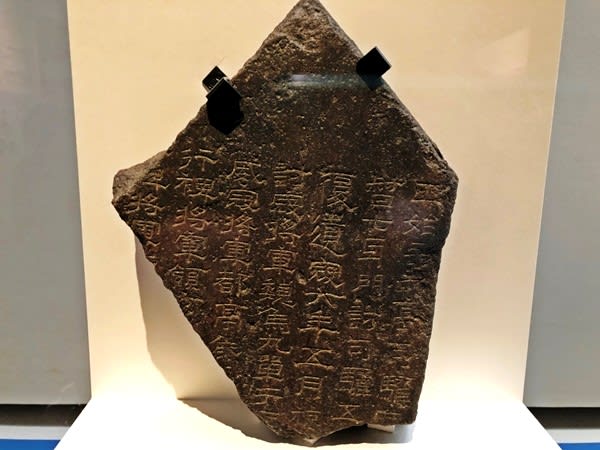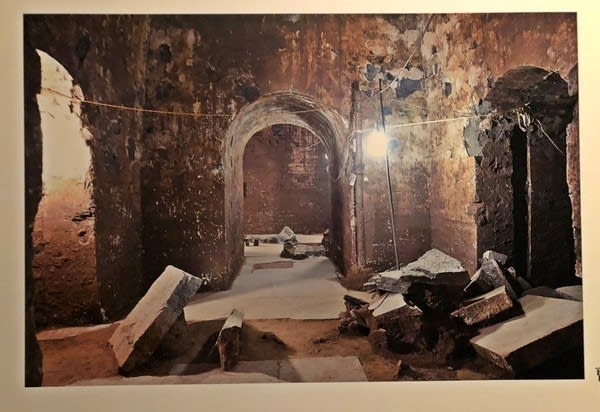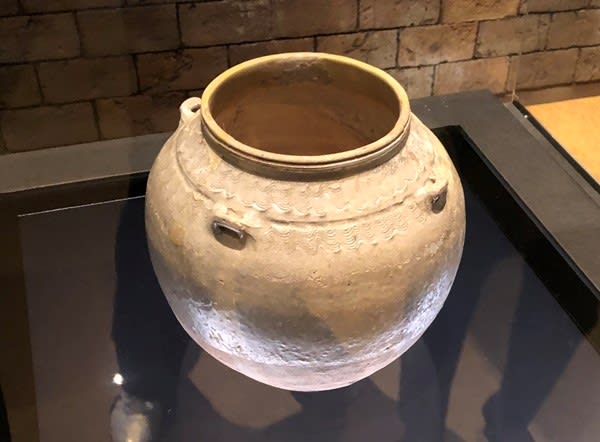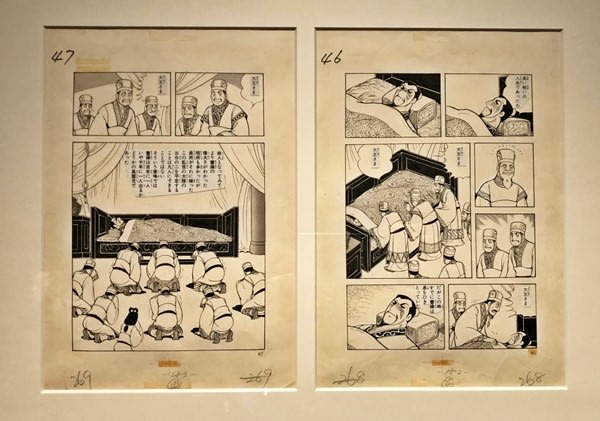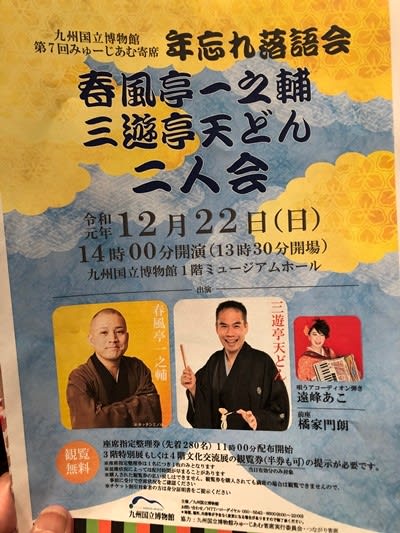太宰府でのランチは、小鳥居小路の古民家カフェ、和気藹々(わきあいあい)で。
メインはスパイシーなグリーンカレーと、ややマイルドなチキンカレーの2種類で、それぞれ単品とセットメニューが選べます。スパイス好きの私たちが選んだのは、もちろんグリーンカレーセット1,100円。

ほどよく効いたスパイスの辛みに、ココナッツミルクが風味を加えていました。

雑穀米に添えられた素揚げ野菜。これがグリーンカレーと実に良く合います。

食後は、コーヒーと紅茶でほっこり。美味しいランチで、いい雨宿りができました (^-^)ゞ

小鳥居小路に面したガラスの引き戸を開けて店内に入ると、右の座敷にテーブルが4卓と、比較的ゆったりとした配置です。押し花をあしらった障子が印象的。このあと立て続けにお客さんが来店し、すぐに席が埋まりました。

築100年を越える古民家を改装した和気藹々。元々は、提灯や傘を作る工房兼自宅だったのだそうです。

小鳥居小路を挟んで和気藹々の向かいにある九州ヴォイス。こちらも古民家を改装した建物です。
いま小鳥居小路周辺では、こうした古い建物をリノベーションしたカフェやギャラリー、雑貨店などが増えているのだそうです。表参道から少し離れただけで、昔の風情を残す太宰府の小径を散策できますよ。

九州ヴォイスは、「九州の地域性豊かで、安心安全な素材を使って丁寧に作りあげた食品や雑貨」を紹介・販売するアンテナショップ。今も昔も、国内外から多くの人が訪れる太宰府から、九州ブランドの魅力を日本のみならず世界に発信するというシンボリックなショップなんです。

糸島のねぎ農家が作るネギ油を使った商品。香りが良くて、いろんな料理に使えて美味しそう。

無色透明の「透明醤油」と、それを使って作られた「柚子舞うぽん酢」は、熊本の老舗醤油醸造元、フンドーダイ五葉が開発。いずれも醤油やポン酢とは思えない美しさで、素材の色そのままに料理を味わえます。

奥は、佐賀県神埼市の「香月さんちのいちご畑」いちごシロップ。
手前は、水巻町のブランド「でかにんにく」を使った「ごはんのともだち水巻でかにんにく味噌」シリーズで、プレーンや京築ゆず、豊前とうがらし、八女小梅、九州地ごま、博多海の幸の6種類があります。

糸島の濃厚ねぎ油と、佐賀県三瀬村の鳥飼豆腐「おからのかりんとう」をわが家のお土産に……。
さっそく使ってみたところ、ねぎの香りゆたかでひと味違う野菜炒めになりました。かりんとうはそのまま食べて良し。ビールに合わせれば更に良し🍺

この後、再び表参道へ。太宰府に来たからには、やはり梅が枝餅は外せませんよね (^-^)ゞ
参道の中ほどにある「かさの家」と、最も天満宮寄りにある「寺田屋」の梅が枝餅を食べ比べ。外はパリッと中はもちっとして、どちらも美味しかったです。(動画は寺田屋さん)
太宰府はなんと6年ぶり。ニュースで伝え聞く混雑ぶりに気後れしてか、ずいぶん足が遠のいていたことに驚きました。次は、九博の「フランス絵画の精華」の期間中、できれば天満宮の梅の時期に合わせて訪ねてみたいと思います。

メインはスパイシーなグリーンカレーと、ややマイルドなチキンカレーの2種類で、それぞれ単品とセットメニューが選べます。スパイス好きの私たちが選んだのは、もちろんグリーンカレーセット1,100円。

ほどよく効いたスパイスの辛みに、ココナッツミルクが風味を加えていました。

雑穀米に添えられた素揚げ野菜。これがグリーンカレーと実に良く合います。

食後は、コーヒーと紅茶でほっこり。美味しいランチで、いい雨宿りができました (^-^)ゞ

小鳥居小路に面したガラスの引き戸を開けて店内に入ると、右の座敷にテーブルが4卓と、比較的ゆったりとした配置です。押し花をあしらった障子が印象的。このあと立て続けにお客さんが来店し、すぐに席が埋まりました。

築100年を越える古民家を改装した和気藹々。元々は、提灯や傘を作る工房兼自宅だったのだそうです。

小鳥居小路を挟んで和気藹々の向かいにある九州ヴォイス。こちらも古民家を改装した建物です。
いま小鳥居小路周辺では、こうした古い建物をリノベーションしたカフェやギャラリー、雑貨店などが増えているのだそうです。表参道から少し離れただけで、昔の風情を残す太宰府の小径を散策できますよ。

九州ヴォイスは、「九州の地域性豊かで、安心安全な素材を使って丁寧に作りあげた食品や雑貨」を紹介・販売するアンテナショップ。今も昔も、国内外から多くの人が訪れる太宰府から、九州ブランドの魅力を日本のみならず世界に発信するというシンボリックなショップなんです。

糸島のねぎ農家が作るネギ油を使った商品。香りが良くて、いろんな料理に使えて美味しそう。

無色透明の「透明醤油」と、それを使って作られた「柚子舞うぽん酢」は、熊本の老舗醤油醸造元、フンドーダイ五葉が開発。いずれも醤油やポン酢とは思えない美しさで、素材の色そのままに料理を味わえます。

奥は、佐賀県神埼市の「香月さんちのいちご畑」いちごシロップ。
手前は、水巻町のブランド「でかにんにく」を使った「ごはんのともだち水巻でかにんにく味噌」シリーズで、プレーンや京築ゆず、豊前とうがらし、八女小梅、九州地ごま、博多海の幸の6種類があります。

糸島の濃厚ねぎ油と、佐賀県三瀬村の鳥飼豆腐「おからのかりんとう」をわが家のお土産に……。
さっそく使ってみたところ、ねぎの香りゆたかでひと味違う野菜炒めになりました。かりんとうはそのまま食べて良し。ビールに合わせれば更に良し🍺

この後、再び表参道へ。太宰府に来たからには、やはり梅が枝餅は外せませんよね (^-^)ゞ
参道の中ほどにある「かさの家」と、最も天満宮寄りにある「寺田屋」の梅が枝餅を食べ比べ。外はパリッと中はもちっとして、どちらも美味しかったです。(動画は寺田屋さん)
太宰府はなんと6年ぶり。ニュースで伝え聞く混雑ぶりに気後れしてか、ずいぶん足が遠のいていたことに驚きました。次は、九博の「フランス絵画の精華」の期間中、できれば天満宮の梅の時期に合わせて訪ねてみたいと思います。