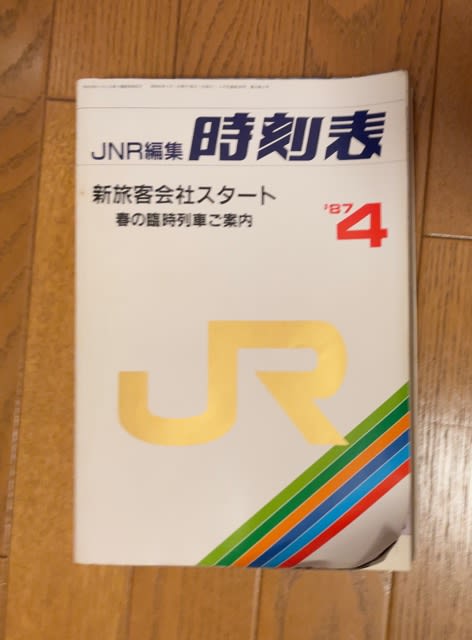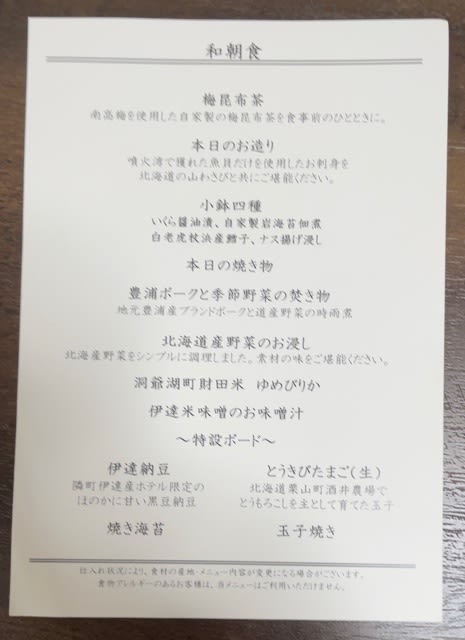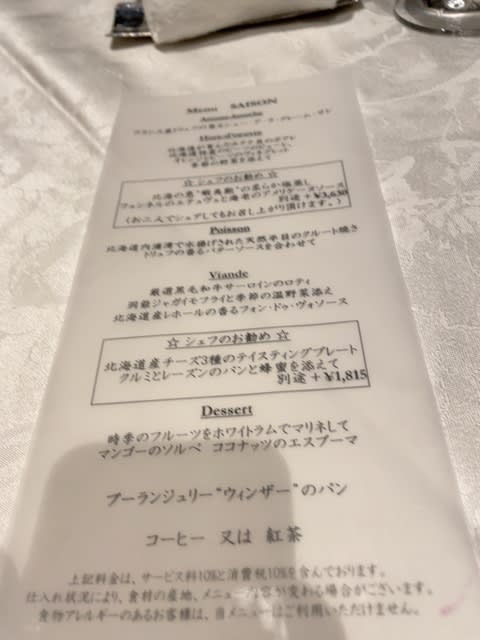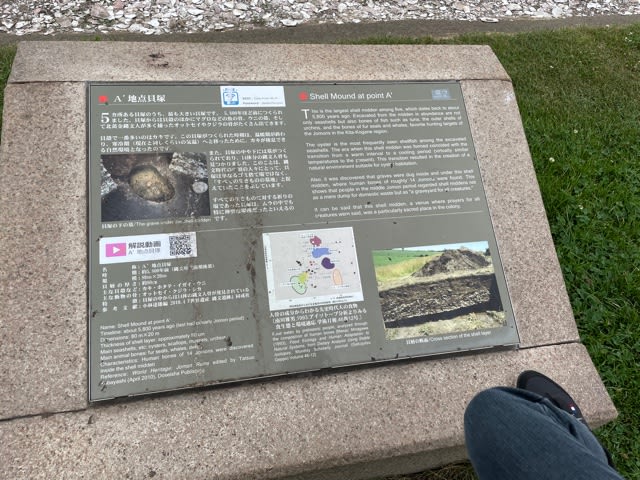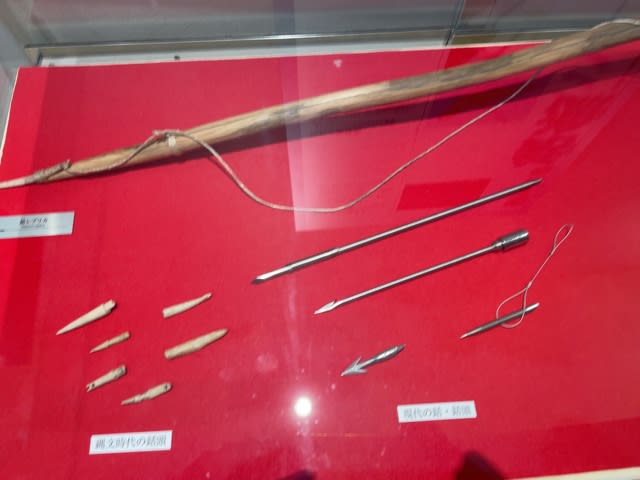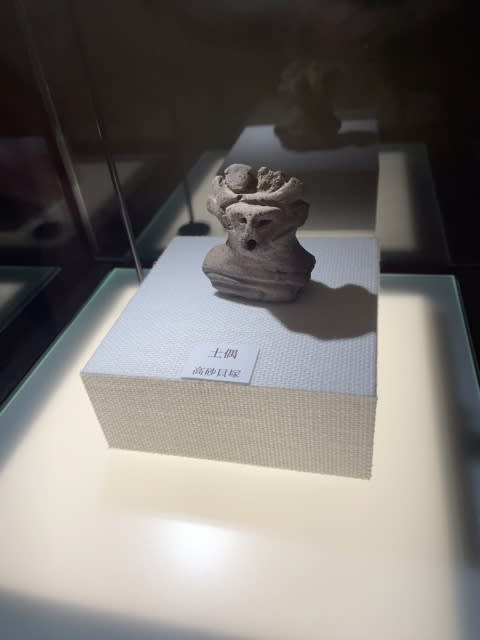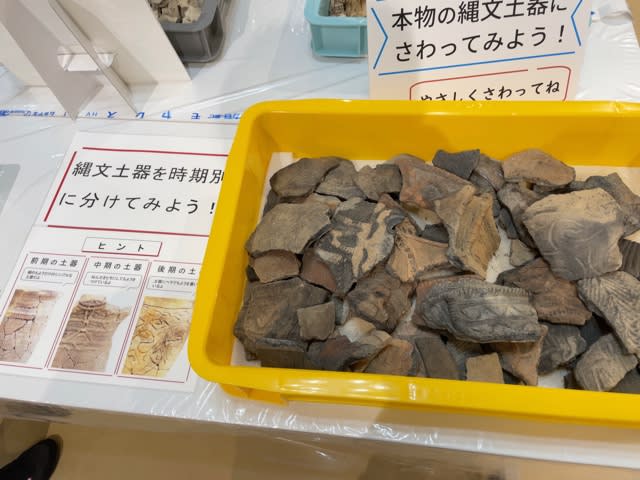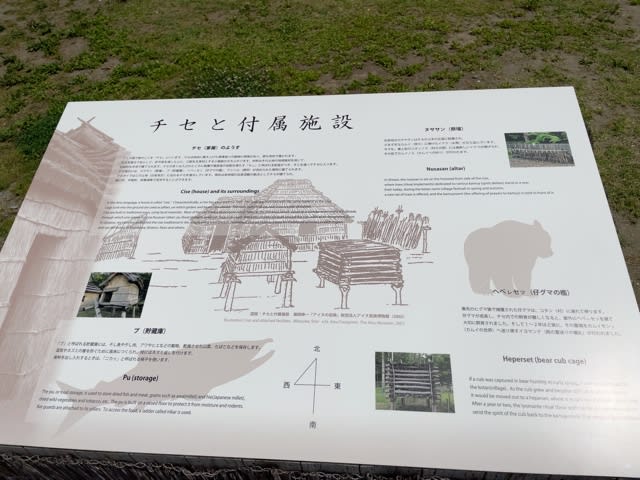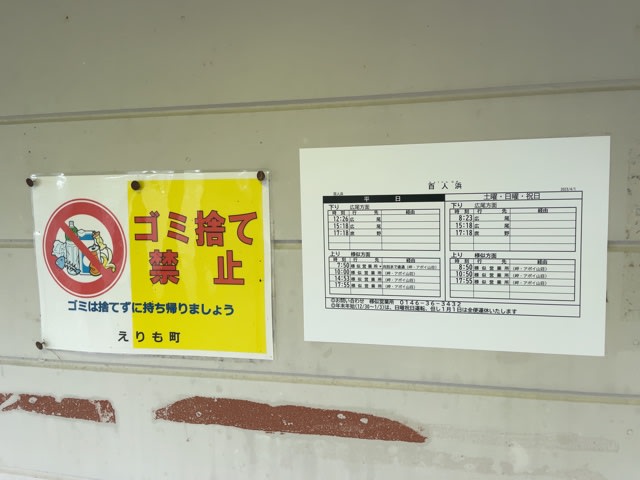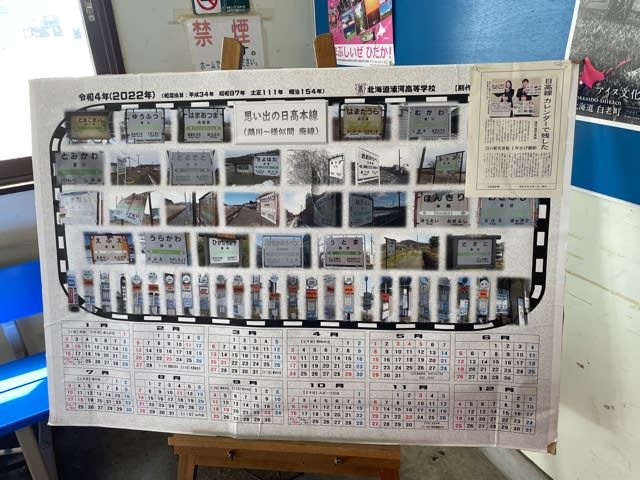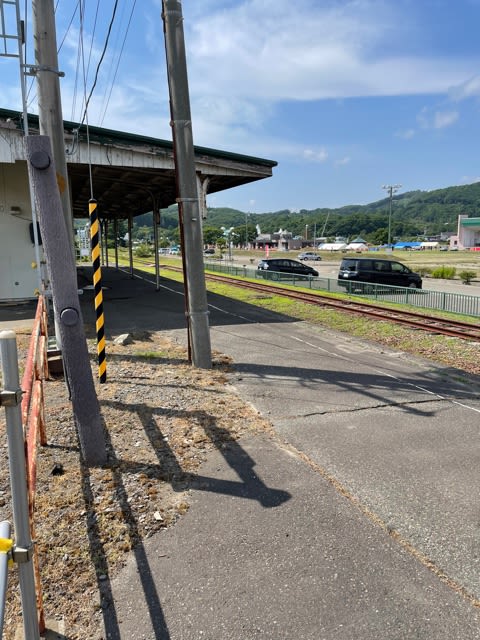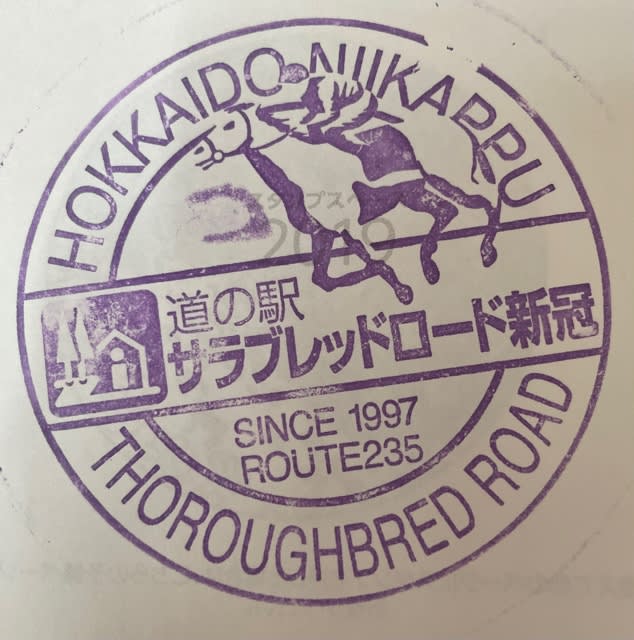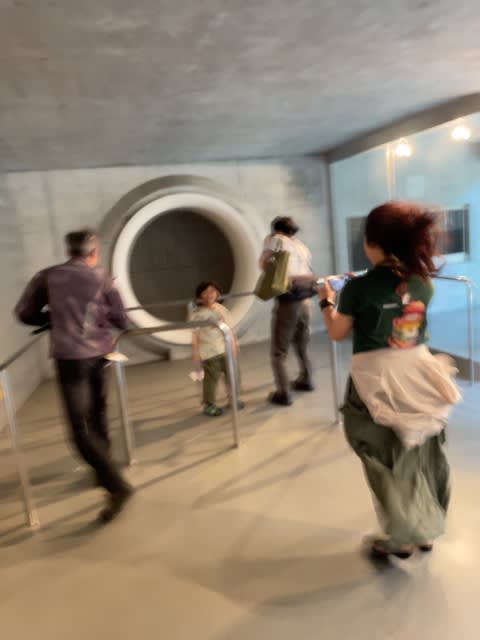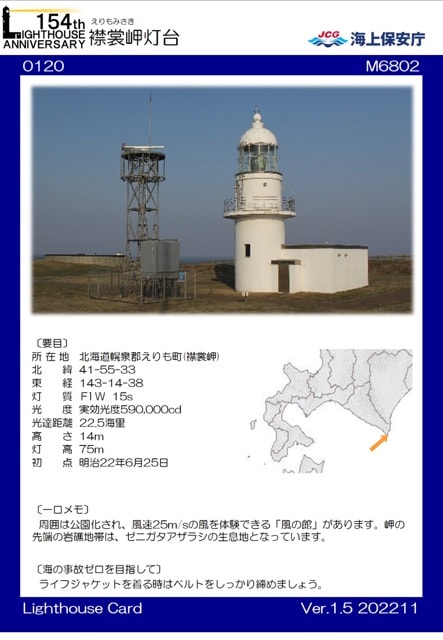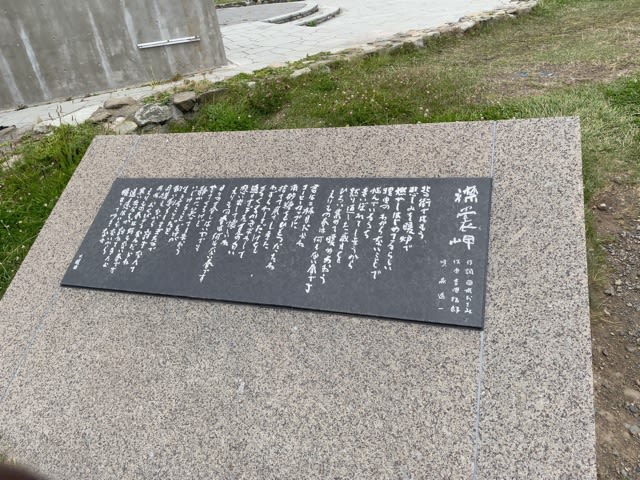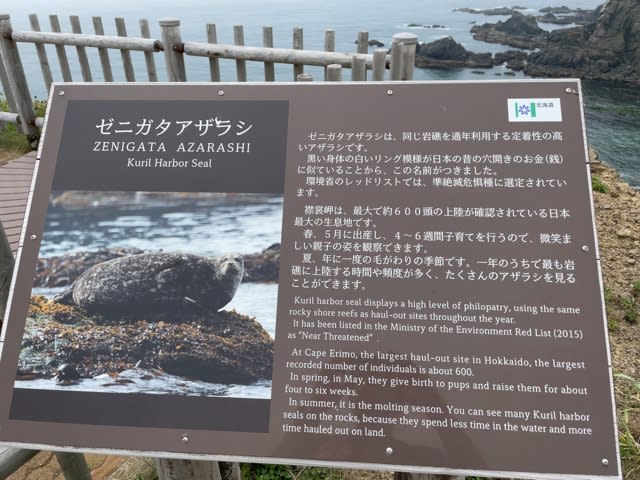6月の旅②。旧軽井沢を諦めた私どもはやむなく白糸の滝ハイランドウェイという有料道路を走る羽目になる。というのは中軽井沢からそのまま国道146号を走れば通行料はいらないのだが、回り道も面倒なのでそのまま。この有料道路は1962年に開通、バスを運行する草軽交通が保有したものでダートの時から金を取っていた。今は流石に舗装はされているが、路盤はガタガタのところもある。

名前の通り『白糸の滝』を通るのだが、逆に言うと白糸の滝にはこの道路を通らないと行けないシステム。500円は入場料と思って走る。三笠、小瀬温泉など草軽交通の前進である草軽電鉄の駅があった所を結んでいる。

20分ほど走ると白糸の滝に到着。無料駐車場に車を止めて歩く。とはいえ歩いて5分ほどで目的地には着く。


ただ、ここまでわざわざ来る人が少ないのか、駐車場はガラガラである。道を右に曲がると湯川の支流が流れていて涼しくなる。大きな木が倒れていたり、お化けのように大きなシダが群勢していたりと自然たっぷり。


壁際にはびっしりとスギゴケが生えていてその中にカタツムリを発見。

もう少し登ると滝が見えてくる。那智の滝や華厳の滝のように太い流れが一本というより周囲に滝のカーテンをかけたように約70mの幅で岩の間から水が染み出して糸のように流れている。白糸の滝のネーミングのうまさに感心。


説明板によると浅間山に降り注いだ雨水が滝に流れ落ちるまで6年もかかるとのこと。水温は11.8℃と地熱の影響もあり、やや高めである。
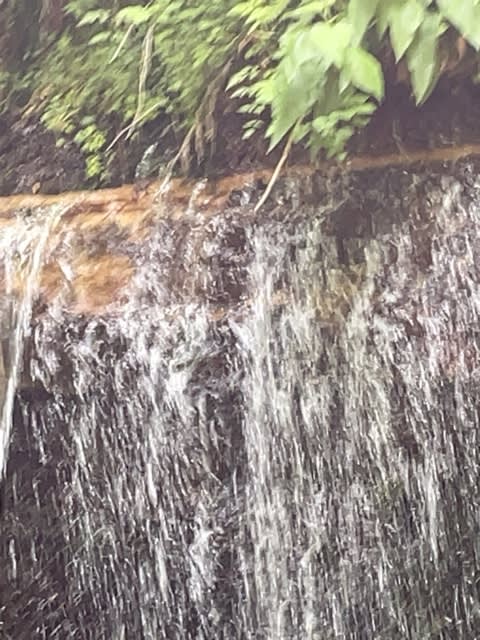

再度、車に乗り、峰の茶屋まで走る。ここまでが有料道路、四差路を右に曲がり、国道146号を走る。このあたりから見る浅間山が美しい。

そう言えば亡くなった父親が浅間山の見える別荘が欲しいと買ったのだが、少し経つと周辺の樹が繁り、浅間山が見えなくなって残念がったことをなぜか思い出した。(以下、次回)