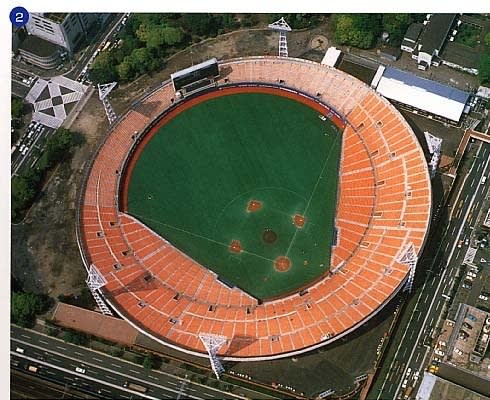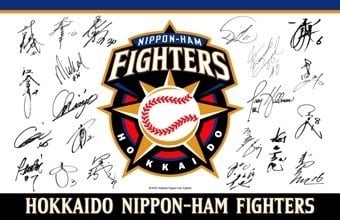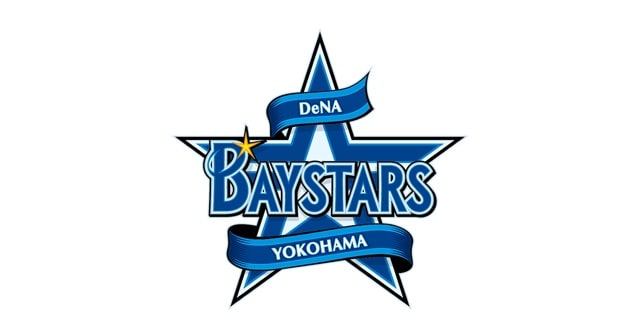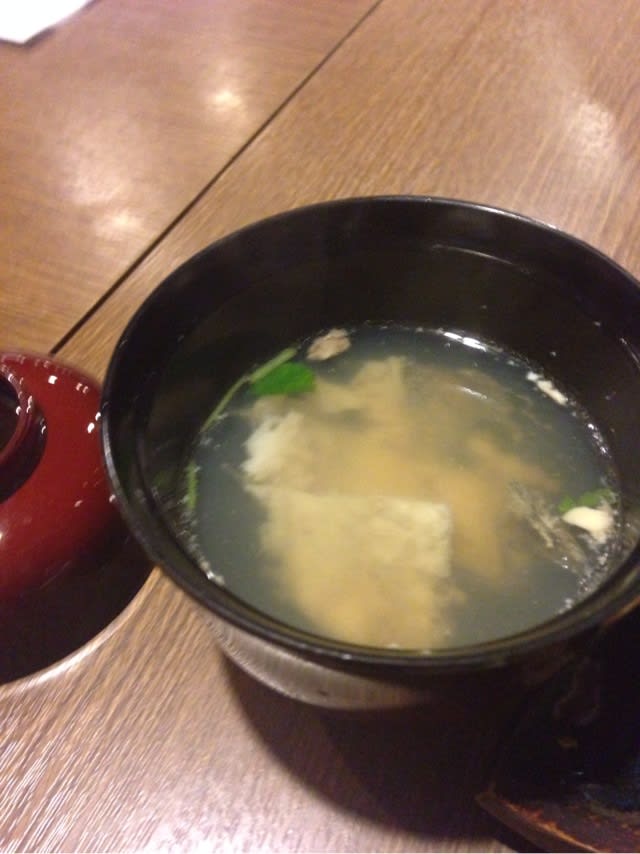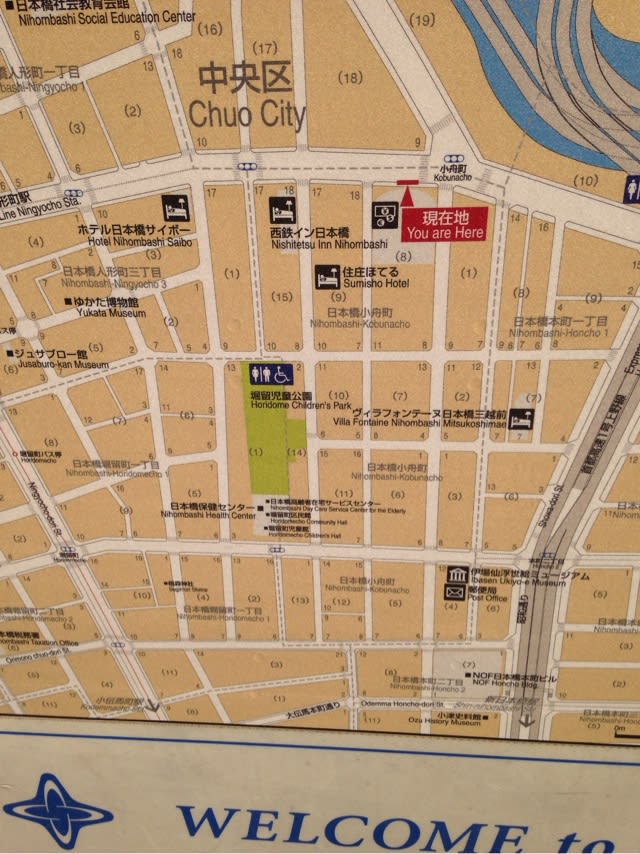切手シリーズ その24。今回は記念切手に描かれた橋がテーマ。日本はご存知の通りの島国で、海が荒れても安全に通りたいというと悲願が叶うものという存在が橋である。その歴史を見ると日本の高度成長を垣間見た気がする。

ただ、初めて橋の記念切手は先日もブログで取り扱った観光地百選の6集、河川の部で登場する『宇治川』に架かる『宇治橋』(1951.8.1)24円切手である。


そして9集の渓谷に登場する『昇仙峡』の『長潭橋(ながとろばしに )』(1951.10.15)24円切手、10集の建造物に登場する『錦帯橋』(1953.5.3)10円と24円切手と続く。

まあ、今回は産業や交通の発達に伴う開通を記念したものに焦点を当てると初めて切手になったのは若戸大橋開通記念(1962.9.26)10円切手。これは縦長の構図に赤一色で良く目立ち、印象深い。若戸とは北九州市発足直前の若松市と戸畑市をつなぐ2.1kmのつり橋の開通を記念したもので、洞海湾を渡る当時画期的な橋。当時、地元では若戸大橋大博覧会なるものも開催されるほどだった。

因みに翌年(1963.2.10)には北九州市発足記念の記念切手も発行されている。
次は天草架橋完成記念(1966.9.24)15円切手で天草5橋全景を小さな切手に納めている。

この橋も船に乗らなければどこにも行けなかった天草島の人には大きな出来事であった。

また、本州と九州を結ぶ関門橋開通記念(1973.11.14)20円切手は横長で落ち着いたトーンである。


そして全国規模で今のところ最後に発行されたのが、瀬戸大橋開通記念(1988.4.8)60円切手連刷4枚。これは香川県側からみた風景と岡山県側から見た風景が2枚ずつの構図である。
ではそれ以降はというと1989.4からスタートしたふるさと切手の形で橋の開通も発行されるようになった。レインボーブリッジ(東京・1997.10.1)、明石海峡大橋(兵庫・徳島・1998.3.20).しまなみ海道(広島・愛媛・1999.4.26)などであるが、規模の縮小は否めない。ただ例外なのが最後のしまなみ海道開通の記念切手で10枚発行、さらに小型シートも出されている。



これだけの橋の切手を見て、小生が最も好きなのはシンプルながら迫力のある若戸大橋である。これはまだまだ発展途上にあった時代であったからかもしれない。