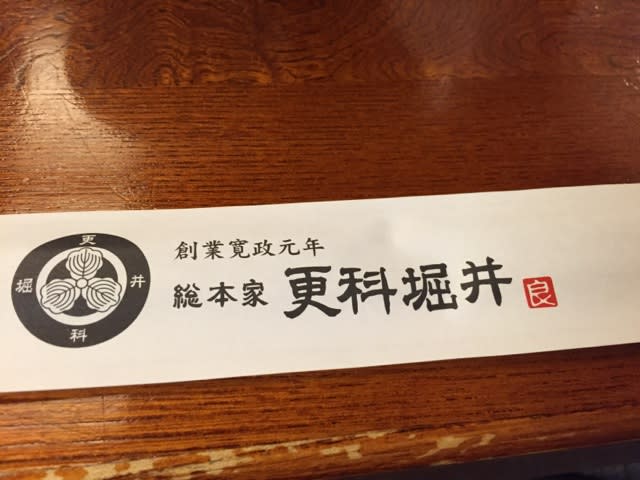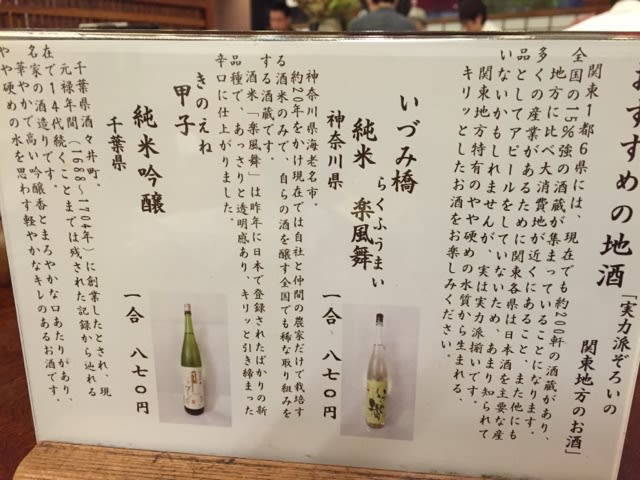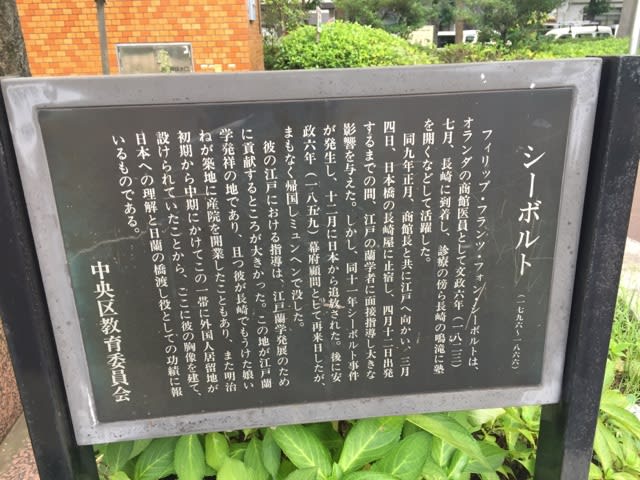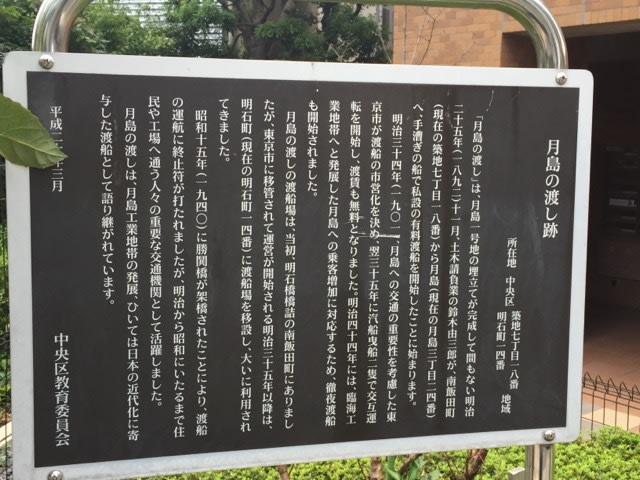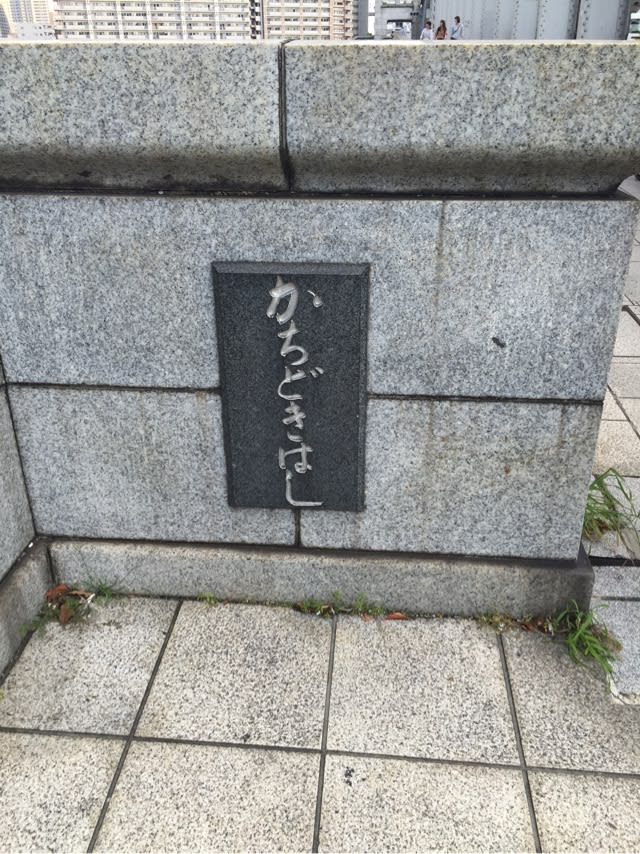『江戸の坂・東京の坂』その54。今回は赤羽北部にある坂道を歩いてみた。北区赤羽は1885年に日本鉄道の駅が出来るまでは一寒村であった。しかし、宿場町の岩淵宿に鉄道を通すことに反対があり、止む無く駅が作られ、品川との間を結んだのが今の山手線の始まりであり、その後の発展はご存知の通り。ちなみに『赤羽』の起源は赤土の多い土壌からこの名前が付いた。



赤羽駅西口を降りると前にバスターミナルがあるが、左の線路際の道を行くと、すぐに左に曲がる道が出てくる。細い道を行くと道がS字に曲がり登り坂になるが、これが『大坂』である。どう見ても大きくないが、坂の案内によるとこの坂道は旧板橋街道に繋がる坂道であり、かつては清瀧不動にあった坂に『小坂』と付いていたため、その対比でこの名前になったらしい。ちなみに狸坂の異名を持つ。



坂を一旦おりてヤクルトの販売所の前を通り、次の信号を左に曲がると右にカーブしていく坂道に出る。この坂道が『うつり坂』である。その後は名前の起源は明らかではない。この坂は旧板橋街道にあたり、戦前には坂上に被服本廠があったため、通ることのできない時期もあったが、戦後その後に赤羽台団地ができて今に至る。今はその赤羽台団地も建て替えのまっ最中で、奥には新しい棟、手前には古い棟が並んでいる。


坂上を右に曲がると八幡小学校の前に出るが、右に降りていく坂道が『八幡坂』。坂の下に赤羽八幡神社の入口があるため、この名前が付いた。これまでの3本の坂は全て弓なりにカーブしている。



坂を下りると赤羽八幡神社の入口に出る。再び坂を登って神社に行くが、この坂には名前はないものの、今回の坂では最も急坂。赤羽八幡神社はその縁起ははっきりしないが、坂上田村麻呂が蝦夷征伐の際に創ったと言われ、その後、源頼政、太田道灌などにも庇護され、徳川家からも7万石の朱印をもらっていた。



坂道を上るが、この神社は東北新幹線赤羽台トンネルの上に位置する。そして振り返ると赤羽台団地など一望できる。



帰りは神社の石段を降りて、神社入口に戻り、隣の坂があるが、これが『師団坂』。現在は星美学園が頂上にあるが、戦前は旧陸軍近衛師団と第一師団に属する工兵大隊があった。そしてこの坂は明治22年に工兵大隊ができた際に作られたもので、今も『師団坂通り』と呼ばれている。

他にも赤羽駅西口には坂道が多くあり、再訪してみたい。

































 魚(アロワナ、ピラルクー、オオカミウオ)やデンキウナギ、そしてテッポウウオ、クラゲ、イソギンチャク、チンアナゴ、タコなど水族館らしいオーソドックスな魚たちのコーナーになり、熱帯魚などが続くのだが、これだけの種類の魚を久々に見るとなかなか楽しい。
魚(アロワナ、ピラルクー、オオカミウオ)やデンキウナギ、そしてテッポウウオ、クラゲ、イソギンチャク、チンアナゴ、タコなど水族館らしいオーソドックスな魚たちのコーナーになり、熱帯魚などが続くのだが、これだけの種類の魚を久々に見るとなかなか楽しい。