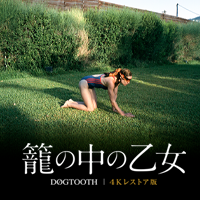映画「籠の中の乙女」を観た。
2023年製作の「哀れなるものたち」と2024年製作の「哀れみの3章」のヨルゴス・ランティモス監督が2009年に製作した作品である。やはりランティモス監督に通底する、支配とセックスと死がテーマとなっている。3作品とも実験的な作品だが、本作品は物語そのものが壮大な実験の記述となっている。
下世話な話で恐縮だが、世界一セックス頻度が高い国がギリシアだそうで、本作品はギリシア映画だから、食事のシーンと同じくらい、セックスのシーンが登場する。ちなみに日本のセックス頻度は飛び抜けて低いというアンケート結果がある。邦画にセックスシーンが少ないのは、そもそもセックスが日常的ではないからという理由が濃厚である。
子どもたちを外へ出さず、知識と経験を限定したら、どのような人間に育つのか。ひたすら従順に、勤勉に、正しく育つだろうという両親の思惑は、途中まではうまくいっていたように見えるが、思春期を迎えて歪みを生じたようで、その時期を描き出したのが本作品である。
健康に育った子どもたちには、食欲と性欲を満たしてやる必要がある。食事には食材が必要で、セックスには相手が必要だ。それらは外界から調達するしかなく、家の外との僅かなつながりは、避けようがない。夫婦が最も苦心しているところだ。子どもたちが覚えてしまった不適切な言葉には、本来とは別の意味を与え、家の外は恐ろしい場所で、自動車でしか行くことができないと教え込む。
子どもたちの知識欲と自由への欲求不満は凄まじく、暴力や悪意となって現れる。兄弟を傷つけたり、飛行機を見て、落ちればいいと願ったりする。飛行機については、目視で確認できるものだから、両親も正確に説明せざるを得ず、たくさんの人が乗っている認識がないことは考えにくい。落ちればいいと願うのは、明らかな悪意である。自由には、悪意も含まれるのだ。
個人が頑張っても限界があるが、共同体が家族よりもずっと大きくなって、たとえば国家ならどうか。北朝鮮を扱ったドキュメンタリー映画を見る限り、情報の制限は、国家指導者に対する無条件の尊敬と服従を徹底できたように思える。しかし脱北者が存在するということは、どこかに破綻があるのだ。
ジョージ・オーウェルの「1984」にも通じるような、国家的な洗脳を、家庭における思考実験として映画化した作品に思えた。メタファーとしてのヒントはいくつも散りばめられていて、微かなヒントからでも、子どもたちはものごとの本質に辿り着こうとする。それは人間という存在の可能性を示しているとも言える。意欲作である。