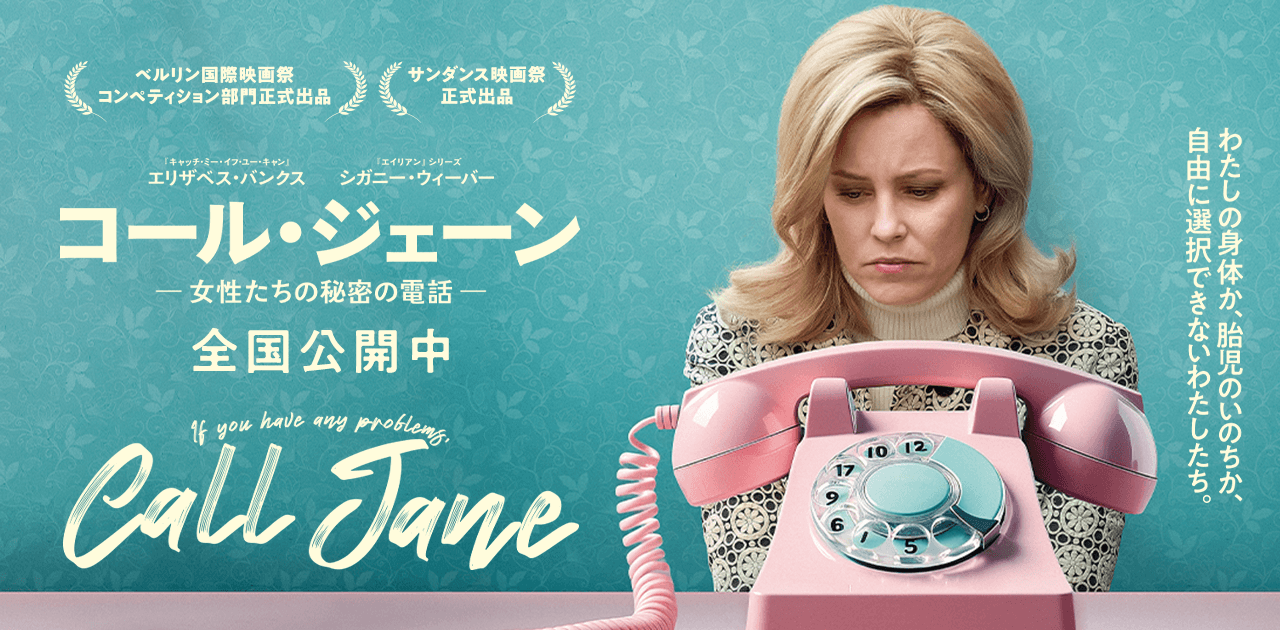映画「オッペンハイマー」を観た。
ロバート・オッペンハイマーの伝記である。若い天才物理学者が30代でマンハッタン計画の責任者に任命されてから、開発した原子爆弾2発が実際に使われるまでの話が主体だが、並行して、マッカーシーが主導した赤狩りで尋問を受けたときが描かれる。ルイス・ストローズの公聴会の部分は、オッペンハイマーが尋問を受けた話の補完のような役割だ。
学生時代、理論には優れているものの、実験が不得手であった過去が紹介されているのは、地上での等速直線運動の観測系における実験物理学に嫌気が差して、理論物理学に傾倒していく様子を描くためだと思う。実験下手の過去を、世界最大の物理学実験である原爆実験に対比させる狙いもあったかもしれない。
思索の人らしく、終始冷静な態度を崩さない。感情を露わにしたのは、終戦後にトルーマン大統領と面会した場面だ。「私の手は血に塗れているようだ」と話すと、トルーマンは問題を単純化し、原爆の製造者は責められない、責められるのはそれを落とした人間だと言い放つ。そしてオッペンハイマーを泣き虫だと決めつける。トルーマンは、自分が無慈悲で想像力の欠如した人間だと自ら露呈した訳だ。
オッペンハイマーの苦悩の複雑さは、単純化できるものではない。言い訳はたくさん考えられる。世界には優秀な物理学者がたくさんいて、自分が開発しなくても、誰かが原爆を作っただろう。原爆を作ったのは、核分裂の連鎖反応が百万分の1秒という短時間で確実に起きることを確かめるためでもあった。原爆実験をすることでその威力に恐れをなして、逆に原爆が使われないようにするのが目的だった。抑止力としての役割に過ぎないのだ。自分の役割は原爆を作ることで、使うことではない。などだ。
しかし原爆投下のあとに調査に入った米軍の撮影した映像を見て、あまりの悲惨さにおののくシーンがある。どんな言い訳をしても、自分がこの大量殺戮に加担したのは間違いない事実だ。原爆が使われる前には、爆発で直接的に死ぬ人数、放射能に被曝して短期間のうちに死ぬ人数まで計算していたし、その数字はほとんど合っていた。これで自分の手が血に塗れていないとは決して言えない。
問題を単純化して白と黒を分けるのが好きなのは、世界中どこの国民も同じだ。複雑さを複雑さのままで理解しようとする人は少ない。アメリカの政治家や官僚も同じで、アメリカが善で日本が悪、だから原爆は善という単純な理屈を信じ、戦後は、資本主義が善で共産主義が悪という独善が猛威をふるった。共産主義国との共存を模索したJ・F・ケネディは、反共という独善の犠牲者だ。
本作品のテーマは、オッペンハイマーの苦悩を余さず伝えるだけではないと思う。戦禍で国民が悲惨な目に遭っても、過去を忘れ、年寄の話を無視して戦争を繰り返す人類に対する、ひとつの警鐘でもあるのだろう。人類はいつまで無自覚なアホであり続けるのか。