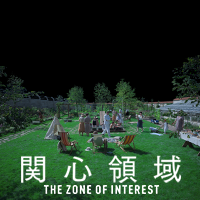映画「FARANG」を観た。
登場人物はもれなく頭の悪そうな連中ばかりで、何でも暴力で解決しようとする。主人公も例外ではない。誰にも感情移入は出来ないが、アクションはいずれも迫力がある。それにとても痛そうだ。ゴア描写は控えめだが、逆にリアリティがある。血の色は本物みたいだ。
登場するタイの市井の人々や、レディボーイたちは、そういう暴力の世界と隣り合っていることを自覚しつつ、なんとか上手くよけながら、ギリギリの状況で生きている。このあたりの描写はとてもいい。しぶとく生き延びるのはこういう人たちだろう。暴力で支配するのは一時的で、長くは続かない。なんとなく諸行無常を感じてしまった。
映画「三日月とネコ」を観た。
ネコ好き3人が一同に介する序盤は、コミュニケーションのぎこちなさが目立って、どうなることかと心配だったが、小林聡美が演じる小説家が登場してからは、物語に安定感が生まれた。やっぱり確固とした世界観の持ち主がいると、人間関係が締まる。
上村奈帆監督は、杉咲花主演の「市子」の脚本を担当しただけあって、日常的な台詞の中に、どこかアンバランスな要素を入れ込む。うまくいっているように見えた人間関係は、実は微妙なバランスで、かろうじて平衡を保っていただけだとわかる。
何度かレビューに書いたが、人生は幸せと不幸せのまだら模様だ。出会いがあれば、必ず別れがある。人生の達人は、素直に喜び、素直に悲しむ。幸せの時間は短く、不幸の時間は長い。やってきた幸せのひとときを、一期一会として楽しむことだ。いま、このときは、二度と来ない。
ネコを可愛がる人々がいる一方で、ネコをいじめる族(やから)もいる。無責任に捨てる者もいる。ネコに対する姿勢は、そのまま人生への対し方でもある。肯定的か否定的か。愛しい人に愛しいと伝えることは自分と周りの人たちを幸せにするが、嫌いな人に嫌いだと伝えることは、誰も幸せになれない。それは単なる悪意にほかならない。
ネコはどうだろう。可愛がってくれる人には、ゴロゴロと喉を鳴らす。かといって自分を無視する人を攻撃する訳ではない。捨てる人やいじめる人もいるが、恨みはしない。自分に危害を及ぼしそうな相手には全力で戦う。どんな相手にでもひとりで立ち向かうのだ。人間よりもネコのほうが、よほど潔い。
保護ネコを世話する施設の人は、飼育を途中で放棄することが許せない。川上麻衣子が演じた施設長は、終生飼育という言葉を使う。ひとたびネコを飼うと決めたら、そのネコが一生を終えるまで、責任を持って飼うということだ。自分がネコより先に死んだ場合のことも、ちゃんと準備しておかねばならない。
ネコに悪意はない。それどころか、一生のうちの大切な時間を自分のために費やしてくれる。これほど愛しい存在は他にないだろう。ネコに感謝できる人は、他人にも感謝できる。そして他人からも感謝される。幸福な時間は、肯定と感謝にあるのだ。
ほのぼのとしているが、人生に対する洞察がある。大切なものをただ大切にするだけでも、一定の覚悟は必要だ。しかしそうすることで人生は豊かになり、幸福の時間が増える。そういう作品だった。
実はこういう映画は、台詞や表情にたくさんの機微を盛り込むことを求められる、役者陣にとって大変な作品なのだ。小林聡美はもとより、安達祐実と倉科カナの名演に拍手。
映画「若武者」を観た。
二ノ宮隆太郎監督の前作「逃げ切れた夢」は、光石研の名演もあって、悪くなかった。痴呆症になるのを恐れながら定年を迎えた主人公が、還暦になってもまだ迷っている。これまでひた隠しにしてきた本当の自分自身をさらけ出してみせるところがとてもよかった。
どうやら二ノ宮隆太郎は、本音をさらけ出す作品を作りたいみたいで、本作品でも本音を言う若者たちを描くのだが、若者にはまだ気取りがある。変に自分を飾ったり、マウントしてみたりするのだ。だから本当のことを言うのに、ねじ曲がった言葉を使ってしまう。
社会のルールは守る。仕事も上手くこなす。しかし上辺を取り繕うこの社会が気に入らない。三人は、三者三様に表現する。分かってもらえることはないが、それでもいい。たまに本音を言って、そして歳を取っていくのだ。歳を取れば、衒いや虚勢が消えて、素直に自分のことが言えるかもしれない。あの喫茶店のマスターのように。
本作品も、悪くなかったと思う。
映画「バティモン5 望まれざる者」を観た。
同じラジ・リ監督の「レ・ミゼラブル」でも、唐突なラストシーンに面食らったところがあったが、本作品のラストシーンも意見の分かれるところだと思う。イスラム青年ブラズは火をつけるべきだったのかどうか、犠牲者を出すべきだったのかどうか。
アビーはブラズに対して、口癖のように「どうして怒るの」と言う。怒りは憎しみになり、憎しみは暴力につながることを懸念しているのだ。ではアビーが怒らないかというと、そうでもなく、ものに当たることもある。しかしなるべく怒らないように感情をコントロールしている。暴力は絶対に振るわない。
しかし臨時市長のピエールは別だ。自分で暴力を振るわずとも、警察という暴力組織を指揮することができる。ピエールは裕福で、困っている人々の気持ちが理解できないし、理解するつもりもない。政治家は政党の権益を守り、地域を統治するのが仕事だと思っている。加えて、移民たちが自分や家族を襲いはしないかという被害妄想もある。現に妻の自動車は被害を受けた。ここは先手必勝だ。
ピエールは私腹を肥やすタイプではなく、真面目に職務をこなそうとしているだけだが、人間を理解していないから、自分の思い通りに人々を従わせようとする。臨時だから、おそらく任期は前任者の残りである短い期間だ。性急に結果を出そうとするあまり、暴力装置を使って無理な計画を強行する。
人々の多くは反発を覚えながらも自分の無力を自覚し、諦める。しかしブラズは別だ。怒りが憎悪となり、沸点に達して暴力の発露に至る。ブラズがテロリストになると、臨時市長は被害者となる。可哀想な遺族として、執務することになると、移民たちの立場はますます悪くなるだろう。アビーが心配していたことが現実になる。
ラストシーンをどうするか、製作側も悩んだだろうと想像するが、本作品のラストがギリギリの選択だったのだろう。たくさんの問題を炙り出した作品だ。
映画「ブレインウォッシュ セックス-カメラ-パワー」を観た。
アメリカの黒人が「Black Lives matter」と叫んで、自らの権利を主張した運動がひとしきり続いた後、コロナ禍のアメリカで、黒人の大男が東洋人の老婆を殴り倒す動画がニュースで紹介された。コロナ禍は東洋人が原因だというのが殴った理由らしいが、とても嫌な印象を受けた。
まず第一に、どんな理由があっても、丸腰の老婆を大人の男が殴り倒すのは人間として間違っている。第二に、東洋人をカテゴライズして全員を憎悪するのは、黒人差別の図式と同じだ。
本作品では、映画において、力のある側が、力のない側の人権を蔑ろにする構図が紹介されている。こういう構図は映画に限らない。取り立てて新しい視点はないが、客体化という言葉に二重の意味を持たせているところが面白い。
ひとつめの意味は、客体化=性的対象として見る、見られること、またはそのように扱う、扱われることである。主に女性が客体化されている。もうひとつの意味は、自己客体化である。性的対象として見られ続けた結果、女性自身が性的対象としての自分を意識する訳だ。
鏡を見る、化粧をする、流行のファッションや際どい衣装を身に着ける。女性自ら、男性の視点を取り入れているのだ。それはつまり、性的な魅力が大きいほど、生きていくのに有利であることを自覚しているということだ。だから女性の映画監督でさえ、ストーリーやテーマに関係のないヌードシーンや女性の体のアップを撮ってしまう。
沢山の映画を観ている観客のひとりとして思うのは、本作品が指摘する男性視線や女性の客体化は、主にアメリカ映画の話であろう。作品もそうだし、映画祭や映画賞の際の女優たちの、ほとんど裸みたいな衣装もそうだ。日本アカデミー賞の授賞式の女優たちの衣装は、それなりに着飾ってはいるものの、シックなドレスや和服が多い。邦画で女体を舐め回すようなカメラワークは観た記憶がない。ポルノではないのだ。
日本では今ひとつ浸透しきれていないレディ・ファーストの習慣は、ある意味では女性蔑視の現れである。日本の男性は女性に対してそれほど積極的に関わろうとしない面がある。それはモラルが優れているわけではない。親しき中にも礼儀ありの精神と言えばよく聞こえるが、人と人との関係性が希薄というか、要するに気が弱いのである。揉め事を嫌う国民性が、他人に対する要求の度合いを低くしている。
逆に言うと、他人に強く要求できる、自分本位の独善的な人間に逆らえないということでもある。一億総自己客体化だ。声の大きな軍国主義者が力を持つと、誰も逆らえない国であることは、戦後も変わっていないのだ。羊も結託すれば狼に勝てるかもしれない。諦めて沈黙していると、狼のいいようにされる。
本作品には、私たちは黙っていない、自己客体化もやめるという、強い意志のようなものを感じた。そこはアメリカのいいところだろう。ただ支配側も強い意志を持っている。せめぎ合いは日本みたいにさざ波のようではなく、荒れ狂う嵐になる。しかもアメリカは銃社会だ。どうなることか。
映画「ありふれた教室」を観た。
教育現場が舞台の映画を観るたびに、国ごとにずいぶん状況が違うんだなと感じる。アメリカやフランスの映画では、教師は割と自由で、生徒と同じくらいに登校して、授業が終わるとさっさと学校を出て、プライベートの時間を過ごす。ときには友人と飲んだり踊ったりする。日本の教師も、アメリカやフランスみたいになれば、奴隷労働から解放されるのにと思うが、最近の文科大臣の答弁を聞くと、そんなことは夢物語だと分かる。
本作品を観る限りでは、ドイツの学校には職員室があるようだ。アメリカやフランス映画には職員室のようなものは登場しない。だから職員会議もない。教室に出勤して、そのまま授業を行なう。そして帰る。
ドイツの教師は日本の教師と同じように、長時間働いている。そして登場人物の台詞によると、ドイツでも教師が不足しているらしい。修学旅行もあるようだ。日本とドイツに共通しているのは、長い間の軍国主義の名残のような気がする。
本作品の教師は、労働環境の悪さに加えて、生徒の親からの圧力も相当だ。本来は親が責任を持つべき素行についても、教師の責任が問われる。成績が悪いのは教師の教え方が悪いせいだという意味の台詞もあった。自分の子供の能力を棚に上げて、教師の能力を問う保護者がいるという訳だ。人種差別や移民の生徒の問題もある。こんな状況では、教師のなり手が少なくて当然である。
そんな逆境の職業に飛び込んでいったカーラ・ノヴァクは、よほど子供が好きなのだろう。日本の教師たちも同じだと思う。重責を問われる長時間労働を好き好んでやる理由は、それ以外にない。それでも、教えるだけならともかく、管理の仕事も同時にしなければならないのは、精神的にきつい。
一般の会社では管理部門と営業部門で、別々の社員が仕事をしている。対立することはあるが、それでバランスが取れる。同じ社員にアクセルとブレーキを同時に踏ませるようなことは、なんの利益も生み出さない。それに社員を追い詰めてしまう。
カーラは生徒も守らなければならないし、自分も守らなければならない。親も説得しなければならないし、学校の立場も代弁しなければならない。それもこれも、教育行政が抱えている矛盾が噴出したものだ。つまりカーラは、ひとりの現場教師でありながら、教育の構造的な問題を背負わされているのである。自力で解決など、できるはずもない。
辛い映画ではあったが、序盤で出てくる算数の問題には驚いた。12歳の子供にはレベルが高すぎる気がしたのだ。正反対の解答を出した二人の生徒はいずれも優秀で、特に正解したオスカーが自分で解を導き出したのであれば、その頭のよさは群を抜いている。カーラが教師としてオスカーに将来性を感じたのは明らかだった。
教師が教育制度の矛盾を背負うのは、負担が大きすぎていつか潰れてしまう。カーラのような熱意のある教師は、共同体が守ってやらなければならない。教育を守るのは教師の心身の健康を守ることだ。それが生徒を守ることになり、ひいては共同体を守ることに通じる。
税金は困っている人のために使うのが筋で、その次は将来のために使う。困っている教育現場の予算を増やし、管理部門と教育部門を分けて予算管理すれば、教師の負担も減るだろう。将来の子供たちのための予算でもある。危機を煽って軍事力に税金を注ぎ込んでいる場合ではないのだ。
映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 後章」を観た。
前編で暴走したカドデがどのように収拾したのか、その訳が明らかになる。かなりSF寄りの設定だが、理解はできる。カドデとオンタンの人格が劇的に変化したのかと思っていたが、そうではなかったという話だ。考えてみれば、人間の世界観は変化していくが、人格はそう簡単には変わらない。
前編で登場しなかった人物が何人も登場するが、話はカドデとオンタンを中心に展開するから、散らかっている雰囲気はなく、人生の広がりを感じさせる。登場する政治家、活動家、部活の先輩、LGBT、それに元侵略者は、ふたりの世界観が広がっていくのを助ける役割を担っていると思う。
人類の暴力性を冷徹に描いている作品で、それはとりも直さず人類の愚かさの表現でもある。共同体を司る大人たちも、かつてカドデの読み順を替えていじめていた小学校や中学校のいじめっ子たちと同じレベルなのだ。文明は軍事技術を先頭に発達してきたが、人類の精神性は文明の発展に追いついていない。子供に銃や爆弾を持たせるようなものだ。自分だけよければ、いまだけよければ、それでいい。そういう指導者たちと、そんな連中に投票する有権者に対する痛烈な批判でもあると思う。
とても面白かった。
映画「関心領域」を観た。
「住めば都」という諺の通り、人は住み慣れた場所に愛着を覚えるようになる。それは場所だけではなく、仕事も同じで、慣れてしまうとその仕事が好きになる。脳は作業興奮を覚えるから、もっと仕事が上手くいくように工夫したり、新しい方法や設備を試したりする。
ナチ党政権を支えていたのは、勤勉な役人たちで、その真面目な仕事ぶりが、ユダヤ人の大量虐殺を生み出したと言われている。アウシュヴィッツの職員も、日本の入管の職員も、基本的に真面目で、自分の立場が悪くなることを最も恐れている。一方で、あわよくば昇進して、権限も給与も増えて、生活レベルが向上することを密かに夢見ている。
本作品の主人公のひとりルドルフ・ヘスは、ナチ党の役人の典型的な人物だ。効率的に仕事を進めるのが好きなようで、大量の死体を処理する性能のいい焼却炉に感心し、早速取り入れる。極めて事務的である。保身にも余念がなく、地域=ゲマインシャフトに受け入れられるように、環境を大切にするように指導したり、SS隊員が不適切なことをしないように警告する。「東方生存圏」というナチ党の理念を信じている。または信じているフリをしている。日本の「大東亜共栄圏」と同じ幻想だ。
もうひとりの主人公である妻は、夫の権力を笠に着て、おそらくユダヤ人と思われる家政婦たちを顎でこき使う。ときには八つ当たりの対象にもする。お前なんかルドルフに焼いてもらうぞと、脅しの言葉を吐く。心はいつも荒んでいる。
ここはいいところだ。住めば都である。自分で家や庭を整備した愛着もある。時折聞こえてくる、タン、タンというピストルの乾いた音にも、もう慣れた。春夏秋の草花を大事にして、色や香りを楽しむ。冬の寒さは、セントラルヒーティングが和らげてくれる。
ふたりとも、今日と同じ明日がずっと続くと信じて生きている。しかし不安がまったくないわけではない。リンゴの取り合いで川に沈められるのは、慣れたとはいえ、やはりおかしい。明日は我が身かもしれない。妻は毎日聞こえてくる悲鳴と銃声に、知らず知らずのうちに心を蝕まれている。夫は音楽家を招いた華美なパーティでも、効率的に殺す方法を考えずにいられない。
時折挟まれる黒い画面や白い画面、黄色い画面、それに重低音の不協和音は、ふたりが心の奥に押し隠している不安と恐怖だ。何百万人もの死が隣にあれば、どんな強心臓の持ち主でも、影響を受けてしまうだろう。
そして殺した者も殺された者も、歴史の彼方に埋ずもれてしまう。我々は歴史から何を学んだのか。そして何を学ばなかったのか。BGMの不協和音は、人類に対する警鐘のようにも聞こえた。
映画「ソイレント・グリーン デジタル・リマスター版」を観た。
ジョージ・オーウェルの小説「1984」と同じく、未来のディストピアを描いた作品である。登場する施設やデバイスや人物の衣装などは、いかにも50年前に想像した50年後で、これが精一杯だろうと窺える。ただ、暴動鎮圧のために警官が被るヘルメットは、どう見てもアメリカン・フットボールのヘルメットで、多分ジョークだろう。
テーマは、いまでも十分に通用する。文明が加速度的に発展し、生活が便利になった反面、大量消費、大量廃棄でゴミが大問題となり、エネルギーの消費と大量生産で産業廃棄物が公害を生む。核分裂発電所は、核のゴミを生み出し続け、処分場を地方に押し付けている。カネをやるからゴミを受け入れろというゴリ押しだ。そのカネはもとはといえば税金で、要するに国民のカネなのだが、ほとんどの政治家と役人は、自分のカネだと思っている。世界中同じだ。
強欲資本主義が、強欲な政治家と癒着したら、ろくでもない未来になるのは目に見えている。強欲の連中が食欲と性欲を独占する。50年前の価値観では、いい酒といい食物といい女が、いまも同じかもしれない。そのために人々からあらゆるものを搾取する。最後は人権どころか、人々の生命さえも蹂躙することになる。
そして生産性のない者や反体制的な人間は排除される。2022年の邦画「PLAN 75」で示された政策を、本作品はもっと過激にした形で表現している。暴動鎮圧は、重機を使って人間をゴミと同じようにかき集めて運んでいく。なんとも凄まじい。
どう考えても将来のない状況だが、強欲の連中は、いまだけ、自分だけよければいい訳だ。自民党とまったく同じである。チャールトン・ヘストンが人類に向かって危機を叫んでいるのに、誰も聞く耳を持たない。
交換所の冷めきった老人たちは、神を否定し、人間を否定する。ソル老人は、神はきっとhomeにいると言うが、homeがどんなところか、彼は百も承知だ。つまり神は死後の世界にいるということだ。言い方を変えれば、死ぬことだけが救いだという絶望である。それはある意味、人類の絶滅を予言していると思う。
映画「湖の女たち」を観た。
考える要素がありすぎて、なかなか整理のつかない作品である。大作と言っていい。最初は高齢者施設での出来事からはじまる。事故か事件かはまだ不明だが、高齢の老人が亡くなった。その老人には過去があり、夫人の記憶を遡ればハルビンの凍った川の思い出に至り、資料を遡れば日本軍の人体実験にまで及ぶ。
福地桃子の演じる池田記者は、もう少しで過去の事件と現在の事件のふたつの真相に辿り着けそうなのだが、権力者に阻まれ、刑事や親に阻まれる。刑事のひとりは、同じ過去の事件を追い、同じように阻まれた過去がある。警察の限界を感じ、刑事という仕事に誇りを持てなくなって、反動で警察の悪い部分を代表するようになってしまっている。
殺人事件と断定されたため、警察は帳場を立てなければならなくなる。そこで警察の悪い部分、つまり権力の濫用がはじまる。警察の威信をかけて、事件の早期解決を図るのだ。つまり誰かを犯人に仕立て上げる訳である。
警察に推定無罪の考え方はない。疑わしきは自白させて有罪にする。警察官に人権意識はない。権力意識だけだ。日本国憲法38条など読んだこともないのだろう。憲法の意義どころか、日本に憲法があることさえ、知らない警察官もいるだろう。警察は常に権力の側であり、庶民の味方であったことは一度もない。
松本まりかの介護士豊田佳代は、過去のトラウマから、マゾヒストになってしまった。強圧的に凌辱されることに快感を覚える。そういう相手は、直感的にわかる。危険だと知っているから近づいてはいけないと理解しているが、体は命令され、人格を蹂躙されることを求めている。
財前直見は辛い役だった。介護士という職業に対する不当な低評価は、過酷な労働に見合わない低賃金に象徴される。建設業の土方と同じで、一番きつい仕事が一番賃金が安いのだ。それでも患者や入居者から感謝されることに喜びを感じて、毎日の作業をこなしている。刑事から職業を貶められる謂れはない。
時代に押しつぶされるような女たちの不幸は、過去からの負の遺産を背負い、未来の不安と恐怖を抱えながら、これからも続いていく。物語は完結しないし、事件は解決しない。長すぎて対岸が見えない橋のように、未来が続くのかさえもわからない。
凄い作品だった。