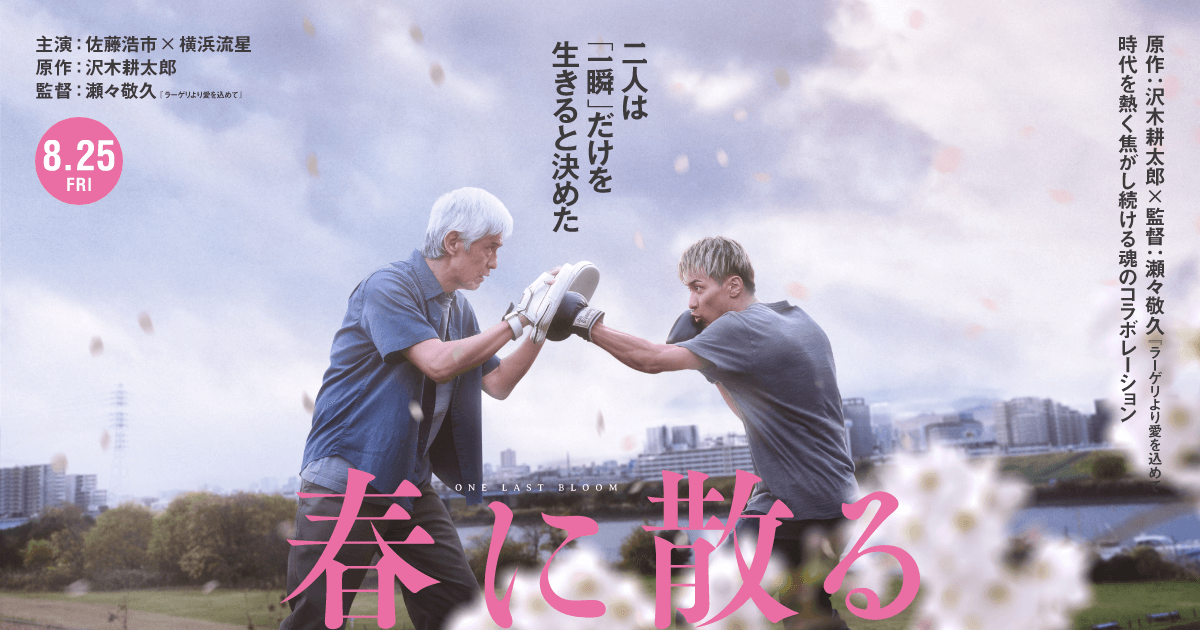映画「かかってこいよ世界」を観た。
チープな恋愛物語だが、そこかしこに社会の悪意が見え隠れする。特に差別主義が取り上げられていて、ヒロインの母親が差別主義者の典型だ。朝鮮人は日本人を憎んでいると、根拠のない発言で他民族を貶める。北朝鮮と韓国を合わせると人口は7700万人を超える。その全員が日本人を憎んでいるという明確な証拠はない。日本人はアメリカが好きだと言うのと同じだ。アメリカが好きな日本人もいれば嫌いな人もいる。決めつけるのは人格を軽んじている証拠であり、決めつけられた方は不愉快だ。
残念ながら本作品では、そういった人間の心理が深く掘り下げられていないから、ヒロインの気持ちにちっとも共感できない。恋愛と差別を絡める物語は割と多くて、大抵は困難を乗り越えて恋愛が成就するパターンだ。本作品の困難は微妙すぎて、困難とは呼びがたい。とってつけた感じだ。
母親との関係も結局はなあなあに終わる。差別主義者と対立するなら、その世界観を全否定するくらいで臨む必要がある。母親を人間のクズと罵るようなシーンや訣別するシーンが必要だったが、結局は融和してしまう。それも含めて全体的になあなあでリアリティに乏しい。たしかに現実の人間関係はなあなあかもしれないが、物語がなあなあだと魂のぶつかり合いを感じることができない。そのせいで作品が力強さに欠けている。
役者陣はそれなりだったが、ひとり菅田俊だけが渋い演技で存在感を示していた。この人がいたから、かろうじて映画が成立している。そんな気がした。ただ、孫の件で商取引を反故にするのは強引すぎて白けてしまった。新人監督のデビュー作なら、作品の出来は別にして、心に突き刺さる何かが欲しかった。いろいろな意味でもったいない作品だ。