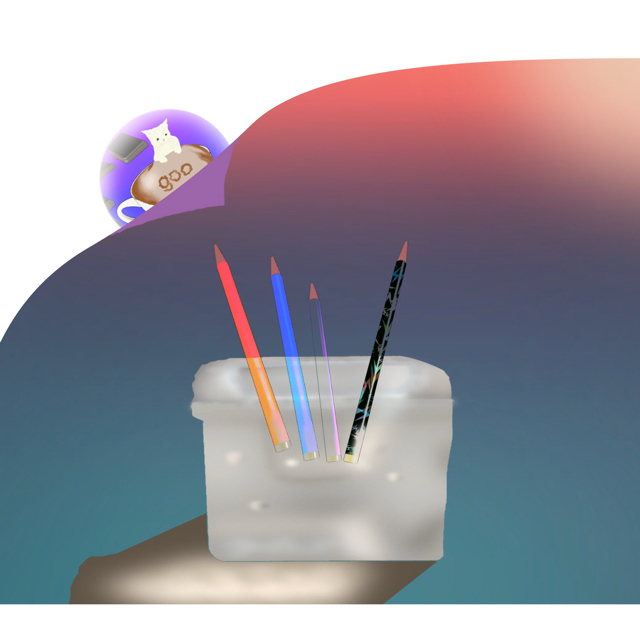「お前が先手だ」
僕は中飛車に振った。すると相手も中飛車に振ってきた。相振り飛車だ。僕が銀を上がると相手も銀を上がった。僕が玉を囲うと相手も玉を囲った。まるで鏡を見ているようで落ち着かない。僕は早く向き合うことから逃れたかった。僕は向かい飛車に振り直した。すると相手は角を換えて桂取りに自陣角を打ってきた。僕は歩を突いて受けた。相手は端歩を伸ばし桂をぴょんぴょん跳んできた。そして、いきなり端に成り捨てて攻めてきた。
強襲だ。
この時、僕の向かい飛車の飛車先はまだ飛車の頭で止まったままだった。(少し悠長に駒組みしすぎたのだ)相手は端を攻め立て飛車まで回ってきた。僕はしばらく受けにまわることになった。飛車のこびんに角を打ち込む形になって、急に棋勢が好転するのを感じた。僕は打ったばかりの角を切って飛車角両取りに金を打った。手順に飛車が端に戻り金が重たくなるのでそれは本筋ではなかった。角の頭に馬を作り厚くいくのが本筋だった。
端を攻めてくる手に対して、僕は左桂を中央に跳ね出した。狙いは中央だが、そこは相手の最も厚いところでもあった。端にと金を作られた手に対して、僕は玉を金と銀の間に移した。端を破られた場合の手筋だ。もしもと金を入ってくれば香で飛車が取れる。下段の香がいることで、たとえ取られても相手の攻めを遅らせることができるのだ。
相手は中段に桂を置いてきた。ぼんやりとして厳しいのかどうかわからなかった。僕は桂を不成で飛び込んだ。(もしも金を横にかわされていたらわからなかったが、とにかく速くなければと焦っていた)相手は素直に銀で桂を取った。僕は銀を金で取り返した。重たかった金が玉と一間のところまで迫ったので希望の持てる寄せ合いとなった。相手はさきほど打った桂の利きから歩を打ってきた。
王手だ!
「さあ、取るのか、逃げるのか」
と問いながら玉に迫ってきた。僕は一瞬迷った。逃げると王手飛車だけど、飛車の移動合で受けてどうなるか。だが、あっさり取る手も有力だ。
「わからないけど桂がほしい」
僕は攻め味を重視して銀で歩を払った。囲いが薄くなる。相手は玉頭の金に対しておかわりの桂を打ってきた。まだ詰めろではない。しかし、何かあれば詰む形になっているので不気味だ。僕は相手玉の両こびんを狙って中段に桂を打った。
「さあ、次は詰ますぞ!」
きっと相手は怖いはず。もしも持ち駒を使って受けてくれるなら、こちらの玉も今より安全になる。相手は玉頭の金を取った。僕の玉は三段目にまで上がり、側にいるのは銀1枚となった。相手は銀の隣にそっと金を置いた。(まさに置いたというような手だったのだ)王手でも詰めろでもない。だが、駒を渡すと詰むかもしれない。何もないと思っているところに読みにない手がきて、僕は慌ててしまう。もっと強い攻めならそれに合わせて受けることもできるが、ふわりとしている分どう受けていいかわからない。
しかし、桂が1枚増えたので詰みがあるはず。金を寄り桂を成り捨て桂を打つ。王手。相手は玉をまっすぐ上に逃げる。残り10秒。もしも、向かい飛車の飛車先が1つでも伸びていれば、簡単な詰みだった。僕は玉頭に銀を捨てた。正しくは端から桂を打つ手で、まさにもらった桂によってぴったり詰むのだが、発見できなかった。するすると上に逃げられ、王手が続かなくなったところで時間切れとなった。
~即詰みを逃す
・曲者は難しい
手数にしては10手ちょっとの簡単な詰将棋だ。しかし持ち駒が角とか桂とかばっかりだと、飛車と金の実戦型よりも大変だ。(桂の利きが人間には難しいのだ)あと下段に落とす方はわかりやすいが、上に追っての詰みとなるとそこも難しい。抜け出されるという怖さがあるし、落とすのと追うのとでは経験に差がある。
・プレッシャーがかかる
普通の詰将棋なら解けても、プレッシャーのかかった局面ではそれだけで難易度が上がってしまう。詰まさなければ自陣が詰む。あるいは詰まされるかもという不安。時間が切迫するというプレッシャー。そういう状況でも詰んでいるものを詰まし切るには、心も強くなければならない。
時間が切迫するというだけで、5手詰や7手詰が詰まなくなる。酷い時など、1手詰を見落としてしまうのだ。
・長い詰みより短い必至か?
長い詰みは時間がかかる。短い詰みよりはそうだろう。短い必至はどうだろう? そこは難しい問題だ。長い詰みなら読み抜けがあるかもしれない。詰みがなかった場合には負けになることが考えられる。だが、実戦で必至をかけることにも問題はある。本当に必至か?(必至にも読み抜けがある)詰めろ逃れの詰めろがあるかもしれない。受けの妙手があるかもしれない。王手で攻め駒を抜かれたり、上部を開拓されるかもしれない。(部分的に必至でも、実戦では王手でそれが解かれることもある)
あるいは、無駄な受けや王手ラッシュをされて時間切れに追い込まれるかもしれない。そうした面を考えると、多少長かろうが即詰みほど確実なものはないとも言える。(読み切ってしまえば)絶対手順に入ってしまえば、時間を使うこともなく、手番を渡さないので王手ラッシュもない。(王手ラッシュ問題の解決策は穴熊だ。それ以外では、その分だけ時間を余しておくことだ)
詰みはあるけど必至はないという局面も存在する。だから、このテーマに1つの正解はない。
~向かい飛車が泣いていた(相振り飛車は攻め合え)
即詰みを逃した。それが直接の敗因だ。しかし、直接の敗因だけをみて反省を終わらせていては、見込めない成長もある。詰む詰まないまで行っていることはよいことだ。では、それ以前はどうだったのか?
一番の問題は向かい飛車が最後まで遊んでいたことだ。詰むとか詰まない、時間があるとかないとかは、言ってみれば運だ。紙一重のところで決まる部分だ。ところが、飛車が遊んでいるというのはもっと将棋の根幹だ。そういう将棋を指していては、今日たまたま勝てたとしても明日は勝てなくなるだろう。相振り飛車の将棋では、気をつけないとこういうことがよくある。(対抗形では互いに戦場を共有していることが常なので、普通に指していればそこまで飛車が遊ぶということが少ない)相振り飛車では、相手の飛車の領域でのみ戦ってしまうと、自分の飛車が遊んだまま終わりかねない。少なくとも、反撃の構えだけは取っておかなければならない。
本局の問題点は端攻めの認識だ。
まず自陣角からの端攻めを過大評価しすぎないこと。そこだけに意識を向けすぎないことだ。端は破られても構わない。基本的に角まで加わってしまうと、美濃囲いの端は守りきれない。だが、端攻めをされた場合、必ず桂とか香とかの持ち駒が入る。それに加えて持ち角もあるので、反撃の駒としては揃っている。端攻めを甘受して反撃に転じることが、相振り飛車の基本となる。主軸として忘れてならないのが飛車で、そのためにも早い段階で飛車先は相手の玉頭に伸ばしておかなければならない。歩と桂を持っての玉頭攻め(こびん攻め)は案外強力で、端攻めよりもダイレクトに響くことが多い。(反撃は相手の玉の位置によって変わる)
一方的に攻められないこと(過剰に受けにまわらないこと)で、飛車を使うことを心がけたい。