7月20日午後2時から「鞍馬寺」で行われる「竹伐り会式」を参拝するため、ミモロは、お友達と鞍馬へと向かいました。


この日、「鞍馬寺」には、大勢の参拝者が訪れ、叡山電車も、ケーブルカーもいっぱい。
「鞍馬で、何か祭事が行われると、いつも電車いっぱいになっちゃうんだよ~」と、お友達に説明するミモロです。
12時半に出町駅で待ち合わせして、鞍馬寺の本堂の前に到着したのは、会が始まる直前。「よかった~間に合って~」とミモロ。「竹伐り会」に奉仕する方々が入場するところでした。

でも、境内には、すでに大勢の人がいて、ミモロはウロウロ。「どこから、見えるかな~」なかなか本堂が見えません。
 ミモロの目の前には、スマホやタブレットを高くかざす人たち。「カメラだと、シャッタースピード速いから、すぐ手を下げてくれるけど、スマホを遅いし、ビデオ撮影する人は、ずっと掲げたままで、よく見えないよ~」と。
ミモロの目の前には、スマホやタブレットを高くかざす人たち。「カメラだと、シャッタースピード速いから、すぐ手を下げてくれるけど、スマホを遅いし、ビデオ撮影する人は、ずっと掲げたままで、よく見えないよ~」と。 「あ、竹伐ってる~」でも、伐る人しか見えず、どのような状態なのか、よくわかりません。
「あ、竹伐ってる~」でも、伐る人しか見えず、どのような状態なのか、よくわかりません。ミモロは、大勢の人のいる正面を諦めて、本堂の横へ。
 こちらは、人がいなくて、
こちらは、人がいなくて、 見通しがききます。会全体は、よく見えませんが、竹をかざす人の姿は見えました。
見通しがききます。会全体は、よく見えませんが、竹をかざす人の姿は見えました。大蛇に見立てた太い竹を、刀で伐る「竹伐り会」の起源は、平安時代の宇多天皇の世にさかのぼります。
解説書によると・・・初夏のある日、鞍馬寺の中興の祖、峯延上人が、護摩の秘法を施している際に、大蛇が現れ、上人を飲み込もうとしたのだそう。そこで上人は、ヒミツの真言を唱え、一心に祈ったところ、たちまち霊験があらわれ、大蛇は死んでしまったとか。その後、もう1匹大蛇が現れ、こちらは、本尊などにお供えする水を絶やさないことを誓ったので、「閼伽井護法善神」として本堂の東に祀られたのだそう。
初めに退治された大蛇は、オス。あとの大蛇はメスだったので、会では、はじめに太い竹をオスの大蛇に見立て、5段に伐ります。また、メスの大蛇に見立てた細い竹は、本堂に飾られていて、それには根があるので、後に山に植え戻すのだそう。
この「竹伐り会式」は、竹を勢いよく伐ることで、邪気を祓う意味があります。
さて、舞楽の奉納に進みます。


胡蝶の姿の子供が、見事に舞楽を舞います。「ちらちらとしか見えないけど…」とミモロ。
さて、竹刈りの儀のクライマックスは、竹の産地の近江と丹波の二手に別れ、竹を伐る速さを競い、その年の豊作を占う行事です。


「なんか勇ましい音がするけど、よく見えないね~」とミモロ。
これで、会は納められます。

結局、「竹刈りの儀」は、あまりに人が多くて、ミモロは、よく見えなかったのでした。
会が納められたので、ミモロは、諦めて、本堂の西側に移動しました。
「あれ、さっき、竹を伐っていて人たちが並んでる~。なにしてるんだろ?」と、ミモロは、近づいてみていました。
 「あの子なんだろ?」と勇ましい姿の大惣法師仲間といわれる方々。「なんか弁慶みたい…」とミモロ。
「あの子なんだろ?」と勇ましい姿の大惣法師仲間といわれる方々。「なんか弁慶みたい…」とミモロ。 思わずミモロの姿に笑みがこぼれます。この方々は、竹伐りの儀で速く竹を伐ることができた勝者です。
思わずミモロの姿に笑みがこぼれます。この方々は、竹伐りの儀で速く竹を伐ることができた勝者です。その方々の手には、鋭い刀と伐った竹が…。
「道をあけてくださ~い」という声で、ミモロは、その場を離れ、脇に…。すると、会を行った皆さんが、戻ってきました。


「あ、あの方、もしかして導師さま・・・」
 ありがたいお姿を拝見し、思わず、手を合わせるミモロです。
ありがたいお姿を拝見し、思わず、手を合わせるミモロです。その後には、僧が続きます。

「竹刈り会の様子は、よくわからなかったけど、導師さまのお姿に出会えて、感激~」とミモロ。
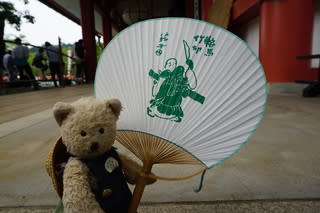
帰りは、ケーブルカーには、乗らず山道を下ります。

帰り道、境内にウロウロするミモロに、ちょっとでも見える場所を教えてくださったカメラ愛好家のおじさまに出会いました。「あのね~導師様に会えたの~」と感激するミモロ。「え~それはよかったですね~。めったにお姿見られませんから…。昔は、こんなに大勢の人が来なかったんですが、最近は、すごいですね~」と。
そう、最近、どこに行っても、大勢の観光客。見物も大変です。
この日、会が始まったとき、ご高齢の方が、突然、倒れられ、警備の人たちが救護活動を…。
熱中症でしょうか。夏の見物には、十分の備えと、注意が必要。会が終わるころには、その方は、回復なさっていました。
さて、「お腹空いた~」ということで、叡山電車に乗る前に、門前で大好きな甘キツネのおそばをいただきました。

「全くよく見えなくて、リポートできずにごめんなさい」と、申し訳なさそうなミモロです。どうぞ、お許しを…。

人気ブログランキング
ブログを見たら、金魚をクリックしてね ミモロより
ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら
ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro@piano.ocn.ne.jp まで
















