「ミモロちゃん、ケーキ食べに行かない?」と、ある日、お友達に誘われたミモロ。もちろん「行く、行く!で…どこ?」とお返事しました。
今回、向かうのは、叡山電鉄元田中駅から、徒歩3分。手づくり市で有名な「百万遍 知恩寺」からも歩いてゆける場所。
「あれ?御蔭通と東大路通の交差点の近所なんだ~」と。御蔭通は、下鴨神社の糺の森に入口に続く通りで、ミモロもよく歩く場所…。「へぇ~こんなところにケーキ屋さんがあるの?」と、ミモロは、お友達の後ろをトコトコついている来ます。
 「はい、ここよ~」とお友達。ミモロは、住宅地の中の趣ある町家の前に…
「はい、ここよ~」とお友達。ミモロは、住宅地の中の趣ある町家の前に…「え~ここが、ケーキ屋さんなの?」とミモロは、不思議そうに、赤い暖簾をくぐります。
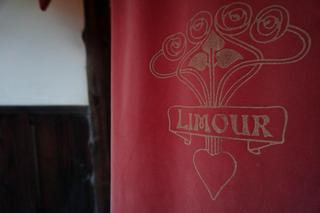
玄関のガラスケースの中には、ケーキが数種類並んでいます。また焼き菓子もいろいろ…


「中でお茶とケーキいただきましょ…」とお友達。さっそくミモロも靴(下駄)を脱いであがります。

「わ~中、広いんだ~」

和室のお座敷が続く店内…壁には、ティーセットなどが収まったアンティークなキャビネットも。


ミモロたちは、カウンター席に座ります。
さて、この「洋菓子工房リモール」は、十数年年ほど前に、オーナーパティシエールの森本さんがはじめたケーキ教室に由来します。かつてニットデザイナーだったという森本さん。ケーキ作りにはまり、製菓学校に通い、洋菓子教室などでアシスタントなどを経験後、自ら洋菓子教室をスタート。 またケーキなどの販売も行うようになります。
「いらっしゃる方から、ケーキがその場で食べられたらいいのに~」との声が高まり、このお店をオープンしたのは、2007年のことだとか。一度食べたら、また食べたくなる…そんなケーキ…。材料のひとつひとつにこだわり、丁寧に作られたお菓子には、作り手の愛情が詰まります。
ヨーロッパ伝統の焼き菓子などは、それを愛し続けた人々の思いが伝わるような飽きのこない味なのです。
「ホント、落ち着くお店だね~」とミモロ。「こんど百万遍の手づくり市に来たお友達も連れて来よう…」と。
お友達は、抹茶のセットを注文。目の前で、さっそくお茶を煎れてくださいます。

 「何杯でもおかわりしてくださいね~」とお店の方。「え~おかわりできるのって、珍しい…」「ミモロちゃんは、なんにするの?」
「何杯でもおかわりしてくださいね~」とお店の方。「え~おかわりできるのって、珍しい…」「ミモロちゃんは、なんにするの?」 人のことばかり見ていて、まだ決めていないミモロでした。「あの~ジンジャエールとケーキにする…」喉が渇いていたミモロは、手づくりのジンジャエール(500円)を注文します。
人のことばかり見ていて、まだ決めていないミモロでした。「あの~ジンジャエールとケーキにする…」喉が渇いていたミモロは、手づくりのジンジャエール(500円)を注文します。
ジンジャエールって、瓶入りのものしか以前は、知らなかったのですが、最近、手づくりのものが味わえるようになり、その美味しさにすっかり魅了されてしまっているミモロです。

「この生姜の苦味がたまらない…」と夢中。そして注文したのは、カトル・カール(250円)という焼き菓子です。

「ちょっと甘酸っぱい…レモンのお味がきいてるケーキ…う~美味しい…」とペロリ。
知る人ぞ知る、「隠れ家的ケーキサロン」です。飲み物も紅茶、日本茶、中国茶、コーヒーやジンジャエールなども揃っています。
「ミモロちゃん、そのフィナンシェも美味しいのよ~」とお友達に勧められたミモロ。「じゃ、おやつに…」

京都に暮らし始めて、お友達などに連れていってもらうお店で、京都のイメージが変わりつつあるミモロです。
「京都って、和菓子と日本料理…のイメージだけど、もちろんそれも美味しいけど、中華料理やケーキ、パンも美味しんだよね」
ガイドブックにあんまり載ってない…だけど、地元の人に愛されているお店…それが美味しいと思うミモロです。
「また、自転車で来ま~す」とミモロ。
お友達ともいっしょに…ぜひ…
*「京の洋菓子工房 リモール」京都市左京区中里ノ前町49-3 075-781-9848 13:00~19:00(サロンは、LO18:30) 水・木曜休み。1月休み

人気ブログランキングへ
ブログを見たら、金魚をクリックしてね~ミモロより
















 「これ、去年作ったヒツジさん…」
「これ、去年作ったヒツジさん…」 ミモロが到着した時は、すでに町内の方々が、製作に励んでいます。
ミモロが到着した時は、すでに町内の方々が、製作に励んでいます。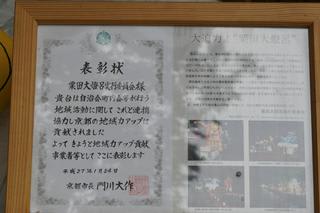

 すでに京都造形芸術大学の学生さんが作ったサルをモデルに、学生さんたちの指導の元、地域の人たちが製作してゆきます。
すでに京都造形芸術大学の学生さんが作ったサルをモデルに、学生さんたちの指導の元、地域の人たちが製作してゆきます。 「こんな感じでいいですか?」「上手にできましたね~その調子で他もやってくださいね~」
「こんな感じでいいですか?」「上手にできましたね~その調子で他もやってくださいね~」

 「きゃ~冷たくて気持ちいい~」
「きゃ~冷たくて気持ちいい~」








 「これに火をつけて投げるんだよ~」
「これに火をつけて投げるんだよ~」 消防車の待機も万全
消防車の待機も万全
 地松の点火がスタート
地松の点火がスタート
 運動会の玉入れのように、次々投げられる放火松…入りそうになるたびに、見物人から歓声がわき起こります。
運動会の玉入れのように、次々投げられる放火松…入りそうになるたびに、見物人から歓声がわき起こります。 「よく燃えるね~」
「よく燃えるね~」


 鮎で知られる江戸時代からつづく老舗の「鮎茶屋 平野屋」で、ゆっくりお食事。陽も落ちて、あたりが暗くなり始めたころ、愛宕神社の一の鳥居から二尊院、清凉寺までの街道沿いに灯りがともりはじめます。
鮎で知られる江戸時代からつづく老舗の「鮎茶屋 平野屋」で、ゆっくりお食事。陽も落ちて、あたりが暗くなり始めたころ、愛宕神社の一の鳥居から二尊院、清凉寺までの街道沿いに灯りがともりはじめます。

 ミモロもちょっと提灯を持たせてもらいました。
ミモロもちょっと提灯を持たせてもらいました。





 と手を合わせるミモロです。
と手を合わせるミモロです。





 「あ、お魚~」
「あ、お魚~」
 ねじった形は、愛宕山の山道を表しているそう。昔から、愛宕神社への参拝者に愛され続けている味です。
ねじった形は、愛宕山の山道を表しているそう。昔から、愛宕神社への参拝者に愛され続けている味です。







 「こんなの初めて食べた~」ともちろん、あっという間に完食。
「こんなの初めて食べた~」ともちろん、あっという間に完食。 丸ごと、ガブリといただきます。
丸ごと、ガブリといただきます。
 赤い前垂れが女将の印。「いかがでした?」「はい、すごく鮎美味しかったし、ここの雰囲気が本当に素敵…なんか、お泊りしたくなっちゃいます」と、お腹がいっぱいのミモロは、眠くなってしまったよう。
赤い前垂れが女将の印。「いかがでした?」「はい、すごく鮎美味しかったし、ここの雰囲気が本当に素敵…なんか、お泊りしたくなっちゃいます」と、お腹がいっぱいのミモロは、眠くなってしまったよう。 実は、この日、嵯峨野を訪れたのは、「あだしの念仏寺」での「千灯供養」のため…「これ、持って行ってください…」と女将がミモロたちに、「平野屋」特製の提灯に火を入れてくれました。
実は、この日、嵯峨野を訪れたのは、「あだしの念仏寺」での「千灯供養」のため…「これ、持って行ってください…」と女将がミモロたちに、「平野屋」特製の提灯に火を入れてくれました。





