先週放送されたNHKのバラエティー番組「日本人のおなまえっ!」では、フィギュアスケートの羽生結弦(はにゅうゆずる)と将棋の羽生善治(はぶよしはる)の二人の姓「羽生」について追究していた。ルーツの異なる二人の姓に使われている「羽」の文字がいずれも、もともと「埴」であったという興味深い事実が明らかにされた。
実は5年ほど前、僕はこの「埴」について調べていた。その時、このブログにアップした記事を再掲してみたい。
玉名は母と妻の生まれた地でもあり、僕にとっても10年ほどを過ごしたほとんど故郷と言っていい。その玉名に関してずっと前から気になっていたことがある。それは「繁根木(はねぎ)」という地名の由来だ。繁根木は昔は繁根木村といって、今の玉名市のほぼ中央部、現在、市役所も置かれているところである。繁根木と名のつくものでよく知られているのは、繁根木八幡宮、繁根木川、繁根木古墳などがある。昨年、玉名市の歴史博物館「こころピア」にも聞いてみたのだがよくわからないという。そんならというわけで自分で古文書などを調べ始めた。
最初の手がかりとしたのは同じ地名が他にあるのかどうか。まず、東京都世田谷区に羽根木という地区があることがわかった。羽根木神社という神社もあるという。その地区では「羽根木」という名前の由来は次のように伝えられているそうだ。羽根木の「羽根」は埴(ハニ)が訛ったもの。埴輪(はにわ)の「埴」。埴とは質の緻密な黄赤の粘土のことを言い、昔はこれで瓦・陶器をつくり、また衣に摺り付けて模様をあらわしたという。そして「羽根木」は「埴黄(ハニギ)」から変化したものと言われているそうだ。「繁根木」と「羽根木」はおそらくもとを辿れば同じ語源だろうと睨んだ。案の定、「肥後國誌」の中には玉名の「繁根木」を「羽根木」と表記したものも散見される。
その後、まさに灯台下暗しで、熊本でも近い所に同名の「羽根木」という地区があることに気付いた。なんと菊池市七城町にあった。しかも僕は一昨年そこに行っていたのだ。そこは西郷隆盛の祖先の発祥の地として知られる旧西郷村、その西郷のすぐ隣りだったのである。ここでは「羽根木」の由来について、「刎木説」(下記参照)と世田谷と同じ「埴黄説」の二つがあり、結論は出ていないという。
さらにもう一つ、古文書の中に気になる言葉を発見した。それは「埴木(ハニキ)」。これは櫨(ハゼノキ)のことで、江戸中期に熊本藩主細川公が殖産のため菊池川の堤防沿いなどに盛んに櫨を植樹する以前から、九州各地には原生の櫨が多く、「埴木(ハニキ)」とも呼ばれていたという。
そこで各説をあらためて整理してみると
1.刎木(ハネキ)説…川などの水量調節をする木製の治水の仕掛けのこと。
2.埴黄(ハニギ)説…質の緻密な黄赤の粘土のこと。
3.埴木(ハニキ)説…黄色の木、すなわち櫨(ハゼノキ)のこと。

繁根木川(はねぎがわ)
繁根木川の河口に近い高瀬の辺りは西南戦争時、乃木希典隊と桐野利秋隊が川をはさんで激突した激戦地。この戦いで西郷隆盛の末弟・小兵衛が戦死した。

























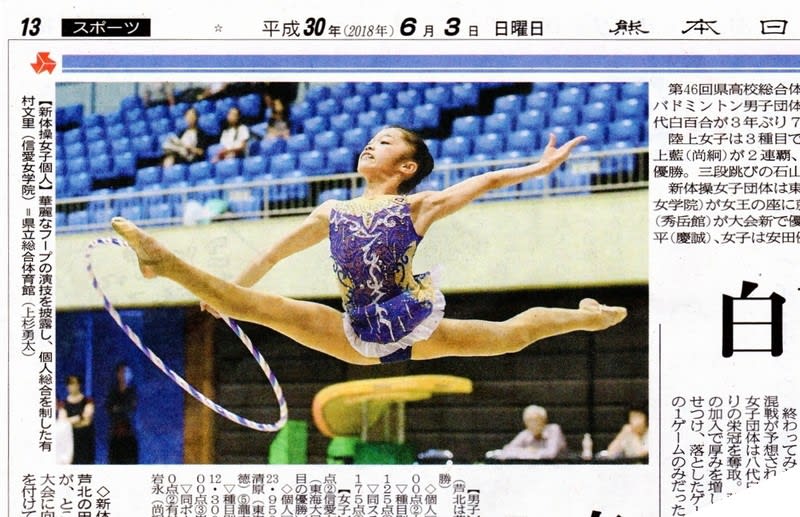
 ▼気軽に集えるカフェに 美濃加茂・旧伊深村役場改装(中日新聞プラス)
▼気軽に集えるカフェに 美濃加茂・旧伊深村役場改装(中日新聞プラス)

