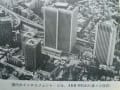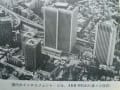
先端技術のゆくえ, 坂本賢三, 岩波新書 (黄版)362, 1987年
・哲学の視点から見た『技術』のこれまでの歴史の流れと、今後の展望について。世を支配するものは、『宗教』→『国家』→『経済』→(今ここ)→『技術』という流れであるという主旨。20年前の本だが古さは感じない。文系・理系問わずに読める、内容のしっかりした良い本だと思うのですが、これまた絶版。地味な書題のため多少損をしているかも。
・写真:『六本木ヒルズ』の前に『アークヒルズ』なんてものを造ってたんだ…と調べて見ると写真中央下の低い建物がサントリーホール(出来たて)なのですね。ほええ。まるで異国の都会の写真を眺めるような。なんにも知らない田舎者まるだし。
・「単に時間的に最前線にあるというだけでなく、従来の技術と質的に異なっているという意味合いを込めるために「高度技術」と呼んでみたのである。(中略)それでは高度技術はどのような点で従来の技術と区別されるのか。これには種々の見方があると思われるが、その根本的な特徴を次の三つの点に見たい。 第一は、それが「科学の応用」や「科学・技術」でなく、科学と技術が一体になった「科学技術」であるということである。第二は、それが情報加工と情報伝達を根底に持っていること、第三は、「技術の技術」がすべての技術の根底に置かれていることである。」p.11
・「だから、科学と技術は対象と主体との関係においてベクトルの向きが違うのである。出発点も目的も逆、前提も帰結も逆である。科学の目指しているのは認識であり、技術の目指しているのは制作である。」p.12
・「日本語の場合、技術・科学技術・工学・科学の概念の境界があいまいなのは、工部大学校以来、科学を基礎として近代技術をつくってきたからであって、明治19年に工部大学校が帝国大学工科大学になっていっそうこの特質が顕著になった。大学に工学部を設置したのは日本が世界で最初なのである。」p.22
・「科学と技術が一体となった「科学技術」にあたる外国語は久しく存在しなかった。「科学技術」の概念形成は日本の方が早かったと思われるのである。しかし、20世紀後半以後は、日本語の「科学技術」にあたる英語として「テクノロジー」という語が定着した。」p.23
・「高度技術の時代の中心をなすものとして「情報」を取り上げる場合には、もっと限定して用いなければならない。在来の用語で表現できるものであれば、知識とかニュースとか、はっきり言ったほうがよいのであって、「情報」という言葉は、情報としか表現できないものに限定すべきであろう。」p.26
・「技術の歴史を一言で言うとすれば、それは人間能力の対象化と外的自然の主体化の歴史である。(中略)乗物のことを「足」と呼び、望遠鏡のことを「目」といい、道具のことを「手」と呼ぶのはこの事情を反映しているのである。」p.28
・「つまり、材料を加工して利用しやすいものにする技術から「物質」の概念が成立し、動力を加工して利用しやすいものにする技術から「エネルギー」の概念が成立したのである。」p.33
・「制御と通信だけでなく、計算や分類などの処理も含んで「情報」の概念が成立したのは、やはり電子計算機の開発によってであった。」p.37
・「しかし、エネルギー生産の発達普及が人間の体力を弱化する傾向を強めたように、情報生産の発展が人間の計算能力や記憶力や情報処理能力を弱める傾向は避けられないと思われる。それらの能力をむしろ機械に任せることによって、機械にはできない人間能力の発展が期待されるのであって、それはプログラム作成やシステム設計よりはむしろ「意味」の発見に向けれらるべきではあるまいかと思われる。」p.39
・「この意味では遺伝子操作も情報加工にほかならない。つまり情報技術は単にコンピュータやニューメディアだけでなく、生命にまで及んでいるのである。」p.44
・「私はこの問題を端的に「何のための技術か」という問いとして扱ってみたいと思う。現代の先端技術はいつでもこの問題を抱えていながら、実はこのように問題を提出したことはないのである。」p.79
・「彼らは、もっぱら教会の仕事に従事するのではなく、軍事的に人を驚かす技術の開発に専念したので、アイデア・マン(ラテン語でインゲニアトール)と呼ばれるようになり、これが英語のエンジニアになったのである。」p.82
・「粒子的要素の力学を基礎とする現代物理学から見ると、ニュートンから始まり、質点の力学、質点系の力学と展開して行った流れしか見えないが、他方にデカルトの連続体説を出発点とする水力学・流体力学の伝統が脈々とあって、実験や土木工事の実際と結びつき、科学研究の重要な一面をなしていたのである。」p.89
・「「日本の技術者には独創性が欠けている」とよく言われるが、私は、これは当っていないと思う。一つには、独創性はあるかないかではなくて、独創性の芽を摘むか摘まないかなのであって、明治以来、採算の面から芽が摘まれることが多く、育てられることが少なかったと言った方がよいであろう。」p.156
・「利潤の獲得を第一の目標にするのであれば、これほど急速な技術水準の向上よりも低賃金で廉価品を作っていればよかったのであるが、官も民間企業もあげて技術の高度化に努力してきたことは、私利よりも国益を優先してきた明治以来の日本の会社の特質からくるものと思われてならない。」p.157
・「こうしてみると、「経済の時代」のあとにくるのは「技術の時代」ではないかと思わせる。(中略)「高度技術時代」は、単に先端技術の延長というだけでなく、経済も政治も技術に奉仕するようになる時代という特質を持つのではあるまいか。」p.164
・「第一に、その転換期におとずれるものは「経済革命」ということになろう。宗教の時代の末期には宗教改革があり、政治の時代(国家の時代)の末期には政治革命があった。(中略)第二に、この時代の担い手は言うまでもなく技術者、もっと厳密にいえば「科学技術者」である。宗教の時代の聖職者・僧侶、国家の時代の王と官僚、経済の時代の企業者にあたるものは、技術の時代には科学技術者であって、じじつ、20世紀後半の科学技術者は聖職者や官僚や企業家に近い存在になりつつある。」p.166
・「しかし、技術の時代には崇拝の対象となるのは記号である。神も記号、価値も記号である。技術の時代は記号が横行する社会である。」p.168
・「本当は「技術の時代」ではなく「人間の時代」が来てほしいと願っているのである。しかし、今のまま進めば技術が人間に奉仕するのではなく人間が技術に奉仕する「技術の時代」になるような気がしてならない。」p.188
・「技術を自己目的化するのでなく、何のために使うべきかを示す哲学、あらためて技術の存在理由を示し、技術のあるべき姿を人々に示し、技術者が耳を傾けるだけでなく、それを実現しようとするような哲学が必要だと思われるのである。」p.191
・「技術を、宗教や政治や経済のためではなく、言い古された言葉ではあるが、民衆のため、人びとの福祉のためのものにすることが何よりも重要なのであって、技術と経済とが分離してきた現在、技術を誰のものにするかが今後の課題なのである。それを究極的に決定するのは民の声である。」p.193