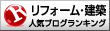googleのmapで道を調べていたら橋の名前が分からない。
国土地理院の地図を見ても小さな橋は名前が分からない。
渡良瀬橋とか思案橋など、歌になっている橋の名もある。
なんだか地図を見ても情緒がない。
さらには市町村合併で情緒もへったくれもないような名前の市町とかは、情けないこと限りなしだと思ったりする。
で、京都の川に架かる橋を調べようと近くの音羽川、松ケ崎疎水を訪ねて、家に帰ってネットを見ると、同じように調べている人がいた。
「東京の橋クラブ」でサイトはこちら
そこに自分が調べた京都の音羽川の情報があった。
ありゃま、京都の河川も調べているみたい。
音羽川、松ケ崎疎水は後日記載のこととして、本日堀川に自転車で散策してきたのでちょいと紹介します。
堀川北大路からスタート。

北大路通りから堀川通りの西側を下がった所に紫式部と小野篁の墓があった。

奥に進むと左側に紫式部の墓。

右側に小野篁の墓がある。

杖をもったお地蔵さんもおられた。

紫明通の交差点を過ぎると、瑞光院 赤穂義士遺髪塔跡碑がある。
京都市の資料には以下のように書いてある。
瑞光院は,慶長16年(1611)に歿した浅野長政の別荘を,山崎家盛が寺院としたもの。
臨済宗大徳寺派。後に赤穂城主・浅野長矩(内匠頭)が夫人の縁故で壇家となった。
長矩の切腹後にはその供養塔をつくり,元禄15年(1702)の浪士討入の後も、大石良雄をはじめとする四十六士の遺髪を埋葬した塔をもうけて供養した。
昭和37年(1962)に山科区安朱へ移転。遺髪塔も遷された。
この石標は,赤穂浪士の遺髪塔があった瑞光院の跡を示すものである。

紫明通の交差点を渡り東側を下ると後花園天皇火葬塚がある。

水火天満宮さんにお参り。

出世石。
大願成就、世に出る石として信仰されています。


出世石の左側に登天石がある。
水火天満宮さんのHPには以下のように書かれている。
菅原道真公が大宰府の地に於いて亡くなられて後、都では天変が相次ぎ、雷火の災いが重なったことから、菅公の怨霊の祟りと不安が高まりました。
時の帝、醍醐天皇は、延暦寺の法性坊尊意僧正に祈祷を依頼します。
勅命を受けた尊意が、急ぎ山を下りて宮中へ向かう途中、鴨川が突如増水し町へと流れ込みました。
しかし尊意は騒がずに、手にした数珠をひともみして、天に向かい神剣をかざして祈りを捧げたところ、不思議な事にたちまち水位が下り、水面が真っ二つ分かれ、水流の間から一つの石が現れました。
その上に菅公の神霊が現れ、やがて昇天し雲の中へ消えて、雷雨も止んだ。ということです。
その石を持ち帰り供養して、登天石と名付けました。
まあ、不思議な石である。
隕石との噂もあるが定かでない。

本殿。
ご祭神はもちろん菅原道真公。

こちらは金龍水。
都名水のの一つ。

六玉稲荷大明神社。

寺之内通を東に進み小川通りとの辻に百々石がある。
この石は、応仁の乱(一四六七~一四七七)の戦場として歴史に名をとどめる「百々橋」の疎石の一つ。
今は姿形もない小川に架かっていた橋。

堀川今出川の南あたりから堀川の水の姿が見える。

元誓願寺橋。

元誓願寺橋を過ぎると西側に晴明神社が見える。
土曜日とあって参拝者で混雑している。
人気があるんですね。

一条戻り橋。
ウィキペデアより↓
「戻橋」という名前の由来については『撰集抄』巻七で、延喜18年(918年)12月に漢学者三善清行の葬列がこの橋を通った際、父の死を聞いて急ぎ帰ってきた熊野で修行中の子浄蔵が棺にすがって祈ると、清行が雷鳴とともに一時生き返り、父子が抱き合ったという。

中立売通りに架かる堀川第一橋。


京都市電堀川(北野)線の橋の跡が堀川第一橋の南側にある。
北野天満宮と京都駅を結ぶこの路線は存続させてほしかったかも。

上長者橋。

上長者橋から北方面をみたところ。

下長者橋。

出水橋。

下立売通りに架かる堀川第二橋。

堀川第二橋も中立売通りに架かる堀川第一橋のようにアーチ状の旧橋が下側に見えた。

椹木橋(さわらぎばし)。

丸太町橋。

竹屋町橋。

夷川橋。

二条橋。

押小路橋。

押小路橋の手前から川の水は暗渠に入る。
堀川は整備された川ですけど、川沿いには歴史的なものが色々とあり楽しめました。
国土地理院の地図を見ても小さな橋は名前が分からない。
渡良瀬橋とか思案橋など、歌になっている橋の名もある。
なんだか地図を見ても情緒がない。
さらには市町村合併で情緒もへったくれもないような名前の市町とかは、情けないこと限りなしだと思ったりする。
で、京都の川に架かる橋を調べようと近くの音羽川、松ケ崎疎水を訪ねて、家に帰ってネットを見ると、同じように調べている人がいた。
「東京の橋クラブ」でサイトはこちら
そこに自分が調べた京都の音羽川の情報があった。
ありゃま、京都の河川も調べているみたい。
音羽川、松ケ崎疎水は後日記載のこととして、本日堀川に自転車で散策してきたのでちょいと紹介します。
堀川北大路からスタート。

北大路通りから堀川通りの西側を下がった所に紫式部と小野篁の墓があった。

奥に進むと左側に紫式部の墓。

右側に小野篁の墓がある。

杖をもったお地蔵さんもおられた。

紫明通の交差点を過ぎると、瑞光院 赤穂義士遺髪塔跡碑がある。
京都市の資料には以下のように書いてある。
瑞光院は,慶長16年(1611)に歿した浅野長政の別荘を,山崎家盛が寺院としたもの。
臨済宗大徳寺派。後に赤穂城主・浅野長矩(内匠頭)が夫人の縁故で壇家となった。
長矩の切腹後にはその供養塔をつくり,元禄15年(1702)の浪士討入の後も、大石良雄をはじめとする四十六士の遺髪を埋葬した塔をもうけて供養した。
昭和37年(1962)に山科区安朱へ移転。遺髪塔も遷された。
この石標は,赤穂浪士の遺髪塔があった瑞光院の跡を示すものである。

紫明通の交差点を渡り東側を下ると後花園天皇火葬塚がある。

水火天満宮さんにお参り。

出世石。
大願成就、世に出る石として信仰されています。


出世石の左側に登天石がある。
水火天満宮さんのHPには以下のように書かれている。
菅原道真公が大宰府の地に於いて亡くなられて後、都では天変が相次ぎ、雷火の災いが重なったことから、菅公の怨霊の祟りと不安が高まりました。
時の帝、醍醐天皇は、延暦寺の法性坊尊意僧正に祈祷を依頼します。
勅命を受けた尊意が、急ぎ山を下りて宮中へ向かう途中、鴨川が突如増水し町へと流れ込みました。
しかし尊意は騒がずに、手にした数珠をひともみして、天に向かい神剣をかざして祈りを捧げたところ、不思議な事にたちまち水位が下り、水面が真っ二つ分かれ、水流の間から一つの石が現れました。
その上に菅公の神霊が現れ、やがて昇天し雲の中へ消えて、雷雨も止んだ。ということです。
その石を持ち帰り供養して、登天石と名付けました。
まあ、不思議な石である。
隕石との噂もあるが定かでない。

本殿。
ご祭神はもちろん菅原道真公。

こちらは金龍水。
都名水のの一つ。

六玉稲荷大明神社。

寺之内通を東に進み小川通りとの辻に百々石がある。
この石は、応仁の乱(一四六七~一四七七)の戦場として歴史に名をとどめる「百々橋」の疎石の一つ。
今は姿形もない小川に架かっていた橋。

堀川今出川の南あたりから堀川の水の姿が見える。

元誓願寺橋。

元誓願寺橋を過ぎると西側に晴明神社が見える。
土曜日とあって参拝者で混雑している。
人気があるんですね。

一条戻り橋。
ウィキペデアより↓
「戻橋」という名前の由来については『撰集抄』巻七で、延喜18年(918年)12月に漢学者三善清行の葬列がこの橋を通った際、父の死を聞いて急ぎ帰ってきた熊野で修行中の子浄蔵が棺にすがって祈ると、清行が雷鳴とともに一時生き返り、父子が抱き合ったという。

中立売通りに架かる堀川第一橋。


京都市電堀川(北野)線の橋の跡が堀川第一橋の南側にある。
北野天満宮と京都駅を結ぶこの路線は存続させてほしかったかも。

上長者橋。

上長者橋から北方面をみたところ。

下長者橋。

出水橋。

下立売通りに架かる堀川第二橋。

堀川第二橋も中立売通りに架かる堀川第一橋のようにアーチ状の旧橋が下側に見えた。

椹木橋(さわらぎばし)。

丸太町橋。

竹屋町橋。

夷川橋。

二条橋。

押小路橋。

押小路橋の手前から川の水は暗渠に入る。
堀川は整備された川ですけど、川沿いには歴史的なものが色々とあり楽しめました。