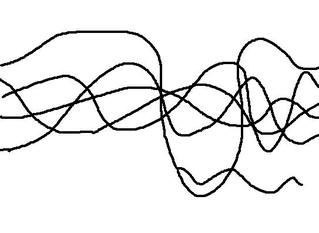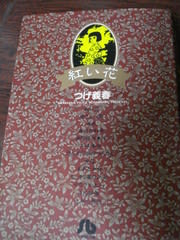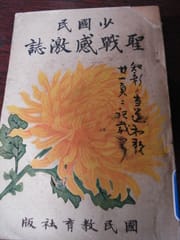http://mainichi.jp/feature/kaasan/
↑
「毎日かあさん」の最近まれに見る傑作
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20120719/234639/
↑
小田嶋隆氏の最近好調のコラム。先週の文楽についてもよかった。氏のコラムは、氏自身が興味があるのかないのか良く分からん話題の時が一番面白い。つまり、この態度はこれからの市民の理想型ではなかろうか、ある意味でぇ~。興味ないことで一番公共性を発揮できるのはすごいよ。
http://www.nicovideo.jp/watch/nm4965434
↑
クラシックオタクは、大作曲家の大交響曲のあら探しをして「第6より第5だ」「あのオーケストレーションはいまいち」とか言いだすのであるが、大作曲家は短い合唱曲でも全然格が違うことが分かる曲。私の葬式で、私の指導学生はこれを合唱すべし。
↑
「毎日かあさん」の最近まれに見る傑作
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20120719/234639/
↑
小田嶋隆氏の最近好調のコラム。先週の文楽についてもよかった。氏のコラムは、氏自身が興味があるのかないのか良く分からん話題の時が一番面白い。つまり、この態度はこれからの市民の理想型ではなかろうか、ある意味でぇ~。興味ないことで一番公共性を発揮できるのはすごいよ。
http://www.nicovideo.jp/watch/nm4965434
↑
クラシックオタクは、大作曲家の大交響曲のあら探しをして「第6より第5だ」「あのオーケストレーションはいまいち」とか言いだすのであるが、大作曲家は短い合唱曲でも全然格が違うことが分かる曲。私の葬式で、私の指導学生はこれを合唱すべし。