
佐久長聖(長野) 5 - 9 作新学院(栃木)
浦添商(沖縄) 6 - 4 愛工大名電(愛知)
桐光学園(神奈川) 7 - 5 常総学院(茨城)
鳥取城北(鳥取) 3 - 1 香川西(香川)
龍谷大平安(京都) 2 - 4 東海大甲府(山梨)←今日ここ
ちっまだ残ってたか。がんばれ山梨ー。
おまけ……木曽青峰(長野)1-6 上伊那農(長野)←地区予選一回戦
浦添商(沖縄) 6 - 4 愛工大名電(愛知)
桐光学園(神奈川) 7 - 5 常総学院(茨城)
鳥取城北(鳥取) 3 - 1 香川西(香川)
龍谷大平安(京都) 2 - 4 東海大甲府(山梨)←今日ここ
ちっまだ残ってたか。がんばれ山梨ー。
おまけ……木曽青峰(長野)1-6 上伊那農(長野)←地区予選一回戦
……昨日は、つい丸山眞男について考えていたら、通俗マルクス主義者になりかけた。思うに、戦後の左翼がやたら実践にとりつかれていたのは、丸山みたいな人がいたからではないか。準備は整ったあとはヤルだけ、という安心感を丸山の文章は醸し出している。そして丸山は決して何もせずベートーベンを聞いてそうなので頭に来る、で街に飛び出したりバリケードをつくってしまう訳である。実践の引き金になっているのは何か?その怒りではない。丸山の方だと思う。
やたら実践研究と称している研究をよんでもまったく実践する気にならんのは、こういうメカニズムに因るのではなかろうか。
やたら実践研究と称している研究をよんでもまったく実践する気にならんのは、こういうメカニズムに因るのではなかろうか。

確かに、丸山眞男は「闇斎学と闇斎学派」を、あるいは学生運動におけるセクトの体たらくを横目に見ながら書いたのかもしれない。そこには、海外から来た「全体的世界観」に身を賭ける人達はいかに生きるか、という問いがあった。しかしいまや、問題はそこじゃねえ……と思われるのは、まずはその前提として、賭ける人びとはいまだにいるかもしれないが、その人達が分派と闘争を繰り広げるほど、そもそもまともなセクトが出来ねえじゃねえか、という感じがするからである。確か鎌田哲哉氏がこの丸山の文章をだしにして、NAMの柄谷天皇を批判していたことがあった(『新現実』に載った論文)。たしかに、あの頃、わたくしも、NAMの決起集会などを見物にしにいったあと、つくばで「柄谷大明神の行く末」について語ったりしたものであった。鎌田氏はちょっと真剣すぎるんじゃないかという感じが当時していた、私には鎌田氏が「もっと超越性に賭けよ」というタイプに見えていたからである。それはまちがっていた。鎌田氏は議論をすることに賭ける人であった。そんな姿が私に見えなかったのは、それはそれでなんとなく空気に抗っていない道のような気がしていたからであろう。議論は集団を解体する方向で働くといういやな感じが当時の私を支配していた。
最近、勉強の妨害にばかりあっているためにそんなことを思うのかもしれない。まずは勉強する場所を守らなければならない。そのためには、議論を拒否することも場合によっては必要なのである。
上の画像は、『丸山眞男集 第十一巻』だが、巻末には「「君たちはどう生きるか」をめぐる問題──吉野さんの霊にささげる──」が載っている。懐かしい文章である。わたしはこれを小学校六年のときに読まされている。吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』中の「雪の日の出来事」を脚本化して主人公のコペル君も主演したもんでね……(笑)。吉野の著作は、左翼の転向と文芸復興のちょっとあと(ある種、絶妙な時期である)──昭和12年に書かれたものであるが、丸山の文章は、書かれたてほやほやの文章であって、私はその文章の「そうです、私達が「不覚」をとらないためにも……。」という末尾に、激しい抵抗の精神を感じない訳にはいかなかった。コペル君は、豆腐屋の浦川君とは違って、早慶戦実況の真似をして喜んだり、おじさんから生産関係のことを教わったりする、ブルジョアでインテリの卵である。子供心に思ったのは、コペルニクス的転向こそが目標だ、しかし卑怯な人間にはならないという倫理はその転向から来るものであろうか、ということであった。コペル君あるいはおじさんの「社会科学的」見方は、どちらかというと作中の一場面の如く、銀座の屋上から群集を眺める式のもので、本当に「雪の日の出来事」の倫理的なものを回収できるのであろうか、という疑問である。本当は、「雪の日の出来事」からの感情的回復(同時代的にはこっちの方が「転向」現象である)があるからこそ、社会科学的認識に落ち着くのではないか。マルクス主義者じみた言い方になるが、そこに実践のモメントはあるのか否か。実践が不可能になっているからこその、コペルニクス転向なのではないか。
しかし、だからこそ実践が目指されるべきだとは、私は必ずしも思わないのである。
コペル君の前途は多難であり、果たして彼の青年期以降、仲間はいたであろうか。いや、それ以前に大政翼賛会に入っていたかもしれない。

インターネットに落っこちていたオリンピックの開閉会式の映像(BBCのもの)を観た。ほとんどロック・フェスティバルであった。さすがロックの国英国。噂では、NHKの中継は、イギリス文化へのリスペクトを欠いたひどいものであったという。私はみていないので何とも言えないが、我が国の国営放送なんかに期待している方がまちがっている。しかも、自分の国の文化さえ理解せずA×Bなどにうつつを抜かしている如き我が国の現象は、英国でも違うかたちでは起こっているはずであって、――いずれにせよ、文化の本体はオリンピックなんぞには出てこない。
しかし、さすがに閉会式の堂に入ったロック・フェスティバルっぷりをみていると、我々の世界は、こういう文化様式に完全に支配されてしまっており、我々がそれを模倣しようとして失敗を繰り返す原因に思いをいたさずにはいられない。
特にポピュラー・ミュージックに詳しくないわたくしでも、でてくるミュージシャンや芸人をだいたい知ってた。モンティ・パイソンの人間大砲や「Always Look On The Bright Side Of Life」の危険きわまりない歌詞に対してもなんとか苦笑いできた。
I am he as you are he as you are me and we are all together.
See how they run like pigs from a gun, see how they fly.
I'm crying.
まるでオリンピックの為の曲にきこえてきたな……。
この曲が終わると、ファットボーイスリムがでてきた。感動した。さすが阿片戦争に代表される不健康文化に関してこの国にはかなわない。ピンクフロイドの「炎」のジャケットの模倣が出てきた場面は泣けた。ジェシー・J、相変わらず歌うまいなあ……。
……という感じで、すっかりイギリスに文化侵略されていたわたくしであったが、最期にいまやお爺さんの The Who がでてきて、「マイ・ジェネレーション」を歌っていたのは笑った。
I hope I die before I get old.
……何歳になってるのか知らんが、さすがである。体だけが丈夫な若者達よお前達ももう少しで老人だ、あるいは、我々はまだ若いと言っているのか、いままでごらん戴いたロック音楽は老人達の戯言だと皮肉っているのか、大英帝国はもうとっくに死んでいるが(あるいはもっとはやく死にたかったのだが……)若い世代のためにオリンピックなんかやってますという皮肉なのか……。
──まあ、ベルリン大会を筆頭とする歴史を「崇高化」する国威発揚もあれば、今回のように「戯画化」を含んだ国威発揚もある。しかし、いずれも、自分たちの音楽や映像に普遍性がある(つまり「売れてる」)という自信がなきゃできないことは確かなのである。その点、我々は非常に追いつめられている。
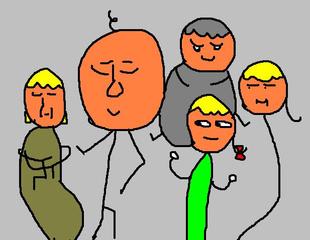
↑
ジム・ヴェンダースの「まわりみち」を見ていたら、オリンピックがとっくに終わっていた。ゲーテの「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」を基にした映画である。作家志望でスランプのヴィルヘルムであるが、その口から出てくる言葉は、スランプだからというより単なる未熟さの現れとも思える──が、そもそも修業時代とはとても恥ずかしいものである。教養小説はその未熟さを人生全体にまで敷衍していくようなものである。そりゃそう見たければそうみえるであろう。──わたくしが子どもの頃、「ジャン・クリストフ」や「ああ無情」を初めて読んだ時の感想は、人生終わりまでこんなに辛いのか、であった。それは完成や目標達成とは無縁であった。といっても「或る女」の結末よりはましか、と思った。ジャン・クリストフやジャン・バルジャンは最期だけ、昇天の壮大なコーダによって人生から退場できるからだ。しかし、私は、「不如帰」より先に「或る女」を読んでいて良かったとおもった。少なくとも、それは、「コーダなし」が「自覚」されるからである。そういえば、リストは「ダンテ交響曲」を書く時に、ワーグナーに「天国篇は無理だよ」、と言われて、地獄と煉獄しか作曲しなかった。この世が地獄でも天国でもあるワーグナーにとって、天国篇は許せなかったのに違いない。しかし、ワーグナーのような生悟りの方が突然「いまこそ天国来ました」とか言いがちである、こっちの方がよほど現代的な問題である。
というわけで、辛いのが大嫌いのわたくしなので、オリンピックは
★柔道女子松本さん金メダル……インタビュアー「集中力はどこからくるんですか」→松本さん「わかりません」。受け答えも金メダル!
★体操男子内村さん金メダル……身長がわたくしに近いのが好感が持てる。
★女子レスリング伊調さん金メダル……「(3連覇)目指してやってきた訳じゃない」→かっこいい
★女子レスリング小原さん金メダル……年齢がわたくしに近いのが好感が持てる。
★女子レスリング吉田さん金メダル……中日ドラゴンズの井端選手に似ているという評判の人であるが、井端選手が浮き沈みのある人であるのに対して、このひとの成績はすごいな。いままで金メダルしかとってないじゃん。もっとみんな褒めろや。
★ボクシング男子ミドル村田さん金メダル……
★レスリング男子米満さん金メダル……吉田さんとの試合を見てみたい。
★女子ウェイト・リフティング三宅さん銀メダル……重いものは、男が持てっ。
★アーチェリー男子古川さん銀メダル……わたくしに眼鏡が似ている。
★バドミントン女子ダブルス銀メダル……羽子板の方が音がいいと思う。
★フェンシング男子フルーレ団体銀メダル……
★卓球女子団体銀メダル……唯一中国でも喜ばれたメダルであろう。
★サッカー女子銀メダル……リメンバー・パールハーバーを忘れるべからず。アメリカは日本には二度負けない。
★競泳男子……まず、速く泳ごうとするならみんなクロールでいいのではないだろうか。
★柔道……柔ちゃんがいなくなったとたんピンチ的な書き方をされているのが気の毒だ。
★女子バレーボール銅メダル……強くなると人間から魔女に昇格する競技である。
★男子100、200メートル……ボルトはわたくし(2㍍)に負けた腹いせにいつも全力で走らない。
★新体操女子……唯一中継で見たよ。浅倉南ちゃんとか、全然容姿で負けてるな。ロシアなど、ほんとの妖精を出してくるのは卑怯なり。日本ががんばって妖精を名乗っているのに。
★野球……球場が広すぎるから、東京ドームで開催すべし。
★スキージャンプ・ラージヒル……まず、こんなシュチュエーションは007の冒頭ぐらいでしかあり得ない。
★数学オリンピック……灘とか筑駒に入ると金メダルとれるかもしれません。
★雪合戦……いじめ発見には最適である。

昔のゼミ生(自称=不肖の弟子)からの暑中見舞いは、上のような形をしていたので、いきなり郵便受けからいきなり転がり落ちた。がんばれ不肖の弟子。
「先生、えらく投げやりですね」と言われたので、いわゆる「ツンヤリ」であるということにしました。「つんつん投げやり」の略です。しかし、よくみたら「ツンナゲ」の方がよいような気がしますから「ツンナゲ」にしましょう。
「ツンデレ」の時代は終わりました。時代は、他人につんつん、しまいにゃ放り投げる時代です。
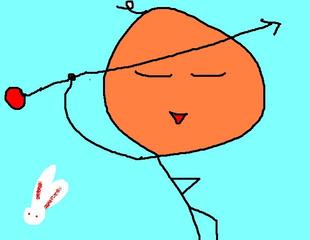
↑
つんつん槍投げ
「ツンデレ」の時代は終わりました。時代は、他人につんつん、しまいにゃ放り投げる時代です。
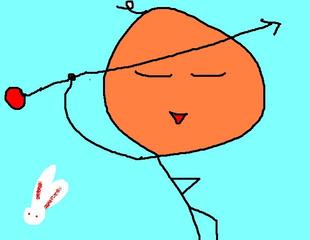
↑
つんつん槍投げ

芥川龍之介の演習の個人指導を行っていたところ、教員採用試験(一次)の結果を知らせに卒業生がぞろぞろやってきた。(なかにもう一昨年既に合格して現役の教員をやっているやつが混じっている……あ、遊びに行くついでにわしのところに寄っただろ、オマエラ……)
あなた方は、試験や現場(笑)からの解放感をなぜ大学にきて味わっているのであるか、もう一回入学しよう、そうしよう。

Veni, creator spiritus,
Mentes tuorum visita;
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

学生には、本というものは選んで買ってもいいが眼つぶって手に触れたものを買うエネルギーと勇気をも持たなければならない、と説教しているわたくしであるが、最近はわたくし自身にそんなエネルギーが徐々になくなりつつあるのは非常に遺憾である。
というわけで、左翼関係の研究から出発した癖に、どうも代々木の本となると妙に尻込みしていたわたくしの旧弊を破ろうと、不破哲三の妻(上田七加子さん)の自伝を買ってみた。
不破哲三と上田七加子は10代にして既に共産党の同志であったが、夫婦になる前には大して接点もなかったと書いてあった。しかし一度、通学途中の電車で彼女が座っていたら前に不破哲三が大量の本を風呂敷に包んで目の前に立っていたので、「本を膝の上に乗せてもいいわよ」と言ったことがあったらしい。なんだ、ロマンスの匂いがぷんぷんするではないかっ。実際どうだったかはともかく。
今日、めざましでばたっと起きあがり、時計の頭を叩きに行った間、どうみても3秒ぐらい。
ボルトに勝った!
ボルトに勝った!
ボルトに勝った!

ボルトに勝った!
ボルトに勝った!
ボルトに勝った!













