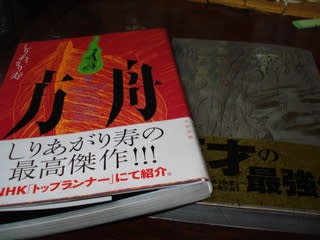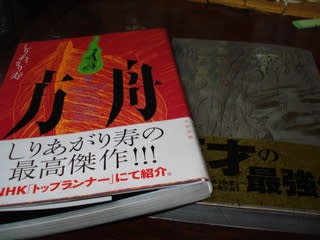
しりあがり寿は好きな作品を書いてくれる作家であるが、なんとなく懐かしい感じがする。『方舟』は、数ある世界滅亡もの?のなかでもすごく叙情的な気持ちのいい作であるが、各話の最初に掲げられる旧約聖書の引用には「主」がいるのに、降り続く雨によって水没する
人類の日本の世界には主がいない感じが濃厚である。したがって方舟つくったのに、ノアもいなけりゃ動物も乗せない。パニックになった市民が乗り込んで死んでゆくだけである。そりゃ、日本を描いてるから、そうなるのであろうが、たぶん作者は、主をいただいていない癖に滅亡してリセットしたがる我々──という問題を強く意識しているにちがいない。日本で最後の?山村の一軒家で、ラジオかテレビから君が代が流れているのは、その証拠であろう。最近も、パンドラの匣の希望やらうんたらかんたらを引用して、顰蹙を買っていた東北復興関係の文書があったけれども──我々はそんななんの内的必然性もない生とその説明に対して、いかにして制裁を下せるのか分からない。だからめんどうくさいので全員しんじまえ、となる。我々がそう思うのは単に我々が中学生的だからではないと思う。大の大人が「エヴァンゲリオン」とか「ドラゴンヘッド」とか創作して、なぜかそこに力がこもるのはどうみてもおかしいのである。「真夜中の水戸黄門」も、その線の作品ではなかろうか。テレビドラマの水戸黄門のやってることは、(ちょっと暴力を含んだ)調停であるが、しりあがりの水戸黄門は、悪代官集団を超能力で皆殺しにする、印籠から電波が出て、江戸幕府のロケット艦隊がやってきて絨毯爆撃をする。最後の場面、黄門が拝謁するのは、将軍というよりベールの向こう側にいる
天皇のイメージに対してであるかのようだ。しかしこの
天皇は、虐殺の罰として黄門にショコクマンユーを与える絶対神である。水戸黄門が庶民に受けてきた理由に潜む欺瞞?をある意味描いているのであろうが……。
いずれにせよ、こういう寓話的な描き方が何となく懐かしさを覚える理由でもある。いまの若者達は、寓話でも日本はどうにもならないのを知っており、みずから寓話的な人物になろうとする傾向があるのではなかろうか。しかし……
『ヨブ記』のような恐ろしい神との対話は我々にはありえない。どうもがいても自分と似た他者との対話になってしまうような気がする。
ところで、上のような問題に加えて、江藤淳など読み返して、われわれの父母─子問題を考えてみたかったのだが、どうも私は、そういう問題が苦手である。