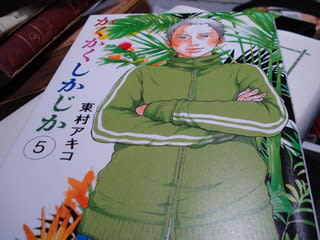村上春樹のすごいところは、いつの間にか速読法を身につけたらしいと錯覚を起こすほどはやく読めるということである。本書でも述べられているが――、徹底的な推敲によって文章が研磨されているのである。彼が音楽好きなのは非常に彼の作品にとって本質的である。音楽を模倣しようとする如く、へたくそなアーティキュレーションを許さないのである。だから、読者はどんどん読んで(聴いて)しまう。しかしだからこそ、作者の文章(演奏)が嫌いな息づかいだと感じる人は、内容以前に不快感を感じる。音楽の演奏は、仮に作品が普遍的な感情や理念を目指していたとしても、その息づかいを聴衆に受け入れさせることができるかが、まあとりあえずは問題になるところだろう。カラヤンやフルトヴェングラーにファンとアンチがいるのと同じ現象が、村上の小説にたいしても起こる。
だから(たぶん……)、どういう内容だったのか案外読者は忘れがちであり、わたくしも職業柄だいたい主要な作品は読んでいるはずなのに、ほとんど覚えていない。試しに「風の歌を聴け」をおおかた読み直してみたのだが、中絶や恋人の死などが描かれていることさえ覚えていなかった。
村上の小説は、たぶん、死者の鎮魂であり、全体として「レクイエム」みたいなジャンルなのだと思う。そこでは、生前のことを細かくあげつらったりはしない。そういう時には、やっぱりあいつも人間だった、弱い人間だった、それで死んだ、なにも出来なかった、などと言っておくのがよいだろう。どうも村上の小説をよんでいると、その延長で生者も死者みたいな属性(上のような)を持ち始めるような気がする。私は全くそうは思わないのであるが……。本当に死者とは、生者に対して「弱者」であるのであろうか。そんなことはない。生者も同じことであり、村上の小説の中のように優しく話題をはぐらかしながらしゃべってくれるとは思われないのである。
「風の歌を聴け」のなかで引用されているハートフィールドの小説で、「火星の井戸」というのがあり、ほぼ「ドン・キホーテ」の洞窟のエピソードと浦島太郎をくっつけたみたいな話になっている。村上の小説は、サンチョ・パンザが自らドン・キホーテになったような感じではなかろうか。しかし、サンチョが幾ら反省してもドン・キホーテにならないのは自明ではないか。いや、そうとも限らんが……、どうも私には、「ドン・キホーテ」には自由があり、村上春樹にはない感じがしてならない。
村上春樹にあるメタフィクション的な構造は、対話ではなく拒絶と具体的記憶の精算、が核にあるようだ。村上氏が、日本的な文章を捨て普遍的な文体を翻訳調に求めて日本を越境してしまったという見方は当たらない、と思う。外側に越境しようとする意識は、根本的に西洋文学(外)の翻案的な性格が強い近代文学の――村上氏の言う日本的な文脈やらコンテンツに縛られることである。彼はむしろ、内側に――何もない内面という底的な穴――というより「演奏」する生身の村上氏――に越境しようとする作家である(これが日本近代文学では案外珍しい姿勢であることを村上氏ははじめから自覚的であり、その意味で、きわめて挑戦的な作家だった。村上氏が嫌われたのもそこに原因があるであろう。)予想はしていたが、本書で村上春樹が大学を含めた学校生活を本当につまらなかった、と嘆息していることは印象に残った。音楽や小説に比べてそれは本当につまらなかった、と。私も似たようなものだったから、その気持ちは理解できるが、自分の学校生活をつぶさに点検してみりゃ、その発言はたぶん出て来ない。村上氏の言うように、頭が「クラッシュ」してしまうからである。だから誰でも内側に越境する、すなわち自浄作用が必要になるわけであるが、村上氏の場合は、小説を読むこと、そして
その完全な延長線上に小説の創作をおくことになる。だから、彼の場合は、自浄作用を働かせようとする時にもうすでに小説を書ける気がし、成功する予感までしてしまう。我々が「あー、よっしゃ、なかったことにしよう」という一言を吐く場合に、村上氏の場合はそれが長編小説にまで引き延ばされるのであろう。長い嘆息である。しかし嘆息であるから、嘆息の終わる瞬間まで予感できているのはあたりまえである。
というわけで、村上氏の小説が読まれるのは、我々がやっぱりあまりにストレスを抱えているからではなかろうか、と思わざるをえない。その意味で、村上氏の小説は、裏返された、というか癒やし系宗教と化した教養小説といえなくはないと思う。だから、まあ、ストレスを徹底して文学で救済しようとしているところが、スゴイと思う。小説にも認識があるぜとか言いつつ、えせ科学みたいなものを人文科学が目指した結果自滅しかかっているところをみると、その意味では、村上春樹は正しかったと言わざるを得ない。ただ、私は、この道にはこれ以上自由はないと思う。学校にだって、どこにだって、自由はあるはずである。
村上春樹の饒舌さに影響されて長く書いてしまったが、相変わらず、彼にある浄化作用は私にはなかなか働かない。







 」という語尾を上げる口調が許されるのは、×田さんだけだ。そこらの女子学生はゆるさん。わたくしも女子の友達がほとんどだった気がする。男子は汚くて粗雑だからいやだ。……とはいえ、小さい頃はよくでかい女子に頭をはたかれていたような気がする。乱暴者はきらいだよ
」という語尾を上げる口調が許されるのは、×田さんだけだ。そこらの女子学生はゆるさん。わたくしも女子の友達がほとんどだった気がする。男子は汚くて粗雑だからいやだ。……とはいえ、小さい頃はよくでかい女子に頭をはたかれていたような気がする。乱暴者はきらいだよ