2010年9月2日
<script type="text/javascript"></script> 加工された板金をさわって確かめる学生たち=足立区小台2丁目の株式会社フクムラ
加工された板金をさわって確かめる学生たち=足立区小台2丁目の株式会社フクムラ
『 ものづくりの現場を自分たちの目でみようと、東京電機大学atom.dendai.ac.jp千代田区神田錦町)の学生たち15人が1日、足立区の三つの町工場を見学した。学生たちは町工場の技術力の高さや重要性を肌で感じ、工場の社長も「やってみたい作業があればいつでも連絡してほしい」と歓迎した。 見学した工場は、金属線材の切断から多様な加工までを行う「ノボリ www.knobori.co.jp/index.htm 」、ガラスの成型・研磨加工などをする「沼田光器www.numatakouki.com 」、板金加工の「フクムラwww.bestcom.jp/fukumura 」。学生は工学部機械工学科や未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の学部生と大学院生。同大の神田キャンパスは2012年4月に足立区内に移転予定で、機械工学科の阿高松男教授は「町工場との意見交換、共同研究や委託研究なども視野に入れたい」と話した。 沼田光器の従業員・パートは15人で、高級腕時計用のサファイアガラスの研磨技術の高さが認められ、国内外の時計メーカーと取引している。下川進社長は「サファイアを磨きたいという人がいればいつでも来てください」。 機械工学科4年の小島康志さんは、塗装しやすい材料をつくるメカニズムを研究している。「大企業の製品ばかり注目されがちだが、町工場が部品をつくっているから成り立っている。大小にかかわらずどれも必要であることを改めて知った」と話していた。』アサヒ・コム
日本の高度な生産技術を支えているのは、町工場、中小零細企業です。何゛年の経験に基づいた職人さんの技術は、メイドインジャパンの高品質で、信頼の置ける製品作りに長年貢献していることを知るべきです。東京電機大学の工学部機械工学科や未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の学部生と大学院生の有意義な工場見学会です。労働力が豊富、安い賃金の中国製品の輸入の多い中、日本の町工場も大変な経営状況になっていると思います。昔のメイドインジャパンの後を追っているのが中国製品と思います。安かろう悪かろう、とにかく安く作るより、高品質で、安心して消費者が使える丈夫で、信頼の置ける日本製品を日本国内や世界市場に送り出し、世界同時不況下で回復景気回復の見通しの付かない日本経済を建て直し、国際競争力をつけるべきです。東京電機大学は、神田キャンパスが2012年4月に足立区内に移転予定ですので、新しい研究や発明、科学技術研究の成果を足立区の町工場の活性化と発展に生かし、町おこしに是非貢献してください。東京電器大学の最新研究と開発された技術と町工場の長年培われた人間の経験と技術を合わせれば新しい製品や機械の開発が出来ると思います。産業立国日本の科学技術は、日本の町工場の他国では真似まね出来ず機械では作れない独創的な優れた技術力と町工場の経営者の皆さんの努力によって生まれていると言うことを忘れてはなりません。
| 東京電機大学 | |
|---|---|
|
東京電機大学 本館(神田) | |
| 大学設置 | 1949年 |
| 創立 | 1907年 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人東京電機大学 |
| 本部所在地 | 東京都千代田区神田錦町2-2 |
| キャンパス | 神田(東京都千代田区) 鳩山(埼玉県比企郡) 千葉ニュータウン(千葉県印西市) |
| 学部 | 工学部(I・II部) 理工学部 情報環境学部 未来科学部 |
| 研究科 | 先端科学技術研究科 工学研究科 理工学研究科 情報環境学研究科 |
| ウェブサイト | 東京電機大学公式サイト |
東京電機大学(とうきょうでんきだいがく、英語: Tokyo Denki University)は、東京都千代田区神田錦町2-2に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は電大、電機大、東電大、東京電大、TDU。 学生や大学内では電大という略称を用いることが多いが、校歌の歌詞では東京電大が用いられ(ちなみに校歌の作詞者は草野心平)、インターネット上のドメイン名ではdendaiを用いている。
本学の至近にある秋葉原電気街は、戦後の闇市が無線や電気製品に特化し、さらにジャンク市場となったのが発祥だが、これには本学の影響が多分にあったとされる。
「東京電機」であり「電気」や「電器」ではない。
概観
建学の精神
東京電機大学は、最新の電気や機械を第一線で扱える技術者を養成し、科学技術の総本山となることを目的として設立された「電機学校」を発祥としている。
学風および特色
実学尊重を重視しており、充実した実験・実習科目を備えている。産学協同プロジェクトや、社会人向け講座、社会人学生の受け入れなど、企業とのコラボレーションにも積極的である。
就職
理工系大学の中でも就職に強い大学であるといわれる。就職先には一部上場企業が多く並び[1]、他大学と比較しても就職率は群を抜いているといえる。学生の就職率は高く、毎年コンスタントに90%以上の学生が就職している。
沿革
- 1907年9月11日 廣田精一と扇本眞吉が「電機学校」として創立
- 1914年 電機学校出版局の雑誌部が独立し、オーム社となる
- 1939年 東京電機高等工業学校及び東京電機工業学校設置
- 1944年 東京電機工業学校を電機第一工業学校と、東京電機高等工業学校を電機工業専門学校と改称。電機第二工業学校設置
- 1948年 電機学園高等学校設置(電機第一工業学校・電機第二工業学校を合併・移行)
- 1949年 学制改革により東京電機大学を開設(工学部第一部電気工学科・電気通信工学科設置))。初代学長に丹羽保次郎が就任
- 1950年 東京電機大学短期大学部開設
- 1952年 工学部第二部開設
- 1958年 大学院開設(工学研究科電気工学専攻設置)
- 1965年 高等学校を神田校舎から小石川校舎に移転
- 1968年 電機学校を神田校舎から小石川校舎に移転
- 1977年 鳩山キャンパス開設。理工学部を設置
- 1981年 大学院理工学研究科開設
- 1990年 千葉ニュータウンキャンパス開設
- 1992年 高等学校を小石川キャンパスから小金井キャンパスに移転開校 東京電機大学電機学校廃止
- 1996年 東京電機大学中学校設置
- 2000年 理工学部に情報社会学科、生命工学科を設置
- 2001年 千葉ニュータウンキャンパスに情報環境学部を設置
- 2004年 大学院情報環境学研究科を設置
- 2005年 東京電機大学短期大学休止、秋葉原ダイビル内に秋葉原ブランチを設置
- 2006年 情報環境学部を2学科から1学科に統合し、情報環境学科に変更。大学院博士後期課程を先端科学技術研究科に変更
- 2007年 工学部・理工学部を改編し、新たに未来科学部を神田キャンパスに設置
- 2008年 工学部第二部電気工学科、電子工学科を改編し、電気電子工学科を設置
- 2012年 北千住駅東口のJT社宅跡地に新キャンパス「東京千住キャンパス」を設置予定
教育および研究
組織
学部
- 工学部第一部
- 電気工学科(2009年度まで)
- 情報通信工学科
- 電子工学科(2009年度まで)
- 機械工学科
- 環境物質化学科(2007年度名称変更)
- 機械情報工学科(2009年度まで)
- 建築学科(未来科学部へ移動)
- 情報メディア学科(未来科学部へ移動)
- 電気電子工学科(2007年度設置)
- 未来科学部(2007年度設置)
- 情報メディア学科
- 建築学科
- ロボット・メカトロニクス学科
- 工学部第二部
- 電気工学科(2010年度まで)
- 電子工学科(2010年度まで)
- 情報通信工学科
- 機械工学科
- 電気電子工学科(2008年度設置)
- 理工学部
- 数理科学科(2009年度まで)
- 情報科学科(同上)
- 情報システム工学科(同上)
- 建設環境工学科(同上)
- 知能機械工学科(同上)
- 電子情報工学科(同上)
- 生命工学科(同上)
- 情報社会学科(同上)
- 理工学科(2007年度設置)
- 理学系(2009年度サイエンス学系から名称変更)
- 数学コース
- 化学コース
- 物理学コース
- 数理情報学コース
- コンピュータ科学コース(2011年度まで)
- 情報システムデザイン学系
- コンピュータソフトウェアコース
- ネットワークシステムコース
- アミューズメントデザインコース
- 社会コミュニケーションコース
- コンピュータサイエンスコース(2009年度設置)
- 生命理工学系
- 生命科学コース
- 生物環境コース
- 生体電子情報コース(2011年度まで)
- 医療・機械システムコース(2011年度まで)
- 創造工学系(2011年度まで)
- 知能機械コース(電子・機械工学系へ移動)
- 電子機械コース(電子・機械工学系へ移動)
- 都市デザインコース(建築・都市環境学系へ移動)
- 建築デザインコース(建築・都市環境学系へ移動)
- 電子・機械工学系(2009年度設置)
- 知能機械コース
- 電子機械コース
- 電子システムコース
- 建築・都市環境学系(2009年度設置)
- 都市デザインコース
- 建築デザインコース
- 共通教育群
- 理学系(2009年度サイエンス学系から名称変更)
- 情報環境学部
- 情報環境学科
- 情報環境工学科(2008年度まで)
- 情報環境デザイン学科(同上)
大学院
- 先端科学技術研究科 - 博士
- 数理学専攻 - 博士(理学)
- 電気電子システム工学専攻 - 博士(工学)
- 情報通信メディア工学専攻 - 博士(工学)
- 機械システム工学専攻 - 博士(工学)
- 建築・建設環境工学専攻 - 博士(工学)
- 物質生命理工学専攻 - 博士(工学・理学)
- 先端技術創成専攻 - 博士(工学・理学)
- 情報学専攻 - 博士(情報学)
- 工学研究科 - 修士
- 電気工学専攻
- 電子工学専攻
- 物質工学専攻
- 機械工学専攻
- 精密システム工学専攻
- 情報通信工学専攻
- 情報メディア学専攻
- 建築学専攻
- 理工学研究科 - 修士
- 数理科学専攻(2009年度まで)
- 情報科学専攻(同上)
- 情報システム工学専攻(同上)
- 建設環境工学専攻(同上)
- 知能機械工学専攻(同上)
- 電子情報工学専攻(同上)
- 生命工学専攻(同上)
- 情報社会学専攻(同上)
- 理学専攻(2009年度設置)
- 情報学専攻(同上)
- デザイン工学専攻(同上)
- 生命理工学専攻(同上)
- 情報環境学研究科 - 修士
- 情報環境デザイン学専攻
- 情報環境工学専攻
付属機関
- 総合研究所
- エクステンションセンター
- 先端工学研究所
- 建設技術研究所
- ハイテク・リサーチ・センター
- フロンティア共同研究センター
- 産官学交流センター
- 総合メディアセンター
- 出版局 - 教職員らが執筆する論説集や学生向け教科書などを発行する。東京電機大学出版局。ちなみに、理工学専門書、コンピュータ関連書などを出版するオーム社の前身でもある。
関連学校
- 東京電機大学電機学校(※1992年3月廃止)
- 東京電機大学短期大学 - 電気科(※2000年を最後に募集停止。2005年廃止)
- 東京電機大学中学・高等学校 - 普通科
大学関係者と組織
キャンパス
東京神田キャンパス
大学院工学研究科、工学部第一部、工学部第二部、未来科学部 (大学・法人本部)
- JR中央線・総武線 「御茶ノ水駅」 徒歩8分
- JR山手線・京浜東北線 「神田駅」 徒歩8分
- 東京メトロ丸ノ内線 「淡路町駅」 B7出口・徒歩3分
- 東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水駅」 B7出口・徒歩3分
- 都営地下鉄新宿線 「小川町駅」 B7出口・徒歩3分
- 東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄三田線 「神保町駅」 A7出口・徒歩8分
- 東京メトロ銀座線 「神田駅」 1番出口・徒歩8分
- 東京メトロ東西線 「竹橋駅」 3B出口・徒歩8分
埼玉鳩山キャンパス
URLhttp://www18.ocn.ne.jp/~abc8181
プログランキングドツトネット http://blogranking.net/blogs/26928












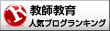

 男性職員が小笠原諸島から持ち帰ったというサンゴの一部。計9キロ余=秋田県
男性職員が小笠原諸島から持ち帰ったというサンゴの一部。計9キロ余=秋田県




