『処分に困り、やっかい者扱いのホッキ貝の殻を、粉状に砕いて2枚の和紙に挟んだ壁紙を作る試みが11日、いわき市遠野町入遠野の同市オートキャンプ場体験小屋であった。実験では、殻はシックハウス症候群を引き起こす化学物質、ホルムアルデヒドの空気中の濃度を下げる効果が認められ、壁紙は製品化にもつながればと期待される。 同市の福島県立勿来、なこそ工業高校www.nakoso-th.fks.ed.jp/top/topics/<wbr></wbr>mezasupe/matome.html )工業化学科の生徒らが、約4年前から取り組む廃棄物有効利用研究の一つ。ホタテの貝殻がホルムアルデヒドを分解するとの報告に注目し、ホッキ貝で実験。昨年、貝を細かく砕いて加熱した粉を漆喰(しっくい)に混ぜて置くと、周囲のホルムアルデヒド濃度が下がったという。 今回は「伝統産業と結びつけよう」と、遠野和紙2枚の間に貝の粉を層状に挟んで壁紙としたところ、漆喰と同様の効果が確かめられたという。 この日の試作には、3年生3人が参加。和紙作りに携わる「磐城手業(てわざ)の会」の指導で和紙をすくところから始めた。生徒は「和紙をすくのは難しいが、空気がきれいになればうれしい」と話した。池田光治教諭は「福島県沖はホッキ貝のいい漁場だが、廃棄される大量の貝殻は使い道がなく困っていた。作ってみたい人にはデータの提供もできる」と話した。』毎日新聞 2010年6月12日 地方版
処分に困り、やっかい者扱いのホッキ貝の殻を、粉状に砕いて2枚の和紙に挟んだ壁紙が実験で、殻はシックハウス症候群を引き起こす化学物質、ホルムアルデヒドの空気中の濃度を下げる効果が認められのは、自然に育っているものから環境がを浄化され空気が綺麗になる。自然の力、自然に生育しているものの偉大さと思います。人間に有害な化学物質には、化学物質で対応するのではなく生物の間にも自然の力でないと命や生活が守れ無いと言う自然から掲示と教えと思います。ホッキ貝の殻いわき市の産業廃棄物として処理に困っていたかも分かりませんが。ホッキ貝の貝殻と日本の伝統にはぐくまれた和紙と日本家屋の 壁に使われて来た漆喰も役立つということが分かり、昔の人の智恵と日本の伝統技術が生かされた空気を綺麗にするのに役立つと言う素晴らしい実験結果です。いわき市の県立勿来工業高校工業化学科の生徒皆さんも物づくりの大切さと日本の伝統技術が生かされ手作られて来たさ和紙や漆喰は、、日本人の生活に密着し作られた昔から生産されているものは、健康と環境を守る大切な役割を果たしていたと言うことを発見されたと思います。物の作りの原点、地場産業や地域の活性化に繋がる地元工業高校の存在意義も見直すべきでは無いでしょうか。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
漆喰(しっくい)とは、瓦や石材の接着や目地の充填、壁の上塗りなどに使われる、消石灰を主成分とした建材である。
<script type="text/javascript"></script>
概要
しっくいは、カルシウムを主成分としており、もとは「石灰」と表記されていたものであり、漆喰の字は当て字が定着したものである。
風雨に弱い土壁そのままに比べて防水性を与えることが出来るほか、不燃素材であるため外部保護材料として、また調湿機能に優れているため、古くから城郭や寺社、商家、民家、土蔵など、木や土で造られた内外壁の上塗り材としても用いられてきた建築素材である。面土や鬼首などの瓦止めの機能のほか、壁に使用される場合には、通常で3~5ミリ程度、モルタルなどへの施工の場合は10数ミリ程度の厚さが要求されている。塗料やモルタルなどに比べ乾燥時の収縮は少ないものの、柱などとの取り合い部に隙間が生じやすいため、施工の際には留意が必要である。
二酸化炭素を吸収しながら硬化する、いわゆる気硬性の素材であるため、施工後の水分乾燥以降において長い年月をかけて硬化していく素材でもある。
近年では化学物質過敏症の原因の主たるものとされる、ホルムアルデヒドの吸着分解の機能があるものとして注目を浴びている。
分類
我が国における漆喰は現在、大きく5種に分けられる。
- 旧来漆喰とされてきたもの。現地にて昔ながらに海藻を炊いてのりを作り、麻すさと塩焼き消石灰を混合して作られる。
- 3ヶ月以上発酵させた藁と塩焼き消石灰と水を混合し、1ヶ月以上熟成させたもの。そのため藁の成分が発色し、施工直後から紫外線で退色するまでは薄黄~薄茶色の姿に仕上がる。練り状の製品しか存在しない。
- いわゆる「漆喰メーカー」が製造した漆喰製品。一般に塩焼き消石灰と麻すさ、粉末海藻のり、炭酸カルシウムなどの微骨材が配合された粉末製品。水を加え練ることで漆喰として使用される。近年では海草のりに加え、合成樹脂を使用した製品や、化学繊維を使用した製品、顔料を混ぜて色をつけた製品もある。また、練り置き済み製品も存在する。
- 藁と生石灰を混合したものに水を加え、生石灰に消化加熱反応を起させることで藁を馴染ませ、さらにそれを擂り潰し熟成させたもの。土佐漆喰に比べ藁の混入量が多いため、紫外線で退色するまでは濃黄~薄茶色の姿に仕上がる。練り状の製品しか存在しない。沖縄の屋根瓦工事を中心に用いられる。
- 近年上市されている、漆喰の機能を有するとされる塗料や海外製の消石灰が配合された塗り壁材など。現状は既調合漆喰との区別をする規定がない。
上記5種以外に、本漆喰から派生した地域独特の漆喰が存在する。(肥後漆喰など。)
原料
- 漆喰の主成分となる。コブシ大程度に砕かれた石灰岩を土中窯や徳利窯と呼ばれる竪窯で、石炭やコークスを燃料として塩を加えながら焼かれる「塩焼き」で焼成された生石灰から作られた消石灰。一般に「塩焼き灰」と呼ばれる。
- 収縮防止やつなぎ(補強)効果を与える。麻に類する植物繊維が主に使われてきたが、現在では豆類や香辛料が輸入される際に包材となる南京袋を加工して作られているものが大半である。歴史的には大麻、苧麻のほか、近世に輸入されるようになった綱麻、亜麻、マニラ麻、サイザル麻などが使われている。土佐漆喰や琉球漆喰のすさには藁が用いられるほか、上級の上塗り漆喰には紙繊維も用いられる。また、関東地域を中心として「つた」とも呼称される。
- 「のり」と呼称されるが、壁に使用される場合、漆喰へ混入される一番の目的は「接着」ではなく「保水効果」による作業性の向上である。さらに粘度調整効果も求められる。
- 歴史的には布海苔、銀杏草、角叉などの海藻を煮炊きして抽出したものが使われていた。現在は加熱後乾燥、粉末化された粉末海藻のりが主流となっている。その原料のほとんどに銀杏草が用いられている。原料海藻は国内では東北~北海道が産地であるが、収穫量が少ないため、韓国や南米産の海藻も多く使われている。
- また、原料海藻を「ふのり」や「つのまた」と総称して呼ばれてきた歴史があるため、実際の品種とは異なる呼称が使われることも少なくない。
- 屋根用や壁の中塗り用として川砂などの骨材が混入される。また、主原料となる消石灰に含まれる水酸化カルシウム分が過剰であるなどして収縮力が強すぎる場合には、その緩衝材として微粉骨材が混入されることが多い。
- 天然由来であるため不安定とされる海藻のりの効果を補填するために使用され始めたが、現在では接着効果として考えられているケースが多々ある。そのため、最も多く使用されている水溶性樹脂メチルセルロースのほか、アクリル樹脂や酢酸ビニル樹脂など様々な樹脂が混入されている製品が存在する。
- ナイロン繊維やガラス繊維など。麻すさの代用品としてだけでなく、強度向上や作業性向上のため混入されている。
- 古くは松煙と呼ばれる油煤を原料とした黒顔料や弁柄など、漆喰に色を着ける目的で使用されてきた。近年ではカーボンや鉱物系顔料など、様々な顔料が用いられている。
- 漆喰に練りこむことで、防水効果を向上させる目的に使われてきた。その技法は台風など雨の影響を受けやすい西日本に多く見受けられる。種類としては古くは荏油、鯨油、魚油、桐油などがあるが、現在は菜種油が主流である。
歴史
建築材料としては、神話の時代から接着剤として知られており、バベルの塔に関する記述に、「しっくいの代わりにアスファルトを得た」という記述が残っている[1]。原始的な漆喰(ほぼ石灰)は日本では古墳(高松塚古墳壁画等)などにも使われている。
また、多くの城郭の壁に使用されており、室町時代末(1565年)に信貴山城(奈良)を訪れた宣教師イスマン・ルイス・ダルメイダは、「今日までキリスト教國において見たことがなき甚だ白く光澤ある壁を塗りたり。其の清潔にして白きこと、あたかも當日落成せしものの如く、天國に入りたるの感あり。外より比城を見れば甚だ心地よく、世界の大部分にかくの如く美麗なるものありと思はれず」と、所感を述べている。
戦後、在来工法建築とともに急速に衰退したが、近年、土蔵の海鼠壁や古民家の鏝絵などを通じて文化的に再評価されつつある。また、漆喰の特性を生かしたタイル(漆喰タイル)も開発されている。










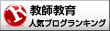

 腕を伸ばしたときと縮めたときの走りの違いを示し、走り方を指導した=福岡市東区
腕を伸ばしたときと縮めたときの走りの違いを示し、走り方を指導した=福岡市東区





