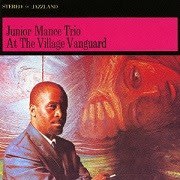アート・ペッパーの全盛期が1950年代後半にあったことは衆目の一致するところと思いますが、この頃の彼は主にコンテンポラリー・レコードから名作群を発表する一方、マイナーレーベルにも少なからぬ作品を残しています。以前に同ブログで紹介したジャズ・ウェスト盤「ザ・リターン・オヴ・アート・ペッパー」、イントロ盤「モダン・アート」、他にタンパ盤「アート・ペッパー・カルテット」、そして今日ご紹介するオメガテープ盤「ジ・アート・オヴ・ペッパー」等がそうです。特にオメガテープはアート・ペッパーのこの作品でしか名前を聞いたことがないような希少レーベルです。しかもそれらマイナーレーベルへの録音は1956年夏から1957年春頃にかけての短期間に集中しており、いかにペッパーがこの時期に多くのレコーディングセッションをこなしていたかがわかります。
精力的な活動の理由としては、麻薬中毒による2年間の収容生活から復帰したペッパーがブランクを取り戻すべく心機一転張り切ったというのもあるでしょうが、裏の理由としてはクスリ代欲しさの小遣い稼ぎの意図もあったのかもしれません。この頃のペッパーはキャリアの中では比較的安定して活動していた時期ではありますが、それでも麻薬の悪癖を完全に克服できたわけではなく、常時クスリを必要としていました。コンテンポラリーはウェストコーストジャズを代表するレーベルではありましたが、おそらくそこからの収入だけでは足りなかったのかも、と邪推してしまいますね。
本盤は発売当時はLPではなく、オープンリールと言う8ミリテープのような媒体で発売されたもので、長らく幻の音源扱いでしたが、今ではCDで手軽に聴くことができます。録音年月は1957年4月。メンバーは西海岸を代表する黒人ピアニストであるカール・パーキンス(ピアノ)に同じく黒人のベン・タッカー(ベース)、ドラムにはチャック・フローレスと言う布陣で、タッカーとフローレスは「モダン・アート」にも参加しています。

収録曲は全12曲。もともとは2枚のアルバムに分かれていたものをCD1枚にまとめたため、かなりのボリュームです。オープニングの"Holiday Flight"とラストトラックの"Surf Ride"は1952年録音の名盤「サーフ・ライド」からの再演で、5年の月日を経て円熟した演奏となっています。それ以外は基本的に歌モノスタンダード中心ですが、こちらも"Too Close For Comfort”"Long Ago And Far Away""I Can't Believe That You're In Love With Me"など他のペッパー作品で聴かれる曲が収録されています。ペッパーのお気に入り曲だったのでしょう。中では"Long Ago And Far Away"が出色の出来栄えと思います。
それ以外でおススメはまずコール・ポーターの”Begin The Beguine"。スイング時代のアーティ・ショー楽団で有名な曲で、スモールコンボのバージョンは少ないですが、ここではペッパー流の見事な解釈で魅惑のミディアムチューンに仕上がっています。また、ペッパーは黒人ジャズメンの曲もちょくちょく取り上げますが、本作ではバド・パウエルの”Webb City"がそれに当たります。ハードドライビングなチャック・フローレスのドラム演奏に乗せて、ペッパーとカール・パーキンスがノリノリの演奏を繰り広げます。"Body And Soul"のバラード演奏やラテンナンバーの”The Breeze And I”も捨てがたいです。全部で65分弱という異例のボリュームのためさすがに後半にスタンダード曲が続くあたりややダレるのは否めませんが、それでも全体的なクオリティはさすがで、全盛期ペッパーの充実ぶりがよくわかる1枚です。