秋田市内の秋もいよいよ終盤。今週はいい天気が続いていたが、来週半ばは雪になるらしい。
今年最後の秋田の秋として、南西部の新屋(あらや)地区を取り上げてみたい。
※2日に分けて撮影した画像を使用しています。
新屋は雄物川の河口の町で、川沿いに「美短」と省略される秋田公立美術工芸短大がある。1995年開学の新しい建物だが、一部は「旧国立新屋倉庫」という、昭和9年から平成2年まで米倉庫だったものを転用している。現在は国登録有形文化財。
色合いは違うが、構造や大きな川沿いにあることが明治26年建築の山形県酒田市の山居倉庫に似ている。
山居倉庫は最上川から船で荷揚げする構造だが、こちらは鉄道で運んでいた。JR羽越本線の新屋駅から引き込み線があったそうで、現在は遊歩道になっている。下の画像は駅方向から遊歩道を歩いて敷地に入ったところ。

プログラムオート F5 1/100
突き当たりのコンクリートの建物が短大の校舎。
手前に白い壁、赤い屋根の倉庫が8棟並んでいる。一段高く、屋根の付いている部分がプラットホームだったそうだ。
正確には8棟のうち、7棟が短大とその関連施設、写真手前の1棟は秋田市立新屋図書館の一部になっていて、写っていないがさらに手前に図書館の新しい建物がある。枝を広げたイチョウが1本。
左に曲がって、秋田西中側の図書館正面に回る。

プログラムオート F8 1/400 露出-0.7
こちらは倉庫の西側にあたり、何本かイチョウが植わっている。山居倉庫で最上川と反対側に日よけのケヤキが植えられているのと同じ役目をしていたのかもしれない。
 プログラムオート F11 1/320 露出-0.3
プログラムオート F11 1/320 露出-0.3
いちばん手前のイチョウはほとんど緑色の葉だが、奥の方はだいぶ落葉している。日当たりもそんなに違わないはずなので、いっせいに黄葉してくれるときれいなのだけど・・・
倉庫の屋根上にもう1つ小さな屋根が付いていて、明かり取りの窓になっている(現在は遠隔操作で開閉できるようだ)。空の青、屋根の赤、イチョウの黄。コントラストが美しい。
 プログラムオート F7.1 1/400 露出-0.3
プログラムオート F7.1 1/400 露出-0.3
短大側から図書館方向を振り返る。
秋の光と影(15時頃撮影)。

プログラムオート F5.6 1/200
秋田大橋横の雄物川の堤防にも行く。太平山が少し赤く見えた。
 プログラムオート F10 1/320 露出-0.7
プログラムオート F10 1/320 露出-0.7
今年最後の秋田の秋として、南西部の新屋(あらや)地区を取り上げてみたい。
※2日に分けて撮影した画像を使用しています。
新屋は雄物川の河口の町で、川沿いに「美短」と省略される秋田公立美術工芸短大がある。1995年開学の新しい建物だが、一部は「旧国立新屋倉庫」という、昭和9年から平成2年まで米倉庫だったものを転用している。現在は国登録有形文化財。
色合いは違うが、構造や大きな川沿いにあることが明治26年建築の山形県酒田市の山居倉庫に似ている。
山居倉庫は最上川から船で荷揚げする構造だが、こちらは鉄道で運んでいた。JR羽越本線の新屋駅から引き込み線があったそうで、現在は遊歩道になっている。下の画像は駅方向から遊歩道を歩いて敷地に入ったところ。

プログラムオート F5 1/100
突き当たりのコンクリートの建物が短大の校舎。
手前に白い壁、赤い屋根の倉庫が8棟並んでいる。一段高く、屋根の付いている部分がプラットホームだったそうだ。
正確には8棟のうち、7棟が短大とその関連施設、写真手前の1棟は秋田市立新屋図書館の一部になっていて、写っていないがさらに手前に図書館の新しい建物がある。枝を広げたイチョウが1本。
左に曲がって、秋田西中側の図書館正面に回る。

プログラムオート F8 1/400 露出-0.7
こちらは倉庫の西側にあたり、何本かイチョウが植わっている。山居倉庫で最上川と反対側に日よけのケヤキが植えられているのと同じ役目をしていたのかもしれない。
 プログラムオート F11 1/320 露出-0.3
プログラムオート F11 1/320 露出-0.3いちばん手前のイチョウはほとんど緑色の葉だが、奥の方はだいぶ落葉している。日当たりもそんなに違わないはずなので、いっせいに黄葉してくれるときれいなのだけど・・・
倉庫の屋根上にもう1つ小さな屋根が付いていて、明かり取りの窓になっている(現在は遠隔操作で開閉できるようだ)。空の青、屋根の赤、イチョウの黄。コントラストが美しい。
 プログラムオート F7.1 1/400 露出-0.3
プログラムオート F7.1 1/400 露出-0.3短大側から図書館方向を振り返る。
秋の光と影(15時頃撮影)。

プログラムオート F5.6 1/200
秋田大橋横の雄物川の堤防にも行く。太平山が少し赤く見えた。
 プログラムオート F10 1/320 露出-0.7
プログラムオート F10 1/320 露出-0.7










 傾いているのはドア側のバネの空気を抜いて乗降しやすくしているため。
傾いているのはドア側のバネの空気を抜いて乗降しやすくしているため。 プログラムオート F4 1/100
プログラムオート F4 1/100 プログラムオート F7.1 1/250
プログラムオート F7.1 1/250 プログラムオート F7.1 1/250
プログラムオート F7.1 1/250 プログラムオート F4.7 1/160
プログラムオート F4.7 1/160 プログラムオート F8 1/160 露出-0.3
プログラムオート F8 1/160 露出-0.3 プログラムオート F8 1/200 露出-0.3
プログラムオート F8 1/200 露出-0.3
 プログラムオート F5.6 1/125 露出-0.7
プログラムオート F5.6 1/125 露出-0.7 プログラムオート F5.6 1/125 露出-0.7
プログラムオート F5.6 1/125 露出-0.7
 プログラムオート F5 1/30 露出-0.7
プログラムオート F5 1/30 露出-0.7



 プログラムオート F6.3 1/250 露出-0.7
プログラムオート F6.3 1/250 露出-0.7 プログラムオート F5 1/125 露出-0.7
プログラムオート F5 1/125 露出-0.7 プログラムオート F7.1 1/320
プログラムオート F7.1 1/320 プログラムオート F6.3 1/250 露出+0.3
プログラムオート F6.3 1/250 露出+0.3 プログラムオート F5 1/200 露出-0.3
プログラムオート F5 1/200 露出-0.3 プログラムオート F4 1/100 露出+0.3
プログラムオート F4 1/100 露出+0.3 プログラムオート F5.6 1/200 露出-0.3
プログラムオート F5.6 1/200 露出-0.3 プログラムオート F4.5 1/125 露出+1.0
プログラムオート F4.5 1/125 露出+1.0 プログラムオート F5 1/200 露出-0.3
プログラムオート F5 1/200 露出-0.3
 プログラムオート F10 1/320 露出-0.3
プログラムオート F10 1/320 露出-0.3 プログラムオート F6.3 1/200
プログラムオート F6.3 1/200 プログラムオート F9 1/400 露出-0.3
プログラムオート F9 1/400 露出-0.3 プログラムオート F10 1/320 露出-0.3
プログラムオート F10 1/320 露出-0.3
 プログラムオート F3.6 1/80
プログラムオート F3.6 1/80

 プログラムオート F8 1/160 露出-0.3
プログラムオート F8 1/160 露出-0.3
 プログラムオート F7.1 1/320 露出-0.3
プログラムオート F7.1 1/320 露出-0.3 プログラムオート F5 1/80 露出-0.3
プログラムオート F5 1/80 露出-0.3 プログラムオート F3.5 1/80 露出-0.7
プログラムオート F3.5 1/80 露出-0.7 プログラムオート F8 1/400 露出-0.3
プログラムオート F8 1/400 露出-0.3 プログラムオート F7.1 1/320
プログラムオート F7.1 1/320 プログラムオート F8 1/400 露出-0.3
プログラムオート F8 1/400 露出-0.3 プログラムオート F10 1/320 露出-0.7
プログラムオート F10 1/320 露出-0.7 プログラムオート F7.1 1/320 露出-0.3
プログラムオート F7.1 1/320 露出-0.3 プログラムオート F9 1/320 露出-0.7
プログラムオート F9 1/320 露出-0.7 プログラムオート F7.1 1/320 露出+0.7
プログラムオート F7.1 1/320 露出+0.7 プログラムオート F/5.6 1/200 露出-0.3
プログラムオート F/5.6 1/200 露出-0.3 プログラムオート F/4.4 1/60 露出-0.3
プログラムオート F/4.4 1/60 露出-0.3 プログラムオート F/4.5 1/125 露出-0.3
プログラムオート F/4.5 1/125 露出-0.3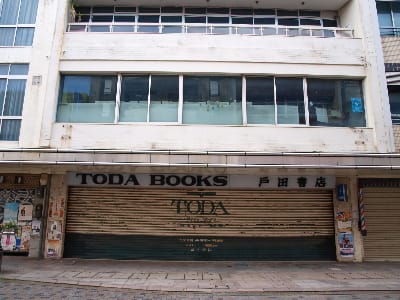 プログラムオート F/3.5 1/80 露出-0.3
プログラムオート F/3.5 1/80 露出-0.3 プログラムオート F/5.6 1/200 露出-0.3
プログラムオート F/5.6 1/200 露出-0.3 プログラムオート F/5.6 1/100 露出-0.3
プログラムオート F/5.6 1/100 露出-0.3 プログラムオート F/5.6 1/60 露出-0.3
プログラムオート F/5.6 1/60 露出-0.3 プログラムオート F/3.5 1/80 露出-0.3
プログラムオート F/3.5 1/80 露出-0.3 プログラムオート F/5.3 1/60
プログラムオート F/5.3 1/60 プログラムオート F/10 1/250 露出-0.3
プログラムオート F/10 1/250 露出-0.3 プログラムオート F/5 1/125 露出-0.7
プログラムオート F/5 1/125 露出-0.7
 プログラムオート F/3.5 1/50 露出-0.7
プログラムオート F/3.5 1/50 露出-0.7 シャッター優先 F/3.5 1/200
シャッター優先 F/3.5 1/200 シャッター優先 F/4 1/200 露出-0.3
シャッター優先 F/4 1/200 露出-0.3 シャッター優先 F/3.5 1/200 露出-0.3
シャッター優先 F/3.5 1/200 露出-0.3 シャッター優先 F/5.2 1/250 露出-0.3
シャッター優先 F/5.2 1/250 露出-0.3 プログラムオート F/5.6 1/100 (熱海駅で撮影)
プログラムオート F/5.6 1/100 (熱海駅で撮影) プログラムオート F/6.3 1/200 露出-0.3
プログラムオート F/6.3 1/200 露出-0.3 プログラムオート F/5 1/80
プログラムオート F/5 1/80



