【キカラスウリ(黄烏瓜)
野草:ウリ科カラスウリ属
花期:6月~9月
キカラスウリは北海道から九州に分布する多年生のツル植物。雌雄異株である。地下部に太い塊茎があり、大量のデンプンを蓄えており、デンプンをとる。地上部は枯れるが、毎年同じ場所に繁茂し、農家の納屋などに絡んでいるのをよく見かける。花は6月後半から9月にかけて咲き、夕方から咲き始めて朝にはしぼみ始める。筒状で先端は5弁にわかれ、先端は糸状に細裂していて芸が繊細である。
キカラスウリはカラスウリに似て果実が黄色であるとの意味である。花弁先端の糸状に分かれた部分はカラスウリの方が長くて繊細である。
◎2010年7月29日 太閤山にて 写真3枚追加しました。



◎2009年7月20日 砺波市郊外にて

野草:ウリ科カラスウリ属
花期:6月~9月
キカラスウリは北海道から九州に分布する多年生のツル植物。雌雄異株である。地下部に太い塊茎があり、大量のデンプンを蓄えており、デンプンをとる。地上部は枯れるが、毎年同じ場所に繁茂し、農家の納屋などに絡んでいるのをよく見かける。花は6月後半から9月にかけて咲き、夕方から咲き始めて朝にはしぼみ始める。筒状で先端は5弁にわかれ、先端は糸状に細裂していて芸が繊細である。
キカラスウリはカラスウリに似て果実が黄色であるとの意味である。花弁先端の糸状に分かれた部分はカラスウリの方が長くて繊細である。
◎2010年7月29日 太閤山にて 写真3枚追加しました。



◎2009年7月20日 砺波市郊外にて












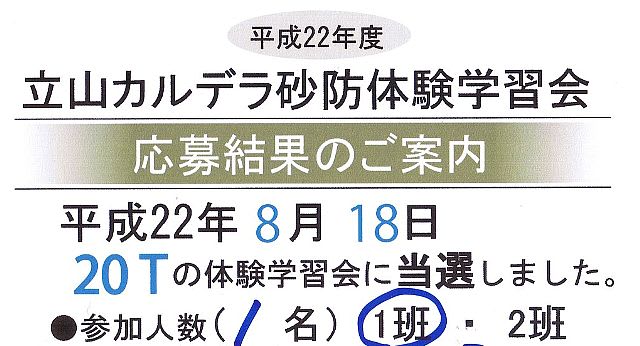







































 、隕石が降ってご神体となった「御石神」
、隕石が降ってご神体となった「御石神」

















































