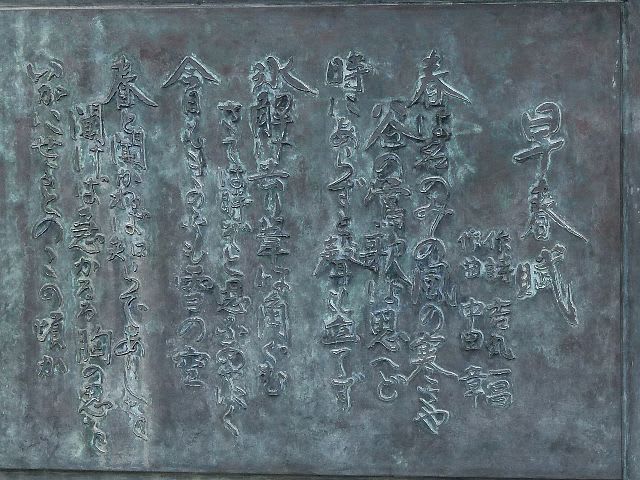【立山の高山植物撮影(その1)】
第4回自遊塾講座 立山の高山植物と星空撮影
県民カレッジ自遊塾 『写真で綴る「絶景」富山の特等席めぐりⅢ』
2011年7月23日(土) 立山:室堂平~一の越~浄土山(中腹)~室堂平
その1 室堂平から一の越
その2 一の越から室堂平
その3 一の越周辺(浄土山中腹)
その4 チョウノスケソウとタテヤマチングルマ
第4回自遊塾講座『立山の高山植物と星空撮影』として天狗平山荘宿泊の1泊2日で催されましたが、今回は個人の都合により一日目の立山の高山植物を撮るに参加しました(私だけ日帰り参加です)。
午前6時に立山駅に集合(土日で夏休みに入っている為かもうすでに駐車場は一杯でした)、6時20分のケーブルに乗車立山・室堂に向かいました。
本日の撮影目的のチョノスケソウを撮るため(私個人としてはタテヤマチングルマも)浄土山の近くまで登りました。
◎立山ケーブルカーの車窓から・・・トンネル内を撮ってみました。
チョッとぶれていますが、中心をベースに手前を流してみました

◎立山:室堂平からの眺望です。麓では小雨・曇り空でしたが弘法辺りから雲の上に出て、青空が広がっていました。
《左》左から天狗山山荘、中央に立山高原ホテルが見えます。 《右》剣岳と雲海から頂を見せる山々


◎室堂平で見かけた雷鳥(メス)・・・雪渓をバックに望遠で引っ張ってみました

◎シナノキンバイと八重のミヤマキンバイです


◎チングルマのアップの写真とチングルマとコツガザクラの群生です


◎クルマユリです・・・下から目線と青い空を入れてみました

◎ミネズオウとベニバナイチゴとウラジロナナカマドです



◎コバイケイソウと残雪・・・コバイケイソウの群生にバックに残雪を入れました

◎イワショウブとヒメイワショウブ


◎ミヤマキンポウゲとハクサンイチゲの花です


◎ハクサンイチゲとミヤマキンポウゲの群生です
 その2
その2 に続きます