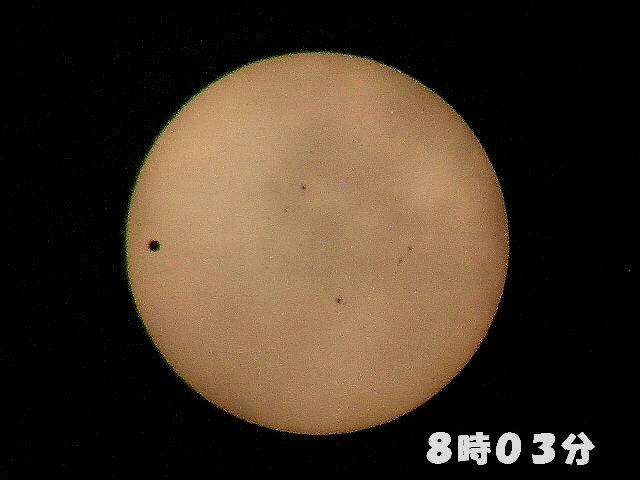2012年6月29日
富山県
梅雨の晴れ間と言おうか?良いお天気が続いているので、今日もミサゴの子育ての様子を見に行って来ました。まだ 巣立ちはしていませんが親鳥がいつも近くで見守っていました。
親鳥と子供達3羽

巣に着地です

近くの梢に止まって周囲の様子を見ていました。


































































【天生湿原自然散策会(その2)】
2012年6月17日(日)
ミズバショウ
ルイヨウボタン・コチャルメルソウ・ルイヨウショウマ・ユキザサ
ニリンソウ・サンカヨウ・コキンバイ・ズタヤクシュ
カツラの門(5本のカツラの木が出迎えてくれます)
カツラの門(遊歩道が2本の巨木の間を通っています)・・・人と大きさを比べてください
キヌガサソウの花
ミドリニリンソウの花たちです・・・いろいろなミドリニリンソウがありました


おわり