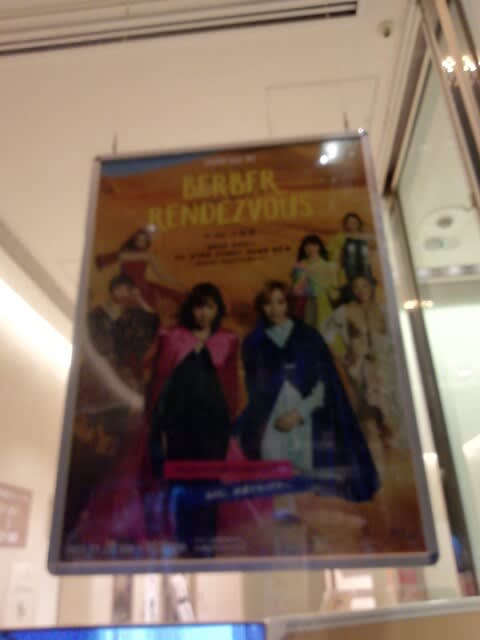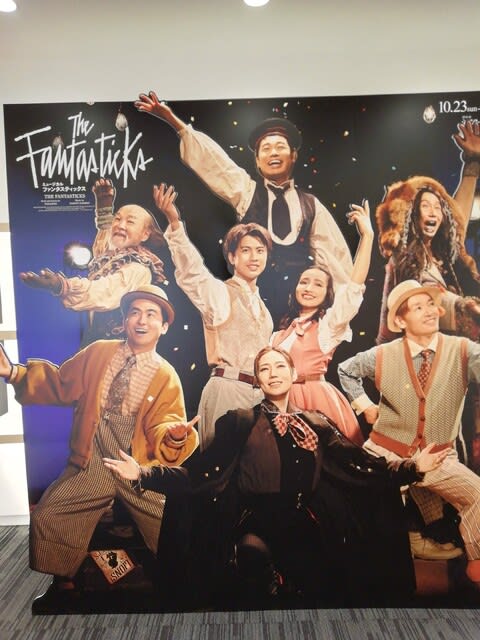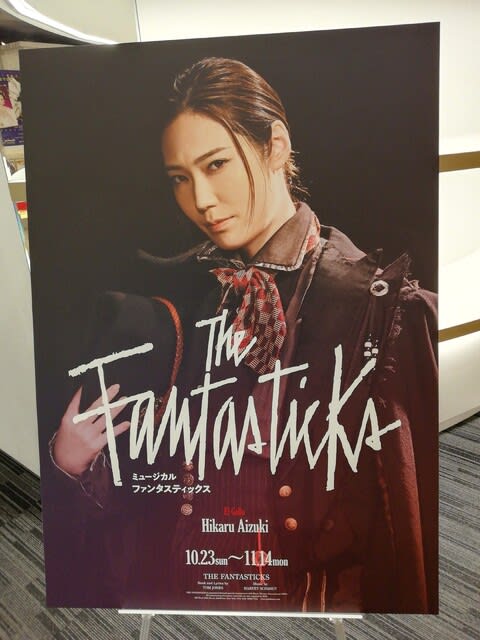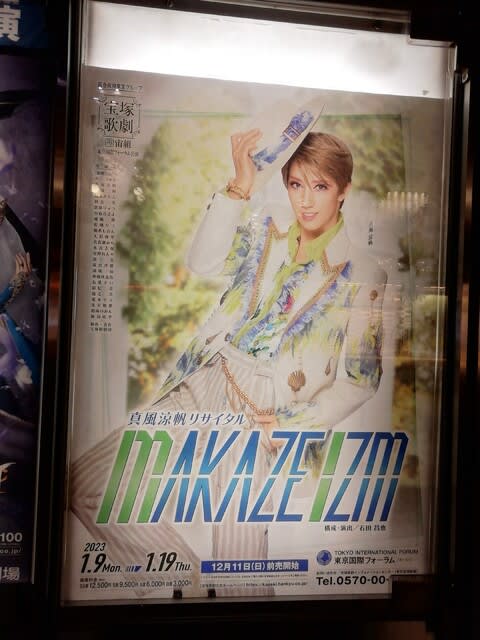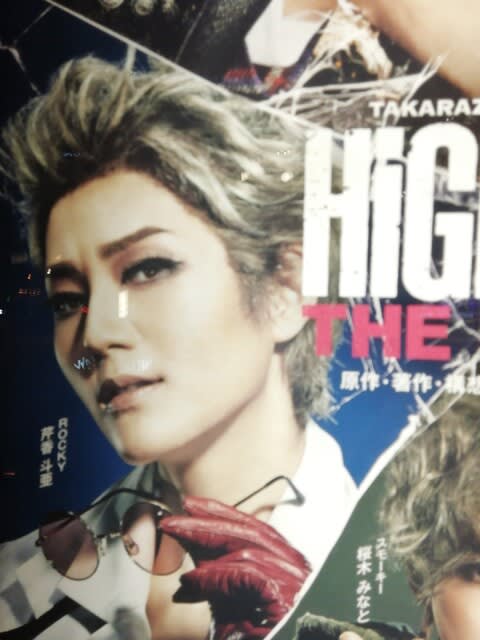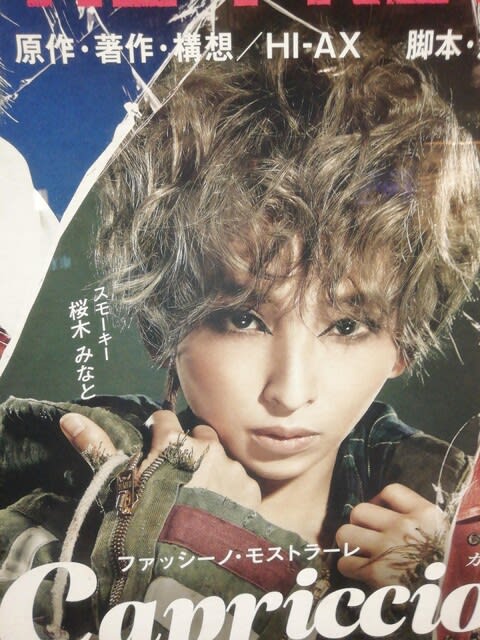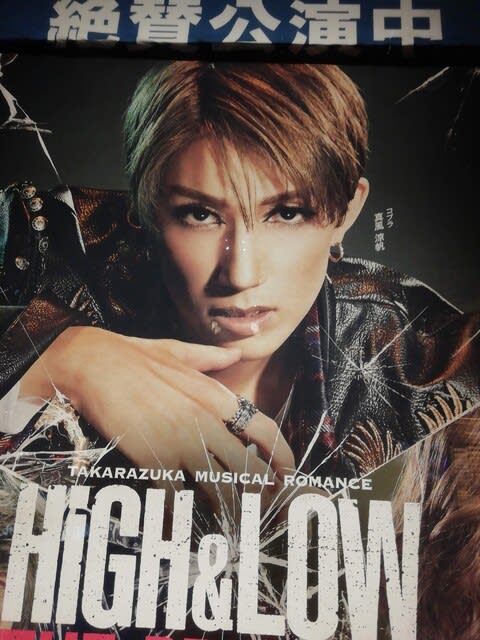2022年11月10日NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221110/k10013887021000.htmlより、
「政府 新型コロナ「第8波」に備え新方針 外出自粛など要請も-
新型コロナの「第8波」に備え、政府は、ことし夏の「第7波」と同じ程度か、それを上回る感染状況になった場合には、都道府県が「対策強化宣言」を出し、住民に外出自粛などを要請できるようにする方針を決めました。
岸田総理大臣は、加藤厚生労働大臣、後藤新型コロナ対策担当大臣と、今後の対応を協議し、新たな方針を決めました。
新たな方針では、現在5段階にわかれている感染状況のレベルのうち、感染者がいない「レベル0」をなくし、4段階に見直すとしています。
そして、ことし夏の「第7波」と同じ程度か、それを上回る状況になった場合などを、レベル3の「感染拡大期」と位置づけるとしています。
「感染拡大期」になれば、都道府県が「対策強化宣言」を出し、住民に対し、症状がある場合の外出や出勤などの自粛や大人数の会食への参加の見合わせなど、慎重な行動を要請できるようにするとしています。
また、医療全体が機能不全の状態になるなどした場合は、最も深刻なレベル4の「医療ひっ迫期」とし、出勤の大幅抑制や帰省・旅行の自粛、それに、イベントの延期など、より強力な要請を可能にするとしています。
政府は、こうした方針を、11日の新型コロナ対策分科会に示すことにしています。」
2022年11月10日女性自身、
https://news.yahoo.co.jp/articles/7f7bcfa690e3af9f276858bf87a6f20c6f663643?page=1
より、
「消費税は15%に、道路利用税を新設…岸田政権が狙う「大増税」が国民を押しつぶす!
10月28日、政府は電気代の負担軽減策などを盛り込んだ総合経済対策を発表。電気、ガス、ガソリン代など標準的な家庭で年間4万5千円の負担軽減となる。
しかしその裏で、増税・保険料増にむける動きも加速している。
「消費税が未来永劫10%のままでは、日本の財政はもたない」
そんな意見が、10月26日に開催された「政府税制調査会」で相次いだのだ。政府税制調査会とは、内閣総理大臣の諮問に応じて、税の制度に関して調査・審議する内閣府の附属機関のこと。委員である識者たちから出された意見を基に議論が行われ、税制改正大綱が作成される。今後の税制改革に大きな影響を与える組織なのだ。
本誌はこの税制調査会での議論を基に、岸田政権が狙う今後の増税の見通しを予測。すると、消費税などの増税だけでなく、退職金や配偶者控除の廃止などといった“実質増税”の全貌が明らかになってきた(表参照)。
「岸田さんは財務省寄りの人間。財務省としても岸田さんが首相のうちに、なにがなんでも増税の道筋を付けておきたいともくろんでいます。なかでも、増税の一丁目一番地は消費税。自民党と癒着した業界の反発を受ける法人税増税などに比べ、消費税の増税は庶民さえ犠牲にすればよく、かつ大きな税収を見込めるんです」
そう語るのは、元経産省官僚で経済評論家の古賀茂明さん。
「消費増税の最速のスケジュールは、今年から議論を始めて、’23年末の税制改革大綱でまとめ、’24年1月から始まる国会で可決しその年の10月ごろには実施というもの。ただし、岸田首相が途中で交代し、増税に後ろ向きな安倍派や菅派から首相が出ることになれば、トントン拍子には進みませんが……」
仮に、もくろみどおり進んだ場合、消費税率は何パーセントまで上がるのだろうか。国際通貨基金(IMF)が’19年に出した報告書によると、「日本は’30年までに消費税率15%にする必要がある」と明記されているのだが……。
「本気で財政を健全化させるなら、消費税率は20~25%になってしまいます。ただ、賃金が上がっていない現状では難しいので、IMFの報告書に便乗し『前倒しして15%にします』というのは、十分ありえる数字でしょう」
そう予測するのは、同志社大学大学院ビジネス研究科教授でエコノミストの浜矩子さん。
そのほか、比較的早く導入されそうなのが“炭素税”の新設だ。
「Co2排出量に応じて企業に課税する炭素税は“脱炭素社会に向けて”という大義名分があるので導入しやすいでしょう。そのうえ、’26年からEU諸国に輸出する際、国境炭素税が課せられるというのも口実となります。いきなり導入すると、鉄鋼大手などからの反発が予想されるため、’24年度くらいから低い税率で段階的に開始されるのでは」(古賀さん)
企業が担う炭素税の負担だが、価格転嫁されることで、消費者にしわ寄せがいく可能性は高い。
■退職金控除や配偶者控除も見直される見通し
さらに、老後の頼みの綱である退職金にも魔の手が伸びている。
現在は、勤続年数が長いほど退職金にかかる税の控除額が増える仕組みだ。しかし「勤続年数にかかわらず控除を一律に」という案が税制調査会で議論されている。
「ハードルは高いですが、雇用の流動性を高めるという政府の方針もあり、最短で再来年春の実施もありえます」(古賀さん)
加えて、生活により大きな影響を及ぼすのが、配偶者控除の見直しだろう。
現在、所得が38万円以下(給与所得のみの場合は年収103万円以下)の配偶者がいる納税者は、38万円の控除を受けられる。しかし、第19回の税制調査会の資料内では配偶者控除の見直しが提示され、その選択肢のひとつとして“廃止”が提示されているのだ。
消費税率アップや控除などの廃止によって、私たちの家計負担がどれほど増えるのだろうか。
’21年の家計調査(総務省)を基に試算すると、世帯主が50~54歳の世帯の場合、消費税が15%になると、年21万6076円支出が増える。さらに、これらの世帯(世帯主の月額平均給与55万1422円)で配偶者控除がなくなった場合、所得税と住民税を合わせて年間10万9千円の負担増となる。2つの増税だけで、年間32万5076円も家計負担が増すのだ。
また、第二の税とも呼べる保険料の値上げも忘れてはならない。
政府は10月18日、国民年金の保険料納付期間を、5年延長して45年とする方向で議論を始めている。さらに、65歳以上の高齢者が、毎月支払う介護保険料の引き上げの議論まで進んでいるのだ。
「結局、進むのは抵抗できない低所得者層にばかり負担が重くなる税制改革。岸田首相は当初、富裕層に課税する金融所得課税を実施すると言っていたのに、結局、反発が大きく引っ込めてしまった。本来は、そういうところから課税すべきなのです」(浜さん)
なぜ、岸田首相は決断できないのか。
「岸田首相は安倍派の顔色ばかり見ながら、失敗したアベノミクスを引きずり続けている。財政は悪化するし、成長もしないので、こうやって庶民に増税するしかなくなっているんです」(古賀さん)
このままでは、国民が重税に押しつぶされてしまうーー。」