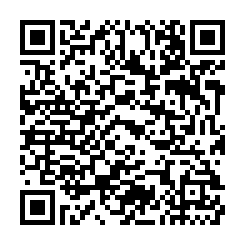ブログやTwitterやFacebook、LINEにInstagramと、SNS花盛りの昨今だ。
その機能は進化して、今や情報発信には画像や動画を添付するのが当たり前の感になった。
それどころか、画像や動画がメインで文章が添え物みたいなSNSも出現した。
文章が不得手、書くのが苦手という人間も、その安直さ故か、こぞって参加するようになり、今やタイムラインは画像や動画で溢れている。
百聞は一見に如かず、というところか。
パソコンやインターネットの普及は、情報発信の活発化やバーチャルでのコミュニケーションの広がりという多大な効果を生み出したが、一方では漢字や英単語の綴りを忘れてしまうという災いをもたらし、書籍や文献を読まなくなるという、いわゆる活字離れの一因ともなっている。
現に私も昔は普通に書けた、多くの漢字や英単語が書けなくなった。
読書量の激減も当然の帰結だ。
そのリハビリの一環として、今、文章修行を兼ねた小説を書いている。
時を同じくして、電子書籍のAmazon Kindleという発表、販売の場ができたことも大きい。
今やそこで販売中の小説は、20冊になる。
画像は言うに及ばず、動画だけではコミュニケーションはできない。
コミュニケーション手段としては言葉に勝るものはないはずだ。
今後も長い文章は小説で、中くらいの文章はブログで、短い文章はTwitterでと、それぞれの特性に合わせた形で、画像や動画に頼らない、文章という言葉で情報を発信していきたい。
その機能は進化して、今や情報発信には画像や動画を添付するのが当たり前の感になった。
それどころか、画像や動画がメインで文章が添え物みたいなSNSも出現した。
文章が不得手、書くのが苦手という人間も、その安直さ故か、こぞって参加するようになり、今やタイムラインは画像や動画で溢れている。
百聞は一見に如かず、というところか。
パソコンやインターネットの普及は、情報発信の活発化やバーチャルでのコミュニケーションの広がりという多大な効果を生み出したが、一方では漢字や英単語の綴りを忘れてしまうという災いをもたらし、書籍や文献を読まなくなるという、いわゆる活字離れの一因ともなっている。
現に私も昔は普通に書けた、多くの漢字や英単語が書けなくなった。
読書量の激減も当然の帰結だ。
そのリハビリの一環として、今、文章修行を兼ねた小説を書いている。
時を同じくして、電子書籍のAmazon Kindleという発表、販売の場ができたことも大きい。
今やそこで販売中の小説は、20冊になる。
画像は言うに及ばず、動画だけではコミュニケーションはできない。
コミュニケーション手段としては言葉に勝るものはないはずだ。
今後も長い文章は小説で、中くらいの文章はブログで、短い文章はTwitterでと、それぞれの特性に合わせた形で、画像や動画に頼らない、文章という言葉で情報を発信していきたい。