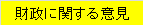立憲民主党は29日の常任幹事会で、最高顧問に菅直人、野田佳彦の両元首相を充てる人事を決めた。
菅直人と言えば東北大震災後の原子炉事故での迷走が記憶に新しい。また、野田佳彦と言えば
消費税増税はしないという民社党の公約を無視して消費税を増税した。
2人とも民主党が政権を失う原因を作った戦犯である。立憲民主党が政権を狙うのであれば、
最高顧問などに登用するのではなく、むしろ厳しく糾弾し彼らが主導した民主党とは異なることを強調すべきである。
元々立憲民主党が設立された当初は過去の民主党とは異なった政党になることを期待したが、
国民民主党との合併によって完全に元の民主党に戻ったようである。
これでは国民は誰も立憲民主党には期待しない。
菅直人と言えば東北大震災後の原子炉事故での迷走が記憶に新しい。また、野田佳彦と言えば
消費税増税はしないという民社党の公約を無視して消費税を増税した。
2人とも民主党が政権を失う原因を作った戦犯である。立憲民主党が政権を狙うのであれば、
最高顧問などに登用するのではなく、むしろ厳しく糾弾し彼らが主導した民主党とは異なることを強調すべきである。
元々立憲民主党が設立された当初は過去の民主党とは異なった政党になることを期待したが、
国民民主党との合併によって完全に元の民主党に戻ったようである。
これでは国民は誰も立憲民主党には期待しない。