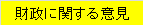農林水産省、JA、自民党農林族の農政トライアングルは、現在の異常な高米価を望ましいと考えている。価格が上がると、零細な兼業農家でも利益が出るようになる。このことは兼業農家を基盤とするJAにとっては好ましい。
しかし日本の農業という点については、このことによって農地の集約は進まず、非効率な兼業農家が残留し、国民は高いコメや農産物を買い続けることになっている。
農業への企業参入に高い障壁が設けられているのも、JAの既得権を守る為でもある。
JAに依存しない大規模農家にとってリスクヘッジの機能を持つ先物市場も、2005年から商品取引所により創設の要請が行われてきたにもかかわらず、価格操作ができなくなるJAの反対により実現せず、特定の産地銘柄の先物取引は認められていない。
今回のコメ不足に対して、農水省は備蓄米を将来的に国が買い戻す条件付きで集荷業者を対象に販売するという。
しかし、コメの流通を担っているのは、卸売業者である。食糧法の規定(第29条、第47条)では、政府が備蓄米を売り渡す相手を集荷業者及び卸売業者としているのに、なぜ売り渡す相手先を集荷業者に限るのか。集荷業者に備蓄米を販売しても、そのコメは卸売業者を通じてスーパー等に販売されるにもかかわらず。
それは集荷業者がJAだからに他ならない。JAへの販売量を増やしてその販売手数料収入を増やすことが目的だということになる。消費者のためではなく露骨な業界保護である。
JAの既得権を守り自らの権益を維持したい農水省により、日本の農業は新規参入を妨げられ、小規模で非効率なままに抑えられている。結果国民は高い農産物を買わされ、今回のようなコメ不足にも直面するようになっている。
農政における農水省とJAの癒着を排除し農業を自由化しない限り、国民は高い農産物を買わされ続けるだろう。
しかし日本の農業という点については、このことによって農地の集約は進まず、非効率な兼業農家が残留し、国民は高いコメや農産物を買い続けることになっている。
農業への企業参入に高い障壁が設けられているのも、JAの既得権を守る為でもある。
JAに依存しない大規模農家にとってリスクヘッジの機能を持つ先物市場も、2005年から商品取引所により創設の要請が行われてきたにもかかわらず、価格操作ができなくなるJAの反対により実現せず、特定の産地銘柄の先物取引は認められていない。
今回のコメ不足に対して、農水省は備蓄米を将来的に国が買い戻す条件付きで集荷業者を対象に販売するという。
しかし、コメの流通を担っているのは、卸売業者である。食糧法の規定(第29条、第47条)では、政府が備蓄米を売り渡す相手を集荷業者及び卸売業者としているのに、なぜ売り渡す相手先を集荷業者に限るのか。集荷業者に備蓄米を販売しても、そのコメは卸売業者を通じてスーパー等に販売されるにもかかわらず。
それは集荷業者がJAだからに他ならない。JAへの販売量を増やしてその販売手数料収入を増やすことが目的だということになる。消費者のためではなく露骨な業界保護である。
JAの既得権を守り自らの権益を維持したい農水省により、日本の農業は新規参入を妨げられ、小規模で非効率なままに抑えられている。結果国民は高い農産物を買わされ、今回のようなコメ不足にも直面するようになっている。
農政における農水省とJAの癒着を排除し農業を自由化しない限り、国民は高い農産物を買わされ続けるだろう。