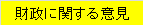発光ダイオード大手の日亜化学工業には「子だくさん企業」というもう一つの顔がある。本社を置く徳島県で生まれる赤ん坊の1割弱は同社の子である。背景には対象男性の7割が取得する育児休業や最高100万円の出産祝い金、時短勤務のしやすさなどの工夫がある。
このことはお金が少子化解消に有効なことの証明でもある。現在は政府も多くの識者の少子化は不可避としている。それでいて新しく説得力ある将来ビジョンを提供できていない。そのことが若者に閉塞感と将来への不安を助長している。
しかし、お金をつぎ込めば子供を増やすことができるという事例が徳島にある。日本にとって少子化かが国家存亡の危機であるならば、他の何を犠牲にしても少子化解消の為に税金を使うべきである。
他の予算を減らし少子化対策に資金を集中すべきであるが、そうしようとすると既得権者からの厳しい反対がおこる。
従来の日本の政治では各省庁と癒着した既得権者への補助金等を削除することは困難であつたが、未曾有の少子化危機にある日本においては、これら既得権者の全ての権益を奪ってでもその資金を子供を増やす為につぎ込むべきである。
このことはお金が少子化解消に有効なことの証明でもある。現在は政府も多くの識者の少子化は不可避としている。それでいて新しく説得力ある将来ビジョンを提供できていない。そのことが若者に閉塞感と将来への不安を助長している。
しかし、お金をつぎ込めば子供を増やすことができるという事例が徳島にある。日本にとって少子化かが国家存亡の危機であるならば、他の何を犠牲にしても少子化解消の為に税金を使うべきである。
他の予算を減らし少子化対策に資金を集中すべきであるが、そうしようとすると既得権者からの厳しい反対がおこる。
従来の日本の政治では各省庁と癒着した既得権者への補助金等を削除することは困難であつたが、未曾有の少子化危機にある日本においては、これら既得権者の全ての権益を奪ってでもその資金を子供を増やす為につぎ込むべきである。