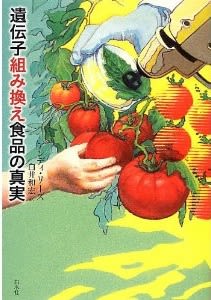『世界展開する"クール"』(2014.03.13)で「遺伝子組み換え食品の真実」をたたき台に遺伝子組み換
え作物の現状を把握、考察を開始したが、長い間放置したままであったことに気付く(約4ヶ月放置)。
そこで一旦リセットし、ここから熟っくり読み進めようと考察をリスタートさせる。
第2章 遺伝子組み換え作物をめぐる全体状況
「遺伝子組み換え技術は、生物学上の核分裂と同じようなものである。かりに、
核爆発ほど危険でなくても、人間にとってきわめて有害であることは確かだ」
ロバート・アンダーソン博士
(ニュージランド「責任ある遺伝学のための医師と科学者の会」会員)
「遺伝子組み換え作物によって、これから十年の間に環境と経済は、中規模から
大規模の破局的な事態を迎えることになるだろう」
ノーマン・エルストランド教授(カリフォルニア大学、環境遺伝学)
(1)核心にある問題
最初に率直に言おう。遺伝子組み換えをめぐる議論は、次のように表現できる。「遺伝子組み換
え技術は、人間の健康を害し、環境と農業に災いをもたらす可能性がある。しかもその結果、一握
りの企業が、私たちの食料となる種子の特許料で貪欲に利益を上げ、さらに世界中の食料の生産と
流通を支配することになるのだ」。それ以外は、枝葉末節の問題である。
次に指摘したいのは、「遺伝子組み換え技術」という用語は、「技術者」という高潔な専門職に
とって侮辱であることだ。「技術」という言葉は「正確さ」を意味する。ところがまさにその「正
確さ」を欠いているのが「遺伝子組み換え技術」の特徴なのである。遺伝子組み換え技術の推進者
だちは、「遺伝子組み換えとは、必要な遺伝子を注意深く取り出して、受容体となるゲノム(生物
体を構成する細胞に含まれる染色体の一紙)の適切な位置に挿入する技術のことである」と人々に
信じこませようとしている。
しかし、植物性タンパク質の研究に四十年以上も取り組んできた、世界的にも有数の専門家アー
パッド・プシュタイ博士は、その主張に反対している。(ちなみに、遺伝子組み換え作物をめぐる
論争の中心に、植物性タンパク質の問題がある)。
「ウィリアム・テルが、的を狙って矢を射る場面を想像してほしい。遺伝子組み換えの場合は、
目隠ししたまま矢を射る。これが遺伝子組み換え技術を使って、遺伝子を挿入するということなの
だ。導入された遺伝子が受容体のゲノムのどの場所に位置しているのか、技術者にはわからないの
が現実なのだ」
すなわち「遺伝子操作」や「遺伝子組み換え技術」という表現は不適切であり、むしろ「遺伝子
細工(Genetic Tinkering)」とでも呼ぶべきなのである。
時代遅れの科学
バリー・コモナー博士など、多くの科学者は次のように指摘する。
「バイテク産業は四十年遅れの科学を基盤にしており、科学の発達を都合よく無視している」
「今では一つの遺伝子によって、複数のタンパク質が生じる可能性がわかっている。これこそ、
バイテク産業が依拠している理論を崩壊させる事実なのである」
マイケル・アントニウス博士も同様に指摘する。
「遺伝子組み換え技術は、時代遅れだ。"遺伝子が独立した情報の単位であり、別の生物に導入し
ても同じ働きをする"という考え方は1980年代の認識である。今日では、遺伝子が複雑で相互に
関連したネットワークの一部として機能していることがわかっている。ある遺伝子が他の遺伝子か
ら独立して機能することはないのだ。新たな遺伝子を挿入すれば、その遺伝子と受容したゲノムの
双方が影響を受ける。遺伝子を配列から取り出した場合に、何か起こるのか予測することも、結果
を完全にコントロールすることもできない。この点が、遺伝子組み換え技術の思考にある、根本的
な欠陥である。遺伝子組み換え技術が正確に機能することはないし、遺伝子組み換え技術は、欠陥
のある科学に依拠しているのだ」
(2) 遺伝子組み換え作物の前史
そもそもなぜ遺伝子組み換え作物が普及したのだろうか。これまでの経緯を簡単に説明しよう。
工業的農業の歴史
工業的農業が先進国で誕生したのは1940年代のことである。今ではどこにでもある農業の姿
であり、英国でも九六%の農地が工業型農業になっている。工業型農業とは、化学肥料・農薬を使
い、画一的な農法で収穫量を上げる農業のことである。除草剤、殺菌剤、殺虫剤や化学肥料などの
農薬に依存した農業なのである。農薬の使用が始まったのは1950年代のことであり、1980
年代後半には使用量が最大となって、今日でも厖大な量が使われ続けている。当初は、こうした農
法が大成功したかのように思えた。先進国では195年代に、途上国でも1960年代初頭には、
単位面積あたりの収穫量が最大に達したからである。
途上国に工業的農業が導入されたのは1960年代であり、食料を増産するというのが表向きの
目標だった。「緑の革命」として知られているように、高収量の種子を使い、化学肥料と農薬を多
投し、直流によって収穫量を増やしたのである。高収量の種子を関発したのが「国際農業調査セン
ターTARC)」であり、この機関は1960年代初期に途上国で設立された。そしてさらに、自
給自足的な農業を営んでいた農民に対して、この高収量の種子の導入を促進したのが、「国際通貨
基金(IMF)」と「世界銀行」だったのである。
その後しばらくの間、収穫量は増えたが「緑の革命」は様々な問題を引き起こした。貧しい農民
を助けるどころか、裕福な農民層に富が集中し、土地も彼らの手に渡ってしまった。余裕のある農
民しか種子や化学肥料を買い続けられなかったために、何千人という貧農は借金の返済に困り、土
地を手放すことになったのである。
しかも農薬の使用量が増加するにつれて、急速に自然の多様性が失われた。農民白身も健康を害
し、地下水、土地、環境が汚染された。潅漑によって水資源が枯渇し、塩害が起きて、農地が使用
できなくなることもあった。土壌の養分は減少し、収穫された作物の栄養素が低下するという新た
な問題も発生した。高収量の種子は害虫に対する抵抗性が弱く、しかも単一栽培が広がったため、
病害虫が発生した時の被害は以前より拡大するようになった。当初、増加した収穫量もやがて頭打
ちになり、連に滅少しはじめた。こうした過程の中で、農業は農民にとって「生活の手段」から、
「利益を求める事業」へと変質し、農業関連企業が製造・販売する様々な商品が普及するようにな
った。
「緑の革命」によって解消されるはずだった飢餓は、構造的な問題になり、空腹と栄養不足に直
面する人々は世界中で8億人も存在する。

自由貿易の推進
世界には物があふれているのに、なぜ貧困が広がっているのだろう。一つの要因は国際政活にあ
り、もう一つの要因は、歴史上初めて、多国籍企業が世界を支配したことにある。
1970年代には、「石油輸出国機構(OPEC)」が原油価格を上げたために二度の石油ショ
ックが起こり、産油国のオイルマネーによって貧困国に対する過剰な融資が行なわれた。融資され
た資金は、それまで人々の生活手段であった農業を変化させることになった。農薬が使用され、熱
帯地域ならバナナやカカオなど、輸出向けの換金作物を生産するための投資がされた。その結果、
地元の農民たちは本来、自分たちの食べ物を生産するための土地を失うこととなった。
しかも、途上国で一次産品が過剰に生産されたために国際価格が下がり、そのうえ、こうした一
次産品を輸入していた先進国も不況になった。途上国に融資された借金の利息は上昇し、途上国で
は長期の借入金が急増した。すると巨額の債務不履行が発生することを恐れた「世界銀行」と「国
際通貨基金(IMF)」は途上国に"構造調整プログラム"を強要した。この政策が目標としたのは、
教育や医療に対する財政支出を強制的に緊縮させるとともに、労働力を減少させ(大量の失業を発
生させ)、環境規制を緩めて、輸出(換金作物の生産量のさらなる拡大)によって外貨を獲得する
ことだった。金融機関はこの状況を利用して、海外企業が有利に参入できるよう途上国に指示し、
その国の産業や天然資源が海外資本に略奪される途を開いていった。
こうして途上国に "構造調整プログラム" を導入したのは、先進国の意図的な政策だった。バイ
テク企業の権力が増加する一方で、多くの造上国は借金を完済できず、今も栄養不足と飢餓がまん
延することになった。
1999年にはドイツのケルンで開催された先進国首脳会議において、「途上国の債務を一部、
帳消しにする」ことが合意された。ところが実際に帳消しにされたのは2005年5月の時点で、
世界最前国の借入金のわずか10%に過ぎない。
そもそも必要なのは、援助だけでなく公正な貿易なのである。ところが貧困国は貿易によって毎
日、13億債ポンドもの損失を披っており、その額は貧困国に与えられた援助金の14倍にも相当
するのである。
結局1980年代以降に推進された。"構造調整プログラム"の基盤にあったのは「自由貿易の推
進」というイデオロギーであり、それを促進してきたのが、先進国の支援を受けて形成された「世
界貿易機関(WTO)」に関わる企業だった。「自由貿易の推進」という大儀名文のため、途上国
2001年までにわずか4社がすべての遺伝子組み換え種子を販売するようになり、現在ではその
90%をモンサント社が占めている。今後は、遺伝子組み換えでない種子を生産する種子企業でも
合併、統合が進むと予測される。がっては利益が上がらなかった作物でも、遺伝子組み換え技術を
導入すれば、農業関連バイテク企業にとって、新たな商品になる可能性があるからだ。
遺伝子革命?
こうしていわゆる「遺伝子革命」が始まった。「緑の革命」の時と同様に、「遺伝子組み換え技術
を導入することは、貧しい農民たちにとって救世主になる」と謳われた。しかし実際には「緑の革
命」と同じように、飢餓を解消すると称して導入されたのは、小手先の農法でしかなかった。作物
の遺伝子を改良して高収量の品種を問発し、農薬も使用するのが「遺伝子革命」の農法なのである。
すでに述べたように「緑の革命」は、多くの農民を苦しめ、環境を破壊して、飢餓をもたらした。
その一方で、大規模農家だけが裕福になり、さらに重要な問題は、農業関連企業が巨額の利益を上
げたことである。

結局、「緑の革命」が失敗に終わった最大の理由は、単純な方法で飢餓問題を解決しようとした
ことにある。本来なら、農業にとって重要な、水の管理、混作、土壌の施肥など持続的な農法を工
夫することによって、収穫量は容易に倍増させられる。それにも関わらず、「緑の革命」はこうし
た農業の基本を無視したのである。過去の反省から学ぶこともなく、遺伝子組み換え技術の推進者
たちは、再び同じ遺を進んでいる。その原因はどこにあるのだろうか。
結局彼らの真の目的は、貧農の飢餓を解消することではなく、企業が食料の生産と流通を支配す
ることにあるのだ。食料生産の分野でバイテク企業の仕事は山ほどある。彼らにとっては、巨大な
マーケットが手つかずのまま広がっている。アフリカでは農民の90%は今も種子を自家採取して
いるし、途上国における大部分の農業は、農薬を使用しない有機農法で行なわれているからである。
(3) 遺伝子組み換えで誰が利益を得るのか?
私が呼ぶところの「遺伝子細工(Genetic Tinkerig)」とは、目的とする形質を得るために、植物
や動物のDNAに一つもしくは複数の遺伝子を挿入することである。たとえば「北極ヒラメ」の遺
伝子をトマトに挿入して、凍りにくい性質をトマトにもたせるようにする。あるいは魚の成長を早
めるために、人間の遺伝子を魚に挿入するのである。
しかし私たちは、遺伝子組み換え生物を求めていないし、私たちが開発を依頼したわけでもない。
結局、バイテク企業の他に利益を得るものはないのである。だからこそ、バイテク産業のロビー
団体は、目的を達成するためには手段を選ばない広告企業に巨額の宣伝資金を投じる必要があるの
だ。バイテク産業は、私たちが食べる食品をつくりかえることで特許料を得ることができる。彼ら
は、私たちには想像もつかないほど、巨大で新しい市場をつくりだしたのである。
疑り深い市民を納得させるためには、「遺伝子組み換え技術が、世界に大きなメリットを生みだ
す」と、もっともらしい理由をいくつも主張する。毎年、何百万トンもの殺虫剤をひたすら製造し
続けている企業が、「遺伝子組み換え作物によって、殺虫剤の使用量を減らせる」と語る。有毒な
化学物質を何百万トンも製造して徹底的に世界を汚染してきた企業が、「遺伝子組み換えによって
環境をよくすることができる」と語る。途上国では平然と子どもを労働力として使い、先進国で禁
止している危険な農薬を輸出してきた企業が、「当社は真剣に人々のことを考えており、世界から
飢餓をなくすためには、遺伝子組み換え技術が必要である」と語る。「遺伝子組み換え種子を無断
で使用されて特許権を侵害された」と主張して農民を告訴する企業が、その舌の根も乾かぬうちに
「遺伝子組み換えは、農民に利益をもたらす」と語るのだ。
彼らの主張はまったく奇妙である。たとえば、もしもカナダで遺伝子組み換え小麦の生産が始ま
ったら、農民は販売先を失い、7800万ドルの損失を彼るという試算がある。ところがその場合
でも、モンサント社の懐には1億5700ドルが入るのだ。
英国政府が2003年に実施した「公開討論」では、八六%の人々が「遺伝子組み換え食品を食
べたくない」と答えている。「巨大企業のやることは、度が過ぎている」と人々は直感的に感じて
いる。ヒキガエルの遺伝子をジャガイモに、魚の遺伝子をトマトに、サソリやクモの遺伝子を野
菜に導入するといった企業のアイデアを、人々は不快に感じているのだ。だからこそ新聞「デイリ
ー・メール」が、遺伝子組み換え食品に「フランケンシュタイン・フード」と命名しても誰も驚か
なかった。1996年に、冷凍食品専門のスーパーマーケット「アイスランド食品」の会長マルコ
ム・ウォーカーは、次のように語っている。
「何百万人という一般の人々が、遺伝子組み換え食品に不安を抱いているが、私もその一人だ。
遺伝子組み換え食品によって、私たちは崖っぷちに来てしまった。生命を構成する基本的な要素を
もてあそぶとは、何と恐ろしいことだろう」
遺伝子組み換えによる環境破壊は問題である。ただし本当は、それ以上に深刻な問題が存在する。
私たちが食べる食品を企業が支配するということは、企業が全人類に対して戦争をしかけるような
大事件なのである。
リーズ、アンディ 著 『遺伝子組み換え食品の真実』
●併せて読んでおきたい一冊
「緑の革命」の考察の参考書? ――本書では、ただたんに人びとから豊かな食生活を奪っただけでは
なく、「コメの品種改良の歴史にひそむ、「科学的征服」の野望」が語られている。裏表紙には、つぎ
のような本書の概略がある。「稲の品種改良を行ない、植民地での増産を推進した「帝国」日本。台湾・
朝鮮などでの農学者の軌跡から、コメの新品種による植民地支配の実態の解明。現代の多国籍バイオ企
業にも根づく生態学的帝国主義(エコロジカル・インペリアリズム)の歴史を、いま繙(もと)く。この概
略を読まないで、帯に大書された「稲も亦(また) 大和民族なり」だけ見て読みはじめると、日本の稲
作文化とそれを支えた農学者たちの礼賛の本ではないかと思ってしまう。著者、藤原辰史は、農学者た
ちの功績を認めつつ、それでも罪悪のほうがはるかに深刻で後世まで引きつづく問題を遺したことに鋭
く切りこんでいく。そして、その功績は市場原理と結びついていったものであり、とくに自家消費用の
在来米を栽培する人びとの生活を豊かにするものではなかったことを明らかにする。著者は、植民地産
米の増産について、つぎのように述べている。「移出する側の植民地の農民は、良質(と内地の市場で
評価される)品種を食べることはまれであり、在来の食味の悪い(と内地の市場で評価される)米や、
粟(あわ)や黍(きび)を食べる。内地米は基本的に自給米ではなく商品であった・・・・21世紀の帝国主義
が、国家の枠を超えて、遺伝子操作技術をはじめとするバイオ・テクノロジーによって人間と人間以外
の生物を同時に支配するという、新しい段階に突入することは間近に迫っているように思われる。医薬
品産業と種子産業はしばしば同一の企業に担われている。古い時代の偶然が新しい時代に必然になるこ
とで、歴史は進展してきたからである――と。早瀬晋三大阪市大教授が書評(2012.09.18)し、次のよ
うに結んでいる。
日本のコメは戦前・戦中の帝国主義・植民地主義と深く結びつき、それが戦後のアメリカの食糧戦
略にも結びついていったことがわかる。そして、「稲も亦 大和民族なり」というように民族文化
と絡み、世界に誇ることができると思っているために、さらにやっかいである。すくなくとも、日
本人の稲のもつ特殊性を理解したうえで、その神聖性は国内にとどめ、外国に押しつけることだけ
はやめた方がよさそうだ。
そういえば、『自我の証明』(2014.06.29)の「技術的特異点 シンギュラリティ」のところで記載
紹介した「考えられうる超人間的知性の中には、人類の生存や繁栄と共存できない――知性の発達と
ともに人間にはない感覚、感情、感性が生まれる可能性がある。AI研究者フーゴ・デ・ガリスはA
Iが人類を排除しようとし、人類はそれを止めるだけの力を持たないかもしれない主張。他の危険性
は、分子ナノテクノロジーや遺伝子工学にに関するもので、これらの脅威は特異点支持者と批判者の
両方にとって重要な問題である。ビル・ジョはその問題をテーマとして Why the future does't need us
(何故未来は我々を必要としないのか)を公表。また、哲学者ニック・ボストロムは人類の生存に対
する特異点の脅威についての論文「Existential Risks(存在のリスク)」をまとめた。多くの特異点論
者は、ナノテクノロジーが人間性に対する最も大きな危険なものだと考えているが、彼らは人工知能
をナノテクノロジーよりも先行させるべきだと主張する」と指摘していることもあり慎重に考えてい
くテーマに違いない。
この項つづく
●美味しい牛肉は日本発?!
ところで、米国内で「WAGYU(和牛)」の文字を含む商標が3日時点で25件認定され、申請中のものが12
件あることが分かったという。和食への関心の高まりに商機を見た食肉業者らが申請の動きを強めてい
るためだが、日本のJA全農も登録申請しているが、同国では別種と交配して生産した牛肉も「和牛」と
して広く流通。商標が乱立する中、和牛肉の対米輸出拡大を目指す日本には、品質の違いを消費者に浸
透させる明確なブランド戦略が必要になりそうだと話題となっている。米国の商標は、「WAGYU」の
名称を独占利用することを認めていない。(文字やデザインの意匠が異なれば)日本から新たに同様の
商標を登録をすることは可能だ」と説明。日本の和牛産地などが米国で商標を得て、独自にブランド展
開する障害にはならないとみる。ただ「KOBE」など日本の産地名を冠した米国産牛肉が先行して流通す
れば、今後輸出増を目指す日本産が埋没したり、混乱を招いたりする恐れがあるという。日本では、和
牛は2007年に決まったガイドラインで(1)黒毛、褐毛などの品種とそれらの交雑種(2)日本国内で出
生し、国内で飼育されたもの――と厳密に定められている。しかし、米国の業界関係者によると、同国
では、日本由来の和牛の血を93.75%以上含めば「和牛純粋種」とされ、この純粋種とアンガスなどを
掛け合わせて生産した牛も「和牛」として広く流通しているのだという。もともと、米国の牛肉を日本
人好みに改良されだしたのは、70年から80年にかけて仲介する日本商社マンなどのの買い付け育成努力
によりなされてきた。それまでの牛肉は堅くて、血が滴るという日本人にはグロテスク?なもの。いま
では遜色ないものが出されるようになった。商社にすればあくまも国内向けのもの。前述した、稲作の
ような「生態学的帝国主義(エコロジカル・インペリアリズム)」でもさらさらない。しかし、欧米は強
かなもの。優良和牛精子を密かに?持ち出し育種し、豪州では「WAGYU(和牛)」として逆輸出して
いるわけだから、中国商法を悪くいう資格はなさそうだ?さて、遺伝子を切り刻み他の遺伝子を組み込
むようなバイオテクノロジーでなければ、商習慣のルールないで思いとどめることができる話だ。