田野町恩山寺谷地区は、小松島市役所の南西約3kmのところ
小松島市役所北側の「小松島市南小松島」信号を西北西へ、県道178号線を進みます
約600mで信号を左(南南西)へ、県道33号線でがJR牟岐線の踏切を越える県道216号線となります
約1.1kmで「⇐室戸・国道55号線」の標識に従って、時差式信号を左(南東)へ、徳島南バイパスです
約400mでコーヒー店前の信号を右(南西)へ、県道136号線です、すぐ先の一時停止に「⇐恩山寺」の案内板です
約500mで「18番札所恩山寺⇒」の標識に従って斜め右(南西)へ

約300mで赤い欄干の橋の先に目的の「恩山寺ビランジュ」の赤い幹がみえました
手前の道路脇に 車を止めさせて頂きました
車を止めさせて頂きました

「びらんじゅ」の標柱です



樹高20m、幹周約2. 4m・約2. 2m・約1. 5mの3本(合計6.1m)の株立ちです

説明版です
天然記念物 恩山寺ビランジュ
昭和29年県指定
ビランジュは、サクラと同属のバラ科の常緑高木である。
もともと3本の木が合わさり一樹となっている。
樹皮は灰褐色であるが鱗片となり脱落しやすく、幹肌は紅黄である。
葉は長楕円形で先はとがり、表面は濃い緑色である。
ビランジュの名は、インドの毘蘭樹にあてたもので、恩山寺が弘法大師ゆかりの地であるため、そう呼び伝えている。
徳島県教育委員会・小松島市教育委員会
*ビランジュは、バクチノキの名前でも知られ、愛媛県宇和島市・瑞林寺のバクチノキ、目通り幹囲5.5mや神奈川県小田原市の早川のビランジュ、目通り幹囲5.2m国指定天然記念物などの巨木も知られています



南東側から



南西側から、独特の色合いですね



西側から



北西側から、玉垣設置から大きくなり過ぎてている様に根が張り出しています



北側から



東側から



山門したから見ました

東側に恩山寺山門です
では、恩山寺へお参りしましょう

2024・6・10・13・10
小松島市役所北側の「小松島市南小松島」信号を西北西へ、県道178号線を進みます
約600mで信号を左(南南西)へ、県道33号線でがJR牟岐線の踏切を越える県道216号線となります
約1.1kmで「⇐室戸・国道55号線」の標識に従って、時差式信号を左(南東)へ、徳島南バイパスです
約400mでコーヒー店前の信号を右(南西)へ、県道136号線です、すぐ先の一時停止に「⇐恩山寺」の案内板です
約500mで「18番札所恩山寺⇒」の標識に従って斜め右(南西)へ

約300mで赤い欄干の橋の先に目的の「恩山寺ビランジュ」の赤い幹がみえました

手前の道路脇に
 車を止めさせて頂きました
車を止めさせて頂きました
「びらんじゅ」の標柱です




樹高20m、幹周約2. 4m・約2. 2m・約1. 5mの3本(合計6.1m)の株立ちです


説明版です
天然記念物 恩山寺ビランジュ
昭和29年県指定
ビランジュは、サクラと同属のバラ科の常緑高木である。
もともと3本の木が合わさり一樹となっている。
樹皮は灰褐色であるが鱗片となり脱落しやすく、幹肌は紅黄である。
葉は長楕円形で先はとがり、表面は濃い緑色である。
ビランジュの名は、インドの毘蘭樹にあてたもので、恩山寺が弘法大師ゆかりの地であるため、そう呼び伝えている。
徳島県教育委員会・小松島市教育委員会
*ビランジュは、バクチノキの名前でも知られ、愛媛県宇和島市・瑞林寺のバクチノキ、目通り幹囲5.5mや神奈川県小田原市の早川のビランジュ、目通り幹囲5.2m国指定天然記念物などの巨木も知られています




南東側から




南西側から、独特の色合いですね




西側から




北西側から、玉垣設置から大きくなり過ぎてている様に根が張り出しています




北側から




東側から




山門したから見ました


東側に恩山寺山門です

では、恩山寺へお参りしましょう


2024・6・10・13・10
































 .
. 












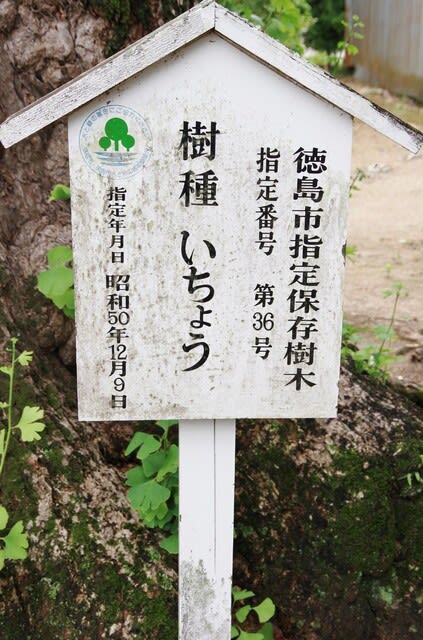































































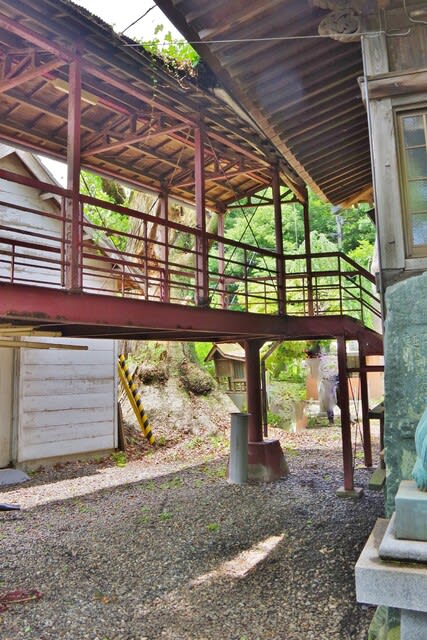

























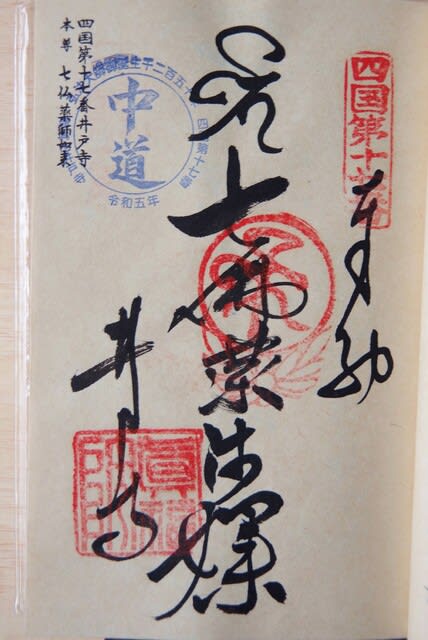













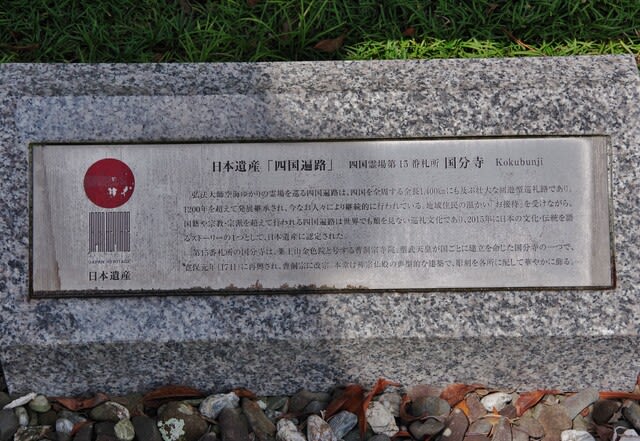





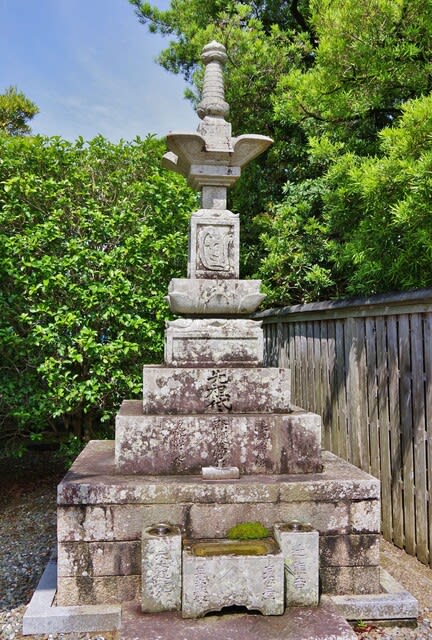




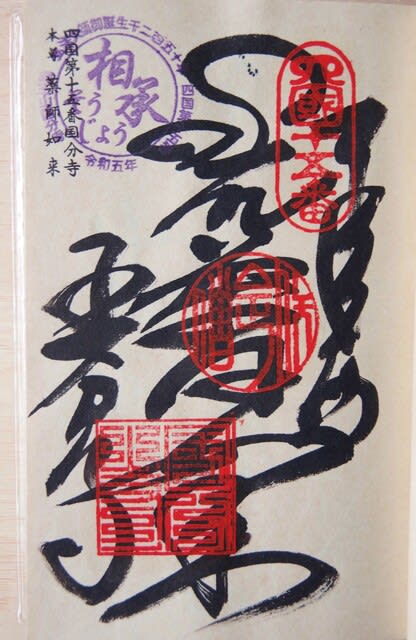
































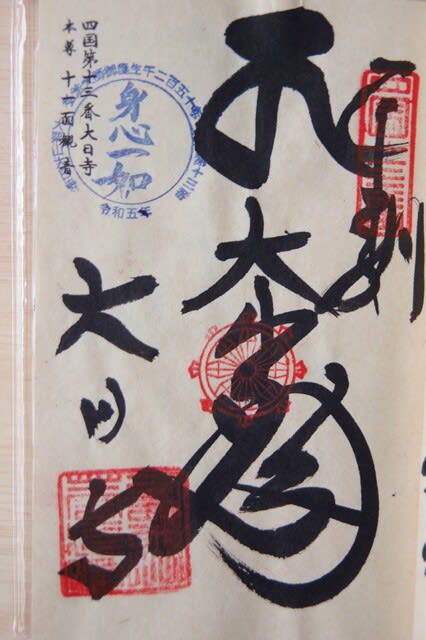
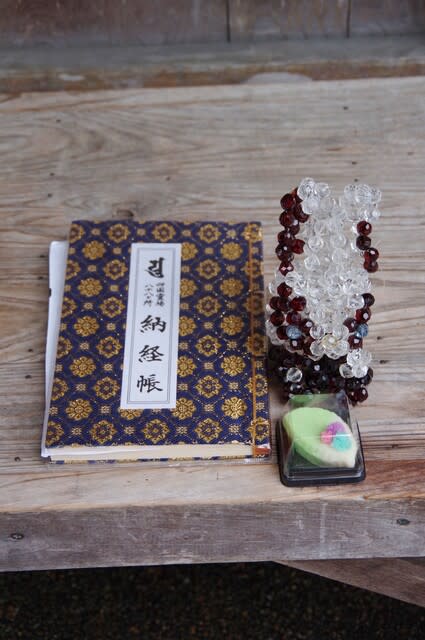

























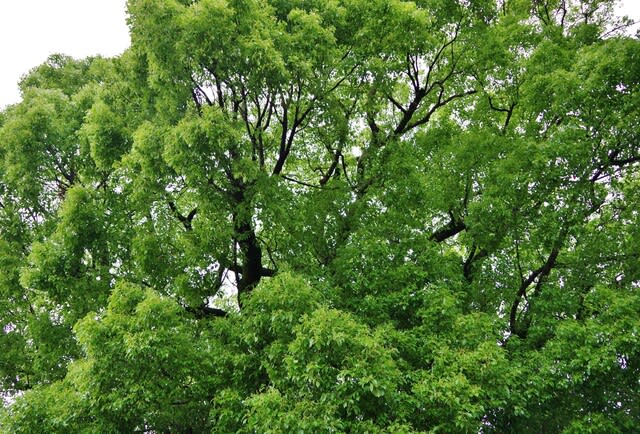


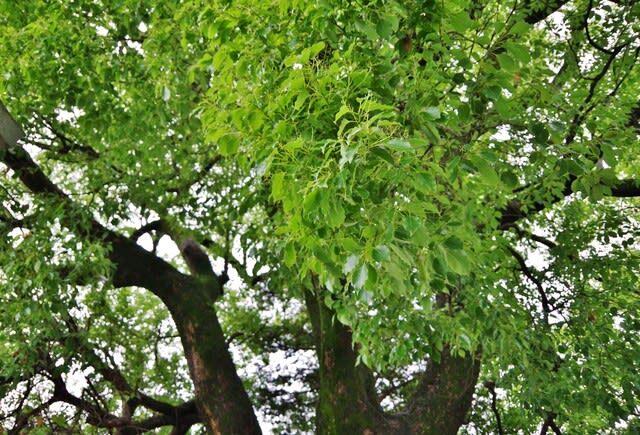
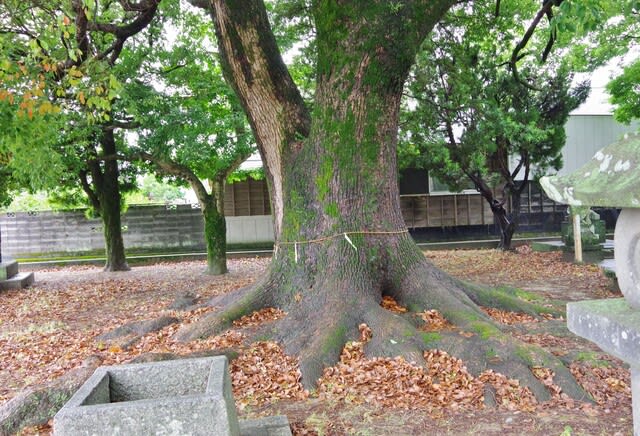


















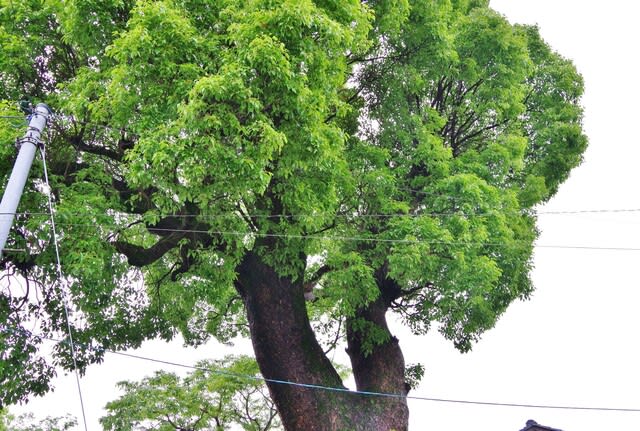






























































 雨が強く成っていましたので、取材は終わりにして、道の駅いたのへ戻りました
雨が強く成っていましたので、取材は終わりにして、道の駅いたのへ戻りました




