 クミアイ情宣シリーズ。同時に「こんなものいらない」シリーズでもある。「学校事務」誌に原稿依頼があったときに、迷わずこのネタを送った。要するに自信作(笑)。発行は2002年10月1日でした。
クミアイ情宣シリーズ。同時に「こんなものいらない」シリーズでもある。「学校事務」誌に原稿依頼があったときに、迷わずこのネタを送った。要するに自信作(笑)。発行は2002年10月1日でした。
こんなものいらない~業界隠語篇
①と書いて“いちまる”。(1)と書いて“いちかっこ”。こう読むのが山形県だけということはみなさんもうご存知のことだろう。スタンダードはもちろんそれぞれ“まるいち”“かっこいち”。山形から出て初めてこの事実に驚愕する県人は多く、他県から山形県の教員になった人はもっと驚いている。このめずらしい『読み方が違う』という方言の発祥には諸説あるが、山形師範学校の指導による、との説が有力。卒業生たちが教師として県内に散らばり、児童生徒に伝えていった結果だと。存続云々でもめていることなど信じられない山形大学教育学部の影響力。
この読み方がいけない、と言っているわけではない。読み方が他とは違う、とわたしたちが意識できているのかどうか。今回はそんなお話。
 その業界でしか通じない(あるいは通じないことになっている)ことばが存在する。隠語、とか符丁とよばれるもの。
その業界でしか通じない(あるいは通じないことになっている)ことばが存在する。隠語、とか符丁とよばれるもの。
芸能界を例にとると分かりやすいかもしれない。テレビの黎明期、もとから隠語を数多く使うことで知られていたジャズ・ミュージシャンや映画人が大挙してテレビ局に出入りするようになり、おかげで芸能界は隠語のるつぼとなった。典型的なのがことばのひっくり返し。食事のことをシーメ、女性のことをナオン、などと呼んでいた。「昨日はナオンとシーメしちゃってさー」こんな感じ。
※シーメ。
非成長産業として成熟期に入ったテレビ業界で、こんな隠語を使う人間はすでに軽蔑の対象になっている。業界人ぶりたいヤツ、というわけだ。でも、かの有名な24時間あいさつが「おはようございまーす」なのは健在らしい。
※あと目立つのが短縮系。合唱コンクールが【合コン】になるのは楽しそうでいいが、前任校で全校マラソンを【全マラ】と略していたのにはまいった。体育主任に頼むからやめてくれ、と懇願したっけ。彼女は意味がわかっていなかったが。
意地悪な見方をするようだが、ここから透けて見えるのは、隠語を使うことでお互いの仲間意識を確認しあいたい欲求。そしてそこから派生したエリート意識、あるいはコンプレックスだ。
学校はどうだろう。
男女別(児童生徒・職員)に名簿をつくったり、お互いを「~先生」と呼び合うといった特殊な村社会を形成し、徹底した前例踏襲主義に固執するこの業界に隠語が存在しないわけが……あ、ありました。しかもウチの学校に。
 曰く『立哨指導』。
曰く『立哨指導』。
どうして単純に交通安全指導じゃだめなのか。あいさつも含めた生徒指導もあるからってか?
そもそも立哨って何だろう。ウチにある古い広辞苑には載ってないし(これはさすがに意外だった)、ATOKでは変換さえしない。インターネットでやっと見つける。
【立哨】……歩哨などが、その位置を動かずに警戒にあたること。
ちなみに
【歩哨】……軍隊で、警戒、監視などの任務につく兵士。哨兵。sentinel。
どうやら教職員は日々命がけの業務についているようだ。
誤解されると困るのだが、前に書いたように、あからさまな軍隊用語だからおかしいと言っているのではない。ほとんど死語となっていることばを、去年もそうだったから、という理由だけで使い続けた結果、すでに一般には通じない隠語化してしまっているじゃないか、と感じるわけ。そのことに、意識的でいるかどうかなのだ。
もっとも、こんな隠語系をどこよりも使っているのは実は組合の方かもしれない。新採、と無意識に口にするけれど、こんなことばも実は一般には存在しないし、36(サブロク)協定だの名目賃金だのは組合の役員だって(実は私も含めて)よくわからないかも。だいたいこの間まで婦人部なる部があったのはどこの組合だ(笑)。
隠語を使うことで、一種のコミュニティをつくり、敷居を高くして外部の人間を排除している場面はないだろうか。みなさんの学校にそんな言葉はないか、一度さがしてみてください。
※置賜の事例はすごい。指導部の名前を、学習指導部が「きらきら学び合い部」生徒指導部が「生き生きスマイル部」保体部が「のびのび元気部」と変更された学校があるのだ。職員会議では「では次にきらきら学び合い部から提案します」とかやってるんだろうか。思い切ったなあ。
 ダン・ブラウン原作 ロン・ハワード監督 トム・ハンクス主演
ダン・ブラウン原作 ロン・ハワード監督 トム・ハンクス主演









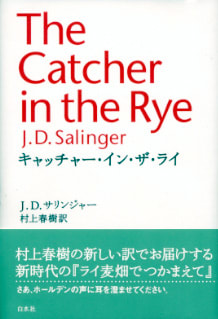 「だだっぴろいライ麦畑みたいなところで、小さな子どもたちがいっぱい集まって何かのゲームをしているところを、僕はいつも思い浮かべちまうんだ。何千人もの子どもたちがいるんだけど、ほかには誰もいない。つまり
「だだっぴろいライ麦畑みたいなところで、小さな子どもたちがいっぱい集まって何かのゲームをしているところを、僕はいつも思い浮かべちまうんだ。何千人もの子どもたちがいるんだけど、ほかには誰もいない。つまり
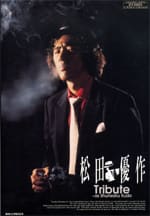 松田優作 成田三樹夫主演 村川透他演出
松田優作 成田三樹夫主演 村川透他演出 クミアイ情宣シリーズ。同時に「
クミアイ情宣シリーズ。同時に「 その業界でしか通じない(あるいは通じないことになっている)ことばが存在する。
その業界でしか通じない(あるいは通じないことになっている)ことばが存在する。 曰く『
曰く『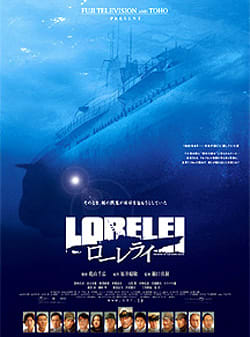 一本の映画を観たあとに、その映画について語り合うシチュエーションといえば、
一本の映画を観たあとに、その映画について語り合うシチュエーションといえば、 卑怯な言い方になるけれど、これはどちらも当たっているんだと思う。「ガメラ」などの特撮で着々と実績を積み上げてきた監督デビューの
卑怯な言い方になるけれど、これはどちらも当たっているんだと思う。「ガメラ」などの特撮で着々と実績を積み上げてきた監督デビューの 十数年前、たまやカブキ・ロックス、Beginなどを輩出した(最高だったのは
十数年前、たまやカブキ・ロックス、Beginなどを輩出した(最高だったのは ホリ・ヒロシ
ホリ・ヒロシ 憂鬱な夜を吹き飛ばすための一冊。しかしこの本はちょっと反則。ディーヴァーといえば映画的手法を駆使して(まあ、スティーブン・キング以降はみんなそうなんだけど)読者を一瞬たりとも飽きさせない剛腕作家。あまりに書き直すものだから出版社に嫌われている粘着質な男でもある。「魔術師」は、代表作「ボーン・コレクター」(文春文庫)に始まる四肢が麻痺した究極の安楽椅子探偵
憂鬱な夜を吹き飛ばすための一冊。しかしこの本はちょっと反則。ディーヴァーといえば映画的手法を駆使して(まあ、スティーブン・キング以降はみんなそうなんだけど)読者を一瞬たりとも飽きさせない剛腕作家。あまりに書き直すものだから出版社に嫌われている粘着質な男でもある。「魔術師」は、代表作「ボーン・コレクター」(文春文庫)に始まる四肢が麻痺した究極の安楽椅子探偵 「『ゴールデン・スランバー』をさ、さっきおまえが寝てる間、ずっと口ずさんでいたんだ」
「『ゴールデン・スランバー』をさ、さっきおまえが寝てる間、ずっと口ずさんでいたんだ」 仙台で首相の凱旋パレードが行われているちょうどそのとき、旧友に主人公は呼び出される。冒頭のやりとりがあった直後、旧友は「お前は陥れられている。逃げろ、
仙台で首相の凱旋パレードが行われているちょうどそのとき、旧友に主人公は呼び出される。冒頭のやりとりがあった直後、旧友は「お前は陥れられている。逃げろ、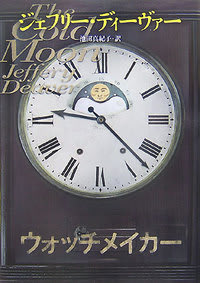 現場に時計を残してゆく殺人鬼ウォッチメイカー。目撃証言から犯人が購入した時計は10個と判明。
現場に時計を残してゆく殺人鬼ウォッチメイカー。目撃証言から犯人が購入した時計は10個と判明。 オカルトではなく、持ち前のセンスと訓練の成果で、容疑者の「しぐさ」や「口調」から嘘を見抜いてしまうキャサリン・ダンスという捜査官が初登場。仕事に関してプロフェッショナルな人間しか認めないライムをも驚嘆させる。筆跡鑑定人パーカー・キンケイドが主人公の
オカルトではなく、持ち前のセンスと訓練の成果で、容疑者の「しぐさ」や「口調」から嘘を見抜いてしまうキャサリン・ダンスという捜査官が初登場。仕事に関してプロフェッショナルな人間しか認めないライムをも驚嘆させる。筆跡鑑定人パーカー・キンケイドが主人公の
 同僚ネタを思い出したので、
同僚ネタを思い出したので、




