これほどまでに日常と一線を引く所作はない。
そんな思いを抱いたのが、10年近く前に、煎茶稽古をはじめてまだ間もない頃、文人会一茶庵で「煎茶入門」という講座に参加したとき。その記憶が鮮明に残っている。
おこがましいが、ブログ記事を書く上で常に大切にしていることがあった。それは、取材テーマにしている日本の伝統文化を “日頃の暮らしに反映させる” ことである。それでこそ、いまやっていることの意義や意味があると思っていたからである。
ところが、この煎茶入門講座3回シリーズで学んだことは煎茶道への一歩ではなかった。「雅」でも「俗」でもない"離俗の美"を求める「文人煎茶」へのものだった。実生活の生活感から離れ、和漢の古典文学をもとにイメージを膨らませる和漢混淆の美、つまり「離俗の美」を追求するものであることを知らされた。
3回講座の第一回目は十数名の方が参集、一茶庵宗家の佃一輝宗匠のご指導を受けた。一回目は「自分だけの茶・・・絶妙な一滴」というテーマだった。そして玉露を自分だけで愉しむ、というのがサブテーマだったことを記憶している。
椅子に座り目の前には、玉露を入れる小品急須である茶銚、煎茶の茶碗である茗碗(めいわん)。それから茶合、托子、水柱、巾承などが置かれていた。
小さな急須に惜しげもなく玉露の茶葉を入れる。その急須に少量の湯を注ぐ。急須を茗碗に傾け搾り出すかのように一滴が出てくるのを待つ。茗碗にたれた一滴の茶の匂いを愉しみ、そして舐める。
この所作を6煎続ける。毎回、急須に注ぐ少量の湯は同じところに注ぐ。そしてまた茗碗に垂らす。1煎ごとそれぞれの味の変化を五感で愉しむ、というものである。
むかしの文人はこのようなことをしながら書斎で愉しんでいたようである。自娯の心が煎茶を絶妙なものにするといわれている。この時間が、まさに離俗ということになる。
誰のためにするものではない、ただただ自身の喜び愉しみの世界を味わうためのものである。ちなみに6煎のあとに湯を注ぎ、茗碗一杯の茶をのむなら「俗」になってしまう。さらに、最高の茶葉で締めにお茶づけでもしようものなら・・・。文人煎茶では、絶対にありえない、という。
そして次回、最終回でどんな一滴が愉しめるのだろうか。











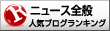
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます