(昨日の続き)
スマホに代表されるIT機器はそれまであった現実世界の一部を取り込んでしまった。
手紙を出さなくても、メールがある。
ゲームセンターであれば、わざわざ出向く必要は無い。
分厚い漫画本をわざわざ持って歩く必要は無い。
写真も写真屋にいかなくていい。
どれがどうなっているかということをいちいち挙げることは難しいが、いずれにせよ、それまであった、人の手による作業というものがずいぶん奪われてしまった。かつて、学会用のスライドを写真屋に走って取りにいったことを知っている人はどれほどいるだろうか。
こういった現象は、今や医学の分野にも確実に入り込んできている。
ためしに、「医療情報 スマホ」といれてググってみたら、ヒット数のあまりの多さ(146万件)におどろいた。
トップに出てきた”医師・医療事業者向けスマートフォンアプリ[Android用アプリ] ”というのを開いたら、ずいぶんといろいろなものがあって驚いた。
昨日も、「あと、10年後には」などと言っていたけれど、実際あと10年経ったら、症状、所見を音声入力して、それに応じた診断が出てくるようになるのではないか。
SFの世界では医療ロボットは当たり前のように活躍している。
というようなわけで、医療ロボットとまでは行かなくても、実際すでにそれに近いものはすでにありそうだ。
日本ではまだ、医者による診療が唯一だが、医療保険に入ることができず、自分のことは自分でしなくてはいけないような人が多い国では、そういった自己責任で診断、治療を行うことになっていくように思う。そこに、スマホが役立つというか、医者の牙城に入ってくることになる。
薬はネットで買えるようになるし、診断、治療に関する情報はすでに溢れている。
情報弱者を別にすると、一般の人によるスマホ医療はこの先どんどん発展していくに違いない。
TPPで保険が自由化され、医療も自由化されていくと、日本の医者はこれまで以上に生涯学習を重ねていかなくてはいけない。昨今の医学生は、タブレット端末に膨大な医学情報を詰め込んでいるそうだ。以前いたレジデントの先生も、疑問がわいたら5秒後にはネットで検索していた。
医者自身ももちろんスマホ無くしては医療をやっていけなくなりつつある。
医者として生き残っていくのは、人間としての五感を駆使して、能力のすべてを患者さんに与えることのできるものしかいないだろう。
病理医の場合も同様で、マクロの所見に始まり、顕微鏡所見まで、機械に無い人間としての能力を発揮して病変を分析、理解した上で、普遍的な診断文を著すことができなければ、機械に負けてしまうかも知れない。
いざ、自分が関係していることが結構な危機に瀕しているということがわかると、結構焦ってしまう。

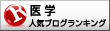
スマホに代表されるIT機器はそれまであった現実世界の一部を取り込んでしまった。
手紙を出さなくても、メールがある。
ゲームセンターであれば、わざわざ出向く必要は無い。
分厚い漫画本をわざわざ持って歩く必要は無い。
写真も写真屋にいかなくていい。
どれがどうなっているかということをいちいち挙げることは難しいが、いずれにせよ、それまであった、人の手による作業というものがずいぶん奪われてしまった。かつて、学会用のスライドを写真屋に走って取りにいったことを知っている人はどれほどいるだろうか。
こういった現象は、今や医学の分野にも確実に入り込んできている。
ためしに、「医療情報 スマホ」といれてググってみたら、ヒット数のあまりの多さ(146万件)におどろいた。
トップに出てきた”医師・医療事業者向けスマートフォンアプリ[Android用アプリ] ”というのを開いたら、ずいぶんといろいろなものがあって驚いた。
昨日も、「あと、10年後には」などと言っていたけれど、実際あと10年経ったら、症状、所見を音声入力して、それに応じた診断が出てくるようになるのではないか。
SFの世界では医療ロボットは当たり前のように活躍している。
というようなわけで、医療ロボットとまでは行かなくても、実際すでにそれに近いものはすでにありそうだ。
日本ではまだ、医者による診療が唯一だが、医療保険に入ることができず、自分のことは自分でしなくてはいけないような人が多い国では、そういった自己責任で診断、治療を行うことになっていくように思う。そこに、スマホが役立つというか、医者の牙城に入ってくることになる。
薬はネットで買えるようになるし、診断、治療に関する情報はすでに溢れている。
情報弱者を別にすると、一般の人によるスマホ医療はこの先どんどん発展していくに違いない。
TPPで保険が自由化され、医療も自由化されていくと、日本の医者はこれまで以上に生涯学習を重ねていかなくてはいけない。昨今の医学生は、タブレット端末に膨大な医学情報を詰め込んでいるそうだ。以前いたレジデントの先生も、疑問がわいたら5秒後にはネットで検索していた。
医者自身ももちろんスマホ無くしては医療をやっていけなくなりつつある。
医者として生き残っていくのは、人間としての五感を駆使して、能力のすべてを患者さんに与えることのできるものしかいないだろう。
病理医の場合も同様で、マクロの所見に始まり、顕微鏡所見まで、機械に無い人間としての能力を発揮して病変を分析、理解した上で、普遍的な診断文を著すことができなければ、機械に負けてしまうかも知れない。
いざ、自分が関係していることが結構な危機に瀕しているということがわかると、結構焦ってしまう。























