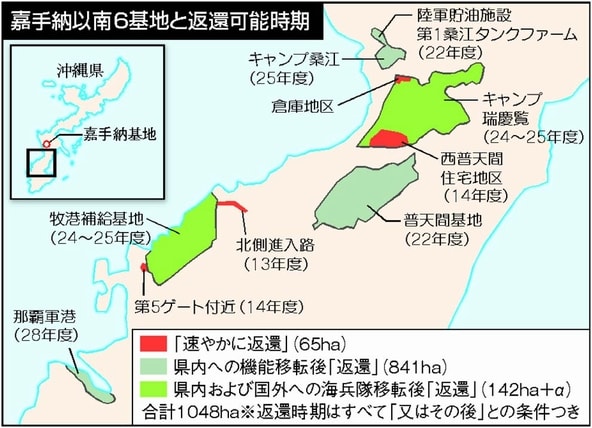解雇の自由化① 財界念願のターゲット
牧野富夫日大名誉教授に聞く
政府が開催する各種会議で「解雇の自由化」にむけた議論が活発化しています。その危険性について、牧野富夫(まきの・とみお)日本大学名誉教授に聞きました。
(聞き手・柳沢哲哉)
安倍晋三首相が議長を務める政府の産業競争力会議で、民間議員が「金銭による解雇ルールづくり」を提言し、「解雇を原則自由化」とするよう法「改正」を求めました。雇用破壊に拍車をかける危険な議論です。
雇用の流動化
これまで労働分野では「規制緩和」が繰り返されてきました。「経済の急速なグローバル化」のもとで財界・政府は、日本企業・日本経済の「国際競争力の強化」が喫緊の課題だとして、1990年代の半ばから、新自由主義に立つ「構造改革」を提起し強行するようになりました。その目指すところは、企業・産業の「停滞・衰退分野」を切り捨て、「成長分野」
を育成・強化する、というものです。これが市場原理の徹底によるコストダウン・高効率・労働者分断によって追求されるようになりました。
この「構造改革」の不可欠な一環として、「雇用の流動化・多様化」をベースとする財界の“新雇用戦略”(日経連「新時代の日本的経営」)が提起されました。これは「終身雇用」慣行を通じて特定企業で「雇用を守る」という旧来の考え方を逆転させ、「雇用の流動化・多様化を通じて雇用を守る」という考え方に立っています。
この「雇用の流動化・多様化」を推進するために政府は、財界の要請に沿って90年代の後半から一連の労働分野の「規制緩和」を加速させたのです。
今回提起された「解雇の自由化」は「雇用の流動化・多様化」にとって最大のポイントであり、財界が以前から虎視眈々(たんたん)と狙っていたターゲットです。財界の雇用戦略の焦点は、正規雇用労働者の「雇用の多様化」、とくに「解雇自由の実現」にシフトしています。

職場に向かう人たち=東京都内
的外れの議論
規制緩和推進派は、「解雇規制が正社員などの雇用抑制を招いている」と主張します。しかし、これは現実の雇用情勢にてらして的外れの議論です。労働契約法16条が解雇に「客観的に合理的な理由」を求め、具体的には「整理解雇の4要件」が想定されています。このような解雇権乱用の防止法理が確立したのは古く、70年代半ばでした。
最高裁判例にもとつく解雇権乱用防止法理の確立後、90年代半ばまで約20年間も経過し、その間、失業率は2%台と低位であったというのが事実です。したがって、90年代後半以降の雇用情勢の急激な悪化の要因は、「解雇規制法理」とは別の、「構造改革」下の企業のリストラや賃金抑制策などに求めざるをえません。
貧困の拡大に
規制緩和推進派はまた、「正規雇用者の雇用が流動化すれば、待機失業者も減り、若年労働者の雇用も増大すると同時に、正規雇用者と非正規雇用者の格差を埋めることにもなる」と主張しています。
ですが、これも賃金や労働時間といった雇用の質を棚上げした議論で、事実に反しています。そのような方策でもたらされるであろう「格差縮小」は、労働条件を低い方にあわせる「低位平準化」による貧困の拡大とならざるをえません。
求めるべきは、そのような方策ではなく、日本の労働時間や有給休暇をドイツやフランス並みに改め、サービス残業を根絶することです。そうすれば、「待機失業者」だけでなく約300万人いる失業者すべてに雇用のチャンスを提供できるでしょう。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年4月5日付掲載
偽物の「雇用の機会拡大」「格差縮小」による「解雇規制の撤廃」。正規雇用者の解雇の規制が取り払われると、非正規雇用者や失業者の身分も不安定になります。
低い方に、不安定な方に雇用の条件が合わせられてしまうのです。
牧野富夫日大名誉教授に聞く
政府が開催する各種会議で「解雇の自由化」にむけた議論が活発化しています。その危険性について、牧野富夫(まきの・とみお)日本大学名誉教授に聞きました。
(聞き手・柳沢哲哉)
安倍晋三首相が議長を務める政府の産業競争力会議で、民間議員が「金銭による解雇ルールづくり」を提言し、「解雇を原則自由化」とするよう法「改正」を求めました。雇用破壊に拍車をかける危険な議論です。
雇用の流動化
これまで労働分野では「規制緩和」が繰り返されてきました。「経済の急速なグローバル化」のもとで財界・政府は、日本企業・日本経済の「国際競争力の強化」が喫緊の課題だとして、1990年代の半ばから、新自由主義に立つ「構造改革」を提起し強行するようになりました。その目指すところは、企業・産業の「停滞・衰退分野」を切り捨て、「成長分野」
を育成・強化する、というものです。これが市場原理の徹底によるコストダウン・高効率・労働者分断によって追求されるようになりました。
この「構造改革」の不可欠な一環として、「雇用の流動化・多様化」をベースとする財界の“新雇用戦略”(日経連「新時代の日本的経営」)が提起されました。これは「終身雇用」慣行を通じて特定企業で「雇用を守る」という旧来の考え方を逆転させ、「雇用の流動化・多様化を通じて雇用を守る」という考え方に立っています。
この「雇用の流動化・多様化」を推進するために政府は、財界の要請に沿って90年代の後半から一連の労働分野の「規制緩和」を加速させたのです。
今回提起された「解雇の自由化」は「雇用の流動化・多様化」にとって最大のポイントであり、財界が以前から虎視眈々(たんたん)と狙っていたターゲットです。財界の雇用戦略の焦点は、正規雇用労働者の「雇用の多様化」、とくに「解雇自由の実現」にシフトしています。

職場に向かう人たち=東京都内
的外れの議論
規制緩和推進派は、「解雇規制が正社員などの雇用抑制を招いている」と主張します。しかし、これは現実の雇用情勢にてらして的外れの議論です。労働契約法16条が解雇に「客観的に合理的な理由」を求め、具体的には「整理解雇の4要件」が想定されています。このような解雇権乱用の防止法理が確立したのは古く、70年代半ばでした。
最高裁判例にもとつく解雇権乱用防止法理の確立後、90年代半ばまで約20年間も経過し、その間、失業率は2%台と低位であったというのが事実です。したがって、90年代後半以降の雇用情勢の急激な悪化の要因は、「解雇規制法理」とは別の、「構造改革」下の企業のリストラや賃金抑制策などに求めざるをえません。
貧困の拡大に
規制緩和推進派はまた、「正規雇用者の雇用が流動化すれば、待機失業者も減り、若年労働者の雇用も増大すると同時に、正規雇用者と非正規雇用者の格差を埋めることにもなる」と主張しています。
ですが、これも賃金や労働時間といった雇用の質を棚上げした議論で、事実に反しています。そのような方策でもたらされるであろう「格差縮小」は、労働条件を低い方にあわせる「低位平準化」による貧困の拡大とならざるをえません。
求めるべきは、そのような方策ではなく、日本の労働時間や有給休暇をドイツやフランス並みに改め、サービス残業を根絶することです。そうすれば、「待機失業者」だけでなく約300万人いる失業者すべてに雇用のチャンスを提供できるでしょう。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年4月5日付掲載
偽物の「雇用の機会拡大」「格差縮小」による「解雇規制の撤廃」。正規雇用者の解雇の規制が取り払われると、非正規雇用者や失業者の身分も不安定になります。
低い方に、不安定な方に雇用の条件が合わせられてしまうのです。