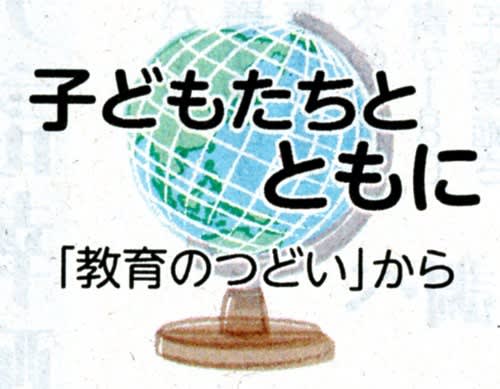AIと科学的社会主義④ 分業固定の条件崩す
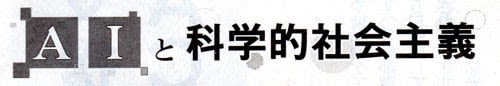
経済研究者 友寄英隆さん
人工知能(AI)の進化は、人間の労働のあり方や、肉体労働と精神労働の分離・分業と格差の固定化、階級支配との関連の問題についても、新しい視点をもたらす可能性があります。
マルクスが『資本論』のなかで強調しているように、人間の活動はほんらい、どんな肉体的活動であっても精神的活動と結びついており、それが他の動物の活動と根本的に違う特徴です。ところが人類の歴史においては、私有財産の発生と同時に、肉体労動と精神労働の分離が始まりました。すでに古代社会から、支配階級は精神労働の分野を独占し、それを搾取制度の手段としてきました。
資本主義的搾取制度は資本による生産手段の私的所有を前提としています。資本は、生産手段の資本所有を根本的条件としつつ、労働の性格という面からみると、肉体労働と精神労働の職業的分業を固定化し、それを階級的支配のために利用してきました。

マンハッタンにあるグーグルビル(ロイター)
精神労働を代替
マルクスは『ゴータ綱領批判』のなかで「共産主義社会のより高度の段階で、すなわち個人が分業に奴隷的に従属することがなくなり、それとともに精神労働と肉体労働との対立がなくなったのち…」と述べています。AIは、未来社会のより近い段階で、「精神労働と肉体労働との対立」をなくすための技術的な条件を準備する可能性があります。
生成AIの開発は、人間の精神的労働がコンピューターによってかなりの程度まで代替されうることを示しています。これは、人類史において搾取制度の手段ともなってきた肉体的労働と精神的労働の分離、職業的固定化の条件が崩れつつあることも意味します。
ところが皮肉なことに、現代の資本主義のもとでは異常な報酬格差が拡大しています。たとえば、次のような報道があります。
「NECはAIなどの分野で優秀な新卒者を対象に年収1000万円以上を提示。富士通は最高で年収3500万円を提示できるとされるデジタル人材向けの新制度を導入」。「海外では、最上位クラスだと同120万ドルといった高い報酬で処遇されている例もある」(米ブルームバーグ通信、22年3月2日付)120万ドルといえば、1億8000万円(1ドル=150円で換算)です。日本では、大企業がIT人材の大卒者を高給で迎え入れているために、理工系大学院への進学者が減少し、独創的な学術研究の弱体化が懸念されています。ある意味では逆説的な現象ですが、利潤を追求する資本主義的な搾取制度の本質的な矛盾でもあります。
脳には及ばない
エンゲルスは『自然弁証法』のなかの手稿「猿が人間になるにあたっての労働の役割」で、労働とともに言語が生まれ、この二つが最も本質的な推進力となって人間の脳が形成されてきたと述べています。ギリシャ語の「言葉(ロゴス)」が同時に「理性」を意味するように、人間の精神的活動は言語を使ってなされるからです。
生成AIとは、人間の求めに応じて文章や画像を作成してくれるAIのことです。生成AIのような大規模言語モデルの開発は、人間の精神的活動と深くかかわっています。
とはいえ、生成AIが人間の言語活動を模倣できるようになったとしても、人間の精神的活動を代替できるようになったとはいえません。現在のAIにはさまざまなリスクや欠陥があり、人間の脳にはまだ遠くおよばない未完成の技術です。
モナリザを描いているレオナルド・ダビンチの手の動きは、言語によっては説明できません。生成AI(generative AI)は、創造AI(creative AI)ではないのです。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年9月20日付掲載
マルクスは『ゴータ綱領批判』のなかで「共産主義社会のより高度の段階で、すなわち個人が分業に奴隷的に従属することがなくなり、それとともに精神労働と肉体労働との対立がなくなったのち…」と述べています。AIは、未来社会のより近い段階で、「精神労働と肉体労働との対立」をなくすための技術的な条件を準備する可能性が。
生成AIが人間の言語活動を模倣できるようになったとしても、人間の精神的活動を代替できるようになったとはいえません。現在のAIにはさまざまなリスクや欠陥があり、人間の脳にはまだ遠くおよばない未完成の技術。
モナリザを描いているレオナルド・ダビンチの手の動きは、言語によっては説明できません。生成AI(generative AI)は、創造AI(creative AI)ではない。
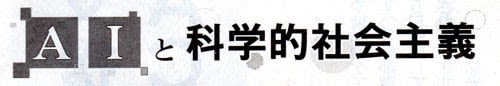
経済研究者 友寄英隆さん
人工知能(AI)の進化は、人間の労働のあり方や、肉体労働と精神労働の分離・分業と格差の固定化、階級支配との関連の問題についても、新しい視点をもたらす可能性があります。
マルクスが『資本論』のなかで強調しているように、人間の活動はほんらい、どんな肉体的活動であっても精神的活動と結びついており、それが他の動物の活動と根本的に違う特徴です。ところが人類の歴史においては、私有財産の発生と同時に、肉体労動と精神労働の分離が始まりました。すでに古代社会から、支配階級は精神労働の分野を独占し、それを搾取制度の手段としてきました。
資本主義的搾取制度は資本による生産手段の私的所有を前提としています。資本は、生産手段の資本所有を根本的条件としつつ、労働の性格という面からみると、肉体労働と精神労働の職業的分業を固定化し、それを階級的支配のために利用してきました。

マンハッタンにあるグーグルビル(ロイター)
精神労働を代替
マルクスは『ゴータ綱領批判』のなかで「共産主義社会のより高度の段階で、すなわち個人が分業に奴隷的に従属することがなくなり、それとともに精神労働と肉体労働との対立がなくなったのち…」と述べています。AIは、未来社会のより近い段階で、「精神労働と肉体労働との対立」をなくすための技術的な条件を準備する可能性があります。
生成AIの開発は、人間の精神的労働がコンピューターによってかなりの程度まで代替されうることを示しています。これは、人類史において搾取制度の手段ともなってきた肉体的労働と精神的労働の分離、職業的固定化の条件が崩れつつあることも意味します。
ところが皮肉なことに、現代の資本主義のもとでは異常な報酬格差が拡大しています。たとえば、次のような報道があります。
「NECはAIなどの分野で優秀な新卒者を対象に年収1000万円以上を提示。富士通は最高で年収3500万円を提示できるとされるデジタル人材向けの新制度を導入」。「海外では、最上位クラスだと同120万ドルといった高い報酬で処遇されている例もある」(米ブルームバーグ通信、22年3月2日付)120万ドルといえば、1億8000万円(1ドル=150円で換算)です。日本では、大企業がIT人材の大卒者を高給で迎え入れているために、理工系大学院への進学者が減少し、独創的な学術研究の弱体化が懸念されています。ある意味では逆説的な現象ですが、利潤を追求する資本主義的な搾取制度の本質的な矛盾でもあります。
脳には及ばない
エンゲルスは『自然弁証法』のなかの手稿「猿が人間になるにあたっての労働の役割」で、労働とともに言語が生まれ、この二つが最も本質的な推進力となって人間の脳が形成されてきたと述べています。ギリシャ語の「言葉(ロゴス)」が同時に「理性」を意味するように、人間の精神的活動は言語を使ってなされるからです。
生成AIとは、人間の求めに応じて文章や画像を作成してくれるAIのことです。生成AIのような大規模言語モデルの開発は、人間の精神的活動と深くかかわっています。
とはいえ、生成AIが人間の言語活動を模倣できるようになったとしても、人間の精神的活動を代替できるようになったとはいえません。現在のAIにはさまざまなリスクや欠陥があり、人間の脳にはまだ遠くおよばない未完成の技術です。
モナリザを描いているレオナルド・ダビンチの手の動きは、言語によっては説明できません。生成AI(generative AI)は、創造AI(creative AI)ではないのです。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年9月20日付掲載
マルクスは『ゴータ綱領批判』のなかで「共産主義社会のより高度の段階で、すなわち個人が分業に奴隷的に従属することがなくなり、それとともに精神労働と肉体労働との対立がなくなったのち…」と述べています。AIは、未来社会のより近い段階で、「精神労働と肉体労働との対立」をなくすための技術的な条件を準備する可能性が。
生成AIが人間の言語活動を模倣できるようになったとしても、人間の精神的活動を代替できるようになったとはいえません。現在のAIにはさまざまなリスクや欠陥があり、人間の脳にはまだ遠くおよばない未完成の技術。
モナリザを描いているレオナルド・ダビンチの手の動きは、言語によっては説明できません。生成AI(generative AI)は、創造AI(creative AI)ではない。