浅田次郎さんの小説。初めて読んだ。
きっかけは、BSNHKドラマ「一路」にはまったことから。
出演者が知らない役者さんばかりだから、調べたら2016年5月に放映されていたのね。
原作者が浅田次郎さんと知る。
いやあこれが胸ワクワクもの、ごめん浅田さん、食わず嫌いでした。
というのもずっとずっと以前、エッセイ『ま、いっか。』を読んで、「いやだわ、これは、ま、いっかじゃない」と
浅田さん嫌いになったのよ。いやいや浅はかでした、申し訳ありません、これからも読ませていただきますと。
原作はドラマ以上、はるかに面白い。どんどんと読み進めることができました。はい。
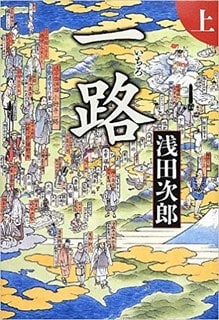
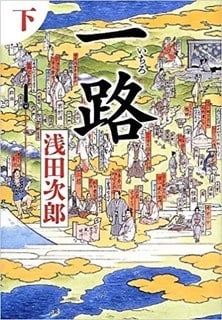
父の不慮の死により家督を相続、交代寄合蒔坂家の御供頭として江戸への参勤を差配することになった小野寺一路、十九歳。
二百年以上前に記された家伝の「行軍録」を唯一の手がかりに、古式に則った行列を仕立て、いざ江戸見参の道中へ。
お役目を果たせなければ家禄召し上げという身で、一所懸命におのれの本分を全うしようとする一路。
その前途に、真冬の中山道の難所が立ち塞がる。さらに行列の内部では、ひそかに御家乗っ取りの企みが・・・
石高はそれ以下の旗本なのに、そんじょそこらの大名よりエライ。
大名と同じように、領地を持って陣屋を構え、参勤交代も義務付けられていて、これがたいへんなのよ。
物語は、若干19歳の御供頭 小野寺一路が、
「参勤交代は行軍だ」とツアコンよろしく真冬の中山道を江戸へ江戸へと行列を指揮していく。
と主人公は一路なのだろうけれど、私は西美濃田名部郡を領分とする7500石の旗本、御殿様の
蒔坂左京大夫(まいさか さきょうのだいぶ)様がたいそう好きになって。魅力的だわ。
芝居小屋の裏木戸で贔屓の出待ちをし、町方に捕まったという御殿様。
松の廊下で飛び六法を踏み、「当分乃間登城差控」となった馬鹿殿様。
三百諸侯中、瓦版の種になる御殿様はほかにおらぬし、そのうえ版元に文句もつけぬというのだから、
正真正銘のうつけにちがいなかった。
てな具合で、世間も家来衆もうつけか?それとも?と戸惑う始末。
他にも参勤交代の行列で歩んでいる中、そうもよおしてきて我慢しきれず、
なにしろご気性真っ直ぐなお方なれば、出すものもまっすぐ一直線。
道中の御殿様のトイレ事情は大変で、家来に穴を掘らせ周囲に幕を張り巡らせ、おまけに袴その他の着物の
脱ぎ着も家来の手を煩わせる。だから本陣できちんと済ませるのに、その時は急なもよおしだったのね。
それではあまりに気の毒とばかりに、御殿様は得意の早足を武器に駆け出すのよ。
行列をはるか後方に置き去りにして、ようやくどこかの役人小屋にたどり着いてやれ嬉しやと厠へ。
あちゃあ、そこは悲惨な状況、説明するもあまりの状況。ぼっとん便所で育った私には想像できる。
おまけに、寒さで何は凍りついて盛り上がっているんですって。
読みながらもうおかしくておかしくて。
こんな具合に全編、滑稽味おかし味にあふれていて。
そして、ときにほろっときたり泣けて来たり、そうよねそうそうと共感したり。
その心の機微が、映像となって目の前に浮かんでくるんだから浅田さんの筆力って凄いんだなと。
登場人物皆が「○○だから、かくあらねばならぬ」という縛りにとらわれしゃちこばった中に、
ん?待てよと己を振り返ったり、あいつはああ装っているけれどひょっとして?
なんて、実にひとりの人間の多面的な面を飄々と描いていて、浅田さん、参りましたと頭垂れるわけ。
たとえば、御殿様以外にも、
正義と忠義の狭間に揺れ続いてきた[伊東喜惣次]
おつむの足らない武辺者とされている[佐久間 勘十郎]
人間には隙がなくてはならぬ。謹厳居士の綽名など、決して褒められたものではないと考え直した[松平豊前守]
人はみな、貧富貴賤にかかわらず、つらい道中を行く旅人にござりますれば。
さだめという重き荷を負うた、おのおのが等しき旅人にござりますればー[乙姫様と鶴橋]
などなどが物語を彩る。
そして、ようよう御殿様の行列は、一路の死に物狂いの活躍もあって無事に江戸にたどり着く。
で、なぜか上様(将軍家茂ね)が一介の旗本の御殿様を呼びつけるの、そんなことってあるかしらなんてことはおいて。
御庭番から
「上様のご推察通り、馬鹿でもうつけでもござりませぬ。
蒔坂左京大夫は紛うかたなく、世に言う賢者名にたがいなしと拝察つかまつりました」と聞いていたからね。
そこで御殿様はありがたくも、
『一万石に加増のうえ、大名に列す。』
のお言葉をいただくわけよ。ははあーと、嬉しありがたしと頭畳にこすり付けて受け取ると思いきや。
今の7,500石のままでいいとお断りになる。なにゆえと迫る上様にそのわけを、
理屈で解き情で訴え領地領民を守る殿さまとしての覚悟で迫って。
上様に「僭越であった」と言わしめる。いやあ、お見事。
食わず嫌いはもったいない。「椿課長の七日間」を借りてきた、はたして。
こちらを参考までにどうぞ。 より興味が増します。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます