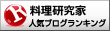京都の続きです。
細見美術館では、徳川家光の時の御水尾天皇行幸の様子を描いた屏風が素晴らしかったです。上の列が、堀川通を二条城に向かう天皇のご様子、下の列は御所に天皇をお迎えするために向かう、将軍と諸大名の様子が、沿道の観衆とともに描かれていました。
当時、秀忠の娘和子が中宮として入内し、徳川家は天皇の外戚として力を持ち、天皇の権力を抑えようと動いておりましたので、天皇と徳川家の関係は決して良好とは言えませんでした。
二条城を天皇をお迎えするために改修し、行幸は実現しました。
行幸は、天皇の外出のことです。行幸については、武家諸法度が制定されてからは、天皇が勝手に行うことはできませんでした。なんと1651年の後光明天皇による朝覲行幸以後、1863年の孝明天皇による上賀茂神社、下鴨神社行幸まで200年以上も行われなかったと後で調べてわかりました。
知らないことばかりで驚いています。
夜は三人で京都のおばん菜を堪能し、ゲストハウスに泊まりました。

一階がカフェになっていて、とてもリーズナブルな価格です。9割以上が外国人。長期滞在者ように、共有のリビングルームとキッチンがあります。一階のカフェは、ほとんどが相席のテーブルで、他のグループの人とも自然に会話ができます。個性的な人ばかりで楽しかったです。
泊まる部屋には、ベッドと寝具だけ備えてあり、テレビなどはありません。
〝テレビがないね〟
私が言うと、マダムKさんが
〝私が、テレビの代わりをするわよ、なんなら四角の枠を作ってくれたら中に入ってずっと喋るから、大丈夫〟
恐れ入りました。おっしゃる通り、会話は弾み、テレビなど全く必要はありませんでした。
実りある京都の小旅行。また行きたいです。