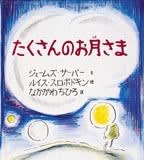かさどろぼう/シビル・ウエツタシンハ:作・絵 いのくま ようこ・訳/徳間書店/2007年初版
スリランカの島の小さな村が舞台です。
傘がないこの村では、バナナや、ヤムいもの はっぱを 傘の代わりにしていました。
この村のキリ・ママというおじさんが、うまれてはじめて町でかけました。 町でみかけたのは、色鮮やかな傘。なんて きれいで便利なものだろうと、さんざんまよったあげく一本の傘をかいました。
バスがむらについたとき、もうあたりは薄暗くなっています。キリ・ママはバス停そばのコーヒー屋で一息つきます。
キリ・ママは、町で見てきた珍しいもののあれこれを、はなしましたが、傘は塀の影にかくして、話さないように気をつけていました。
ところが帰ろうとすると傘がありませんでした。せっかく、みんなにみせびらかそうと思っていた素敵な傘がなくなっていたのです。
あきらめきれないキリ・ママは、なんども町に行って傘を買うようになりました。
けれども、傘はコーヒーを飲んでいる間に、いつもなくなってしまいます。
ここまでくると、どうもコーヒー屋の主人があやしいのですが、思わぬ展開をします。
町でもういちど傘を買ったキリ・ママは、傘の間に小さく切った紙切れをたたんで、傘の中につめこんでおきました。そして道に落ちている紙切れのあとを追っていくと、ふるくて大きな木の上に。ずらりと傘がぶらさがっていました。
木によじ登ったキリ・ママは、傘を回収しますが、一本だけは、どろぼうに、やるため残しておきました。
回収した傘で、店を開いたキリ・ママのところへは、村中の人が、どっとおしかけてきました。
キリ・ママは、きれいな傘の花がさくと「どろぼうが 傘をぬすんでくれてよかった。おかげで 傘の店ができたのだから、おれいを いいたいぐらいだよ」と感謝しますが、傘どろぼうは一体だれだったのでしょう。
何度も盗まれたら、怒り心頭になりそうですが、キリ・ママさん なんとも太っ腹です。それにしても店を開けるほど傘がありましたから、何回町へかよったのでしょうか?。
ゆったりした時間が流れている絵本でした。
キリ・ママがコーヒーで一休みするところがでてきますが、スリランカといえば紅茶ですから、コーヒーについて調べてみました。かってはコーヒー栽培が盛んだったようです。そして、いま幻とよばれるコーヒーの栽培に取り組まれているとありました。