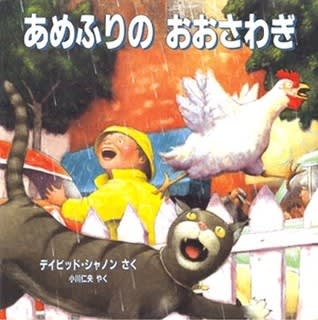
あめふりの おおさわぎ/デイビット・シャノン・作 小川仁央・訳/評論社/2002年
土曜日の朝、雨が降り出して、にわとりが鳴き出し、ねこがにわとりにフーッとほえかかる。
とうさんが犬をしかると、あかんぼうが目を覚まし、かあさんが、静かにしてと叫ぶと、騒ぎを聞きつけたおまわりさんがパトカーをとめて、「どうしましたか」と、戸をたたく。
パトカーの後ろに、タクシー、トラック、自動車販売のアイスクリームがならび、美容院、ペンキ屋さん、八百屋が大騒ぎ。
ところが突然雨が上がると、空には虹が。
するとみんなの機嫌がよくなって、「こんな いいてんきに、けんかは にあわないね」と、パン屋さん。美容院もアイスクリーム屋さんも、タクシーも商売繁盛です。
突然の夕立。こんなこともありそう。
今年は梅雨の雨空がずっとつづいて、鬱陶しい毎日。
晴れたら気分もよくなるでしょう。




























