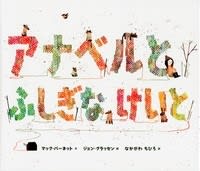長い長いお医者さんの話/カレル・チャベック・作 中野好夫・訳/岩波少年文庫/1952年初版
チェコのカレル・チャペックの律儀なルンペンのお話。
フランティシェク・クラールというルンペンの宿は警察の留置場。浮浪罪でおまわりさんにつかまってはそんな暮らしを続けています。
ひもじさで おなかがグウグウなりだすと、この人は腹の虫をなかしていらあ、とみんながいっていました。
ある日、クラールが、どこかでコッペパンかチーズをもらおうと首をひねっているとき「あ!、きみ、ちょっとこれをたのむ!と紳士が、革のカバンをクラールに投げわたして、風にふきとばされた帽子をおいかけていきました。
ところが三十分待っても、一時間待っても紳士はもどってきません。空にちいさな星がまたたくころになってももどってきません。
ここまでまつクラールは立派というしかありません。なにしろネコババするという考えがまったくありませんから。
不審に思われたクラールは泥棒と間違われ留置場へ。
カバンのなかには、1367815コルナのお金と歯ブラシが一本はいっていました。
「あずかりものです」というクラールの言い分はとおらず、殺人をおかし、死体をどこかにかくしたにちがいないと死刑にされそうになります。
そのとき、ひとりの見知らぬ紳士が、からだじゅうホコリみまれになってフウフウ息をきらしながら姿をあらわします。
そして、カバンの中身が、クラールのいうことと一致するのが証明されます。
紳士は「ルンペンも大勢いるが、あなたのような人はまったく、めずらしい。いってみれば、鳥の中の白いカラスですよ」と称賛します。
紳士は、家と家におくテーブル、テーブルにのせるお皿、皿に入れるあたたかいソーセージを買うだけのお金を、正直のほうびとしてクラールにやったのです。
これだけでおわらないのがチャペックのお話です。クラールのポケットに穴があいていたので、もらったお金が みんなおっこちて、もとのモクアミになったのです。
それだけでなく、白いカラスにあって、白いカラスの王さまに選挙でえらばれますが、クラールはどこかへいって行方がわからなくなっていました。
クラールは王さまの意味。最初の名前の意味が、おわりになってようやく結びつきます。
チャペックのお話、あちこちとびながらすすんでいくのですが、白いカラスとのやりとりもかなりながくなっていきます。
紳士が風でふきとばされた帽子をおいかけるところも、おとぎ話の世界です。
帽子が国境をこえ、ホテルに勘定をはらわずに逃げて、外交官にばけ、モスクワまで。さらに新聞記者になって政治に頭をつっこみます。ロシアの政府をのっとろうとして、銃殺されそうになりますが、風がふいてきて、またまた逃げ出し、ダッタン人の首領になったりと大冒険をするのです。この帽子だけでもひとつのお話です。