
slowrideさん、セシルさんよりご質問をいただきましたので、
「ノンアルコールワイン」の詳細を書いておきます。
輸入販売元は「日本アルコールフリー飲料」
http://www.wine-free.co.jp
ワイン名は「エボニーヴェイル シャルドネ」(白)
「エボニーヴェイル カベルネソヴィニョン」(赤)
「ライトライブ スパークリング」(白泡、これだけALC 0.5%)
(切れて見えないですが、写真の上方にはスパークリングの紹介もあります)
の3アイテムです。
赤の名称が「カベルネ・ソーヴィニヨン」ではなく、どこか早口で発音する
「カベルネソヴィニョン」を和名としているところが、「なんちゃって」を
予感させてくれますね。
写真が見にくいので赤の部分を拡大します。
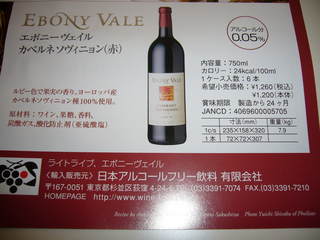
カロリーが24kcalというのもいいですね。
価格も小売希望で1260円です。(白、泡も同価格です)
ただし、賞味期限が24ヶ月となっています。
なんでもドイツが生産国ですが、ブドウはヨーロッパ産ということです。
3回蒸留してアルコールを取り除いているものの、それとは思わせない香りが
特長だとか・・・説明には書いてあります。
私が飲んだ感想は、
泡・・・ペラペラのジュースやおもちゃに近い。
白・・・やや甘口なのでジュースっぽいけど何とか飲める。ただし、
毎日連続ではちょっと萎えます。
赤・・・これが案外飲める。やさしく軽い味わい。淡白だけど、きっと
飲めない身としては十分に嬉しかろう、と思いました。
今までもノンアルコールのワインは発売されていたようですが、この白、赤は
案外良い線行ってるかも知れませんよ。
車に積んで、ドライブしながらラッパ飲みをしてみたい気がします。
問い合わせてみて、「カベルネソヴィニョン」をお店に置いてみましょうか???
「ノンアルコールワイン」の詳細を書いておきます。
輸入販売元は「日本アルコールフリー飲料」
http://www.wine-free.co.jp
ワイン名は「エボニーヴェイル シャルドネ」(白)
「エボニーヴェイル カベルネソヴィニョン」(赤)
「ライトライブ スパークリング」(白泡、これだけALC 0.5%)
(切れて見えないですが、写真の上方にはスパークリングの紹介もあります)
の3アイテムです。
赤の名称が「カベルネ・ソーヴィニヨン」ではなく、どこか早口で発音する
「カベルネソヴィニョン」を和名としているところが、「なんちゃって」を
予感させてくれますね。
写真が見にくいので赤の部分を拡大します。
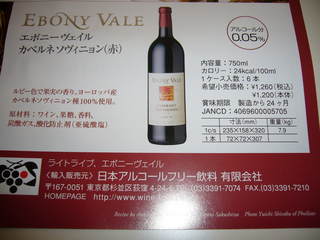
カロリーが24kcalというのもいいですね。
価格も小売希望で1260円です。(白、泡も同価格です)
ただし、賞味期限が24ヶ月となっています。
なんでもドイツが生産国ですが、ブドウはヨーロッパ産ということです。
3回蒸留してアルコールを取り除いているものの、それとは思わせない香りが
特長だとか・・・説明には書いてあります。
私が飲んだ感想は、
泡・・・ペラペラのジュースやおもちゃに近い。
白・・・やや甘口なのでジュースっぽいけど何とか飲める。ただし、
毎日連続ではちょっと萎えます。
赤・・・これが案外飲める。やさしく軽い味わい。淡白だけど、きっと
飲めない身としては十分に嬉しかろう、と思いました。

今までもノンアルコールのワインは発売されていたようですが、この白、赤は
案外良い線行ってるかも知れませんよ。
車に積んで、ドライブしながらラッパ飲みをしてみたい気がします。

問い合わせてみて、「カベルネソヴィニョン」をお店に置いてみましょうか???


























近年の交通事故対策もあり、ノンアルコール飲料自体の需
要は伸びているようですね。
うちでも仕入れてみます。いつ入荷するかは分かりません
が(直接取引のないメーカーで、ロット数なども分かりま
せんし)、入荷したときはお知らせいたします。
ただ、セシルさんが仰る用途で「お酒が飲めない方」が
味的に受け入れられるかどうかは微妙ではあると思いま
す。(飲めない方にはジュースの方が美味しいと思うから)
ヨーロッパ産葡萄、というのは間違いなく東欧でしょうね。
ヨーロッパに取材に行くと、運転手が付く事が多いのですが、一緒に飯を食うときに、彼らは必ずノンアルコールビールを頼んでいます。
食事はワインに合うモノが多いので、こういうモノはどんどん出てくるだろうなと思いますね。
ちなみに、ノンアルコールビールはドイツ産・イタリア産が結構旨いです。
これで飲めない人も楽しめそうでうれしいです。
前もって注文した方がいいのですよね?
slowrideさん(相方ですが)が言っていた、
カリフォルニアのアリエルは、
スパークリングこそ良かったですけど、
赤はそうでも、って感じでしたから。
どういう方法でアルコールを抜いているのかが気になるー。
ちなみにアリエルは、逆浸透膜を使って、
ワインからアルコール以外の水分を抜くという、
逆浸透膜の作用を逆手にとったような方法をとっていました。
今は色々あるんでしょうね。