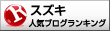立本寺(りゅうほんじ)で宝物お風入れと庭園開放があるというので、
スクーピーとカブで行ってみた。
場所は北野天満宮から南へ200mぐらい。バイクは天満宮に停めてそこから
歩くことにした。
天満宮へ行く道中は、どこでも地蔵盆の真っ最中。
路地を抜けようとすると地蔵盆の子供たちでいっぱい。
ゆっくり走ってジャマにならないようとことこ走り。

北野天満宮からふれあいの街きたの商店街を南東に。
路面電車のモチーフが商店街のいたるところにある。

七本松通りを南に行くと立本寺。
入り口で志を奉納して庭に通じる廊下へ。
日蓮宗由緒寺院の一つであり、法華系京都十六本山の一つ。
また、妙顕寺(上京区寺之内通堀川東入る)、妙覚寺(上京区上御霊前通堀川
東入る)と並び三具足山の一つ。本尊は十界大曼荼羅。

古いガラス越しに見る庭も、石でできた手水鉢がアクセントになってる。

部屋には色々な宝物が展示されている。
掛け軸とかに書かれた文字は達筆すぎて読めず。なさけない。
水墨画に目が惹かれる。墨の濃淡だけでこのように書くってすごい。
うまい人の絵は空気感が表れる。

狩野玉楽という、戦国期に小田原狩野派の一人として、北条氏の城下町・小田原
で活躍したとみられる絵師の作らしい。

襖絵の虎に睨まれてしもた。

簡素な庭の雰囲気がいい。

建物の中の柱とかは黒光りしていた。年期がはいってる。

境内の鬼子母神堂で地蔵盆が行われている。

立本寺に一礼して千本出水のほうへ。
千本出水から七本松へ戻るルートをとる。
福勝寺(ひょうたん寺)は門が閉まっていて入れなかった。
隣の出水の毘沙門様の華光寺へ。
ほほえましいお地蔵さんが入っていいよといっている。

出水という地名は湧き水から来ているといわれ、ここの庭にも豊かな水を利用した、
庭園がある。
天正11年(1583)に妙顕寺の12世日堯上人が開山した。
十界曼荼羅を本尊として祀る。また本堂の一角に安置されている毘沙門天像は、
鞍馬寺の像と同木同作で平安後期の作と伝え、豊臣秀吉が伏見城で祭祀してい
たのを、この寺の守護神として寄進したといわれている。


百足は足が多いので、おあし(銭)がたくさんつくといわれ、金運を呼ぶもの
として人々の信仰を集めた。
また、百足は後ろに下がらず、前進するのみであるから、戦国武将に好まれた
らしい。

ここにはかわいらしいお地蔵さんがいる。

毘沙門様を出てすぐ向かいの「うかれ猫」の光清寺へ。
門を入るとすぐ石庭が飛び込んでくる。

うかれ猫。名前がいい。説明書きにはこのように書かれてます。
『光清寺の鎮守堂に、牡丹に三毛猫の絵という異例の絵馬が江戸時代から掲げら
れている。江戸時代後期、近辺の遊里から三味線の音が聞えてくると、誘われる
ように猫が絵馬から浮かれ出し、女性の姿になって踊り始めるのだった。それを
見た人がいて、大騒ぎとなった。住職が不快に思い、法力で浮かれ猫を絵馬に封
じ込めてしまった。
その夜、衣冠束帯に威儀を正した武士が住職の夢枕に現れた。「私は絵馬の猫の
化身だが、あなたに封じ込められて苦しくてしかたがない。今後は、世間を騒が
すことはけしてしないので、許してもらえないか」と嘆願した。住職は哀れに思
い、法力を解いたという。
この界隈に伝わる「出水の七不思議」の一つに数えられる。』

石庭の正面。

観音寺のよなき地蔵さんにお参りしてから、少し南に下がって祐正寺の妻取地蔵へ。
独身男性がお参りすると、よき妻とめぐり合うらしい。

一条商店街(大将軍商店街)へ。
ここは妖怪ストリートがあり、見ているとけっこう面白い。
境港の水木しげるロードには完全に負けるが、手作りの面白さがある。
これは家具屋に置かれたタンスの妖怪。

パン屋の妖怪。

魚屋の妖怪。
これ以外にも、この道にはいろんな妖怪たちがお客を呼んでいる。

大将軍八神社へ。
祭神は古来の日本の神ではなく大将軍一神を祀っていたが、 明治時代に「神仏
分離令」によって 神道を国教とし現在の形「素盞鳴尊、その御子五男三女神、
並びに 桓武天皇を合祀」となり、御子八神と暦神の八神が習合して以後社名は
「大将軍八神社」という。

欄干にちいさな屋根がついてる。

祭殿の裏手に錨発見。何の船の錨かわからず。

北野天満宮へ戻る途中に、なつかしい看板発見。
NIKON D70 標準ズーム使用
スクーピーとカブで行ってみた。
場所は北野天満宮から南へ200mぐらい。バイクは天満宮に停めてそこから
歩くことにした。
天満宮へ行く道中は、どこでも地蔵盆の真っ最中。
路地を抜けようとすると地蔵盆の子供たちでいっぱい。
ゆっくり走ってジャマにならないようとことこ走り。

北野天満宮からふれあいの街きたの商店街を南東に。
路面電車のモチーフが商店街のいたるところにある。

七本松通りを南に行くと立本寺。
入り口で志を奉納して庭に通じる廊下へ。
日蓮宗由緒寺院の一つであり、法華系京都十六本山の一つ。
また、妙顕寺(上京区寺之内通堀川東入る)、妙覚寺(上京区上御霊前通堀川
東入る)と並び三具足山の一つ。本尊は十界大曼荼羅。

古いガラス越しに見る庭も、石でできた手水鉢がアクセントになってる。

部屋には色々な宝物が展示されている。
掛け軸とかに書かれた文字は達筆すぎて読めず。なさけない。
水墨画に目が惹かれる。墨の濃淡だけでこのように書くってすごい。
うまい人の絵は空気感が表れる。

狩野玉楽という、戦国期に小田原狩野派の一人として、北条氏の城下町・小田原
で活躍したとみられる絵師の作らしい。

襖絵の虎に睨まれてしもた。

簡素な庭の雰囲気がいい。

建物の中の柱とかは黒光りしていた。年期がはいってる。

境内の鬼子母神堂で地蔵盆が行われている。

立本寺に一礼して千本出水のほうへ。
千本出水から七本松へ戻るルートをとる。
福勝寺(ひょうたん寺)は門が閉まっていて入れなかった。
隣の出水の毘沙門様の華光寺へ。
ほほえましいお地蔵さんが入っていいよといっている。

出水という地名は湧き水から来ているといわれ、ここの庭にも豊かな水を利用した、
庭園がある。
天正11年(1583)に妙顕寺の12世日堯上人が開山した。
十界曼荼羅を本尊として祀る。また本堂の一角に安置されている毘沙門天像は、
鞍馬寺の像と同木同作で平安後期の作と伝え、豊臣秀吉が伏見城で祭祀してい
たのを、この寺の守護神として寄進したといわれている。


百足は足が多いので、おあし(銭)がたくさんつくといわれ、金運を呼ぶもの
として人々の信仰を集めた。
また、百足は後ろに下がらず、前進するのみであるから、戦国武将に好まれた
らしい。

ここにはかわいらしいお地蔵さんがいる。

毘沙門様を出てすぐ向かいの「うかれ猫」の光清寺へ。
門を入るとすぐ石庭が飛び込んでくる。

うかれ猫。名前がいい。説明書きにはこのように書かれてます。
『光清寺の鎮守堂に、牡丹に三毛猫の絵という異例の絵馬が江戸時代から掲げら
れている。江戸時代後期、近辺の遊里から三味線の音が聞えてくると、誘われる
ように猫が絵馬から浮かれ出し、女性の姿になって踊り始めるのだった。それを
見た人がいて、大騒ぎとなった。住職が不快に思い、法力で浮かれ猫を絵馬に封
じ込めてしまった。
その夜、衣冠束帯に威儀を正した武士が住職の夢枕に現れた。「私は絵馬の猫の
化身だが、あなたに封じ込められて苦しくてしかたがない。今後は、世間を騒が
すことはけしてしないので、許してもらえないか」と嘆願した。住職は哀れに思
い、法力を解いたという。
この界隈に伝わる「出水の七不思議」の一つに数えられる。』

石庭の正面。

観音寺のよなき地蔵さんにお参りしてから、少し南に下がって祐正寺の妻取地蔵へ。
独身男性がお参りすると、よき妻とめぐり合うらしい。

一条商店街(大将軍商店街)へ。
ここは妖怪ストリートがあり、見ているとけっこう面白い。
境港の水木しげるロードには完全に負けるが、手作りの面白さがある。
これは家具屋に置かれたタンスの妖怪。

パン屋の妖怪。

魚屋の妖怪。
これ以外にも、この道にはいろんな妖怪たちがお客を呼んでいる。

大将軍八神社へ。
祭神は古来の日本の神ではなく大将軍一神を祀っていたが、 明治時代に「神仏
分離令」によって 神道を国教とし現在の形「素盞鳴尊、その御子五男三女神、
並びに 桓武天皇を合祀」となり、御子八神と暦神の八神が習合して以後社名は
「大将軍八神社」という。

欄干にちいさな屋根がついてる。

祭殿の裏手に錨発見。何の船の錨かわからず。

北野天満宮へ戻る途中に、なつかしい看板発見。
NIKON D70 標準ズーム使用