この「診断即治療」は、 FC2ブログ にも転載しています。
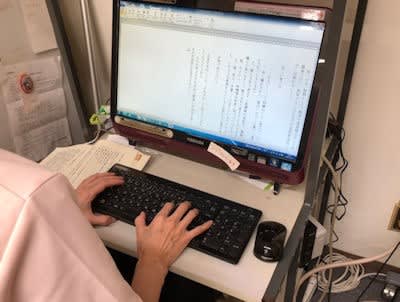
パソコンに打ち込む様子
アントレプレナーの勉強をするのに、「人間学」を学ばせてもらいました。
人間学とは、簡単に言うと「人間の本質を哲学的に研究する学問」と辞書には書かれていますが、「人間の精神や身体のあり方などの行為に関する学問」という解説もします。
人間学では、『論語』も勉強しましたが、この論語がまた面白い。
「なるほど、なるほど……」と読み進めてしまいます。
そして、何よりも面白いと思ったのは、読むときの「自分の心境」で、読み方が違うことです。
ですから、きょう読んだ内容を1か月後に読んで見ると、違う意味に解釈されるのです。
でも、違わないのがあります。
それは、「君子」のあり方です。
論語には、頻繁に「君子」という言葉が出てきますが、論語でいう「君子」とは、儒教でいうところの「仁・義・礼・智・信」を備えた人であり、「常に人のことを考えて行動する人」のことです。
固いことのように聞こえるかも知れませんが、固いことはありません。
たとえば、『論語』に
【君子は徳を懐い(おもい)、小人は土(ど)を懐う】(君子は政治のための道徳を考えるが、小人は自己の利益につながる郷土のことを考える)という内容の一説があります。
つまり、相手や皆さんのことを考えるのか、自分のことだけを考えるのかということです。
自分のことだけ考えていては「つまらない人」になってしまいます。
その「つまらない人」のことを論語では「小人」という言葉で表現しています。
「小さい人間」という意味ですね。
上の写真は、1990年(28年前)に私がワープロで書いて出版した本ですが、在庫などはありません。
1冊だけ当院の本棚に並べてあるので、それを読んだ方々から、「再販しないの?」と聞かれました。
しかし、昔のワープロ原稿なので、フロッピーもないし、打ち込むとなると大変な作業になるので、そのままになっています。
今年から当院で勤め始めたスタッフが、
「先生、これ面白いし、わかりやすいので、再販しないんですか?」と言ってきました。
「あ、これねー。この本は駆け出しの時に書いた本だけど、意外に人気があって、何人もの方から再販を言われるのですが、打ち込む時間がないんです」と言うと、
「私が打ち込みましょうか」と言う。
「ほんとー? 大変ですよー」
「打ち込んでいいですか? これは患者さんにも役立つと思うので……」
「いいんですか? やってくれれば助かるけど……」
「はい。わかりました」
と、この本を打ち込み始めたのです。
起業するときに最初に考えるべきことは、販売する商品や事業のコンセプトなどですが、並行して、「顧客は何を求めているのか」ということも考えます。
それを考えるときに、「自分はどう思うのか」というのを基本にします。
つまり、「自分が考える商品はこのような商品」というのを基本にするわけです。
そのように考えながら起業したなら、それなりに伸びていくと言われます。
そして、そこに「君子の心」があれば、尚よしというわけです。
「こういうものがあったら、皆さんが助かるだろうなー」と考えることができるかどうかになるわけです。
「国民のことを考えて仕事をする」のは、政治家だけの問題ではありません。
我々も、人のことを考えながら仕事をすることが求められているのです。
それが「君子への道」だと考えるわけです。
スタッフがそれを行動で示してくれました。
治療の合間に打ち込んでいるので、時間はかかると思いますが、すでに行動に起こしていますので、出来上がるのは時間の問題です。
出来上がりましたら、またこのブログで紹介するつもりです。
そのときは、私ではなく、うちのスタッフを褒めてあげてください。
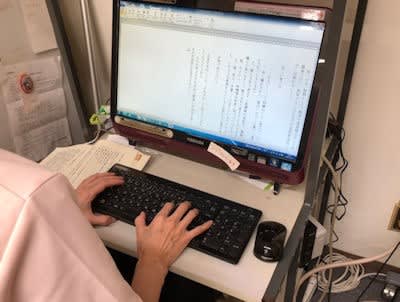
パソコンに打ち込む様子
アントレプレナーの勉強をするのに、「人間学」を学ばせてもらいました。
人間学とは、簡単に言うと「人間の本質を哲学的に研究する学問」と辞書には書かれていますが、「人間の精神や身体のあり方などの行為に関する学問」という解説もします。
人間学では、『論語』も勉強しましたが、この論語がまた面白い。
「なるほど、なるほど……」と読み進めてしまいます。
そして、何よりも面白いと思ったのは、読むときの「自分の心境」で、読み方が違うことです。
ですから、きょう読んだ内容を1か月後に読んで見ると、違う意味に解釈されるのです。
でも、違わないのがあります。
それは、「君子」のあり方です。
論語には、頻繁に「君子」という言葉が出てきますが、論語でいう「君子」とは、儒教でいうところの「仁・義・礼・智・信」を備えた人であり、「常に人のことを考えて行動する人」のことです。
固いことのように聞こえるかも知れませんが、固いことはありません。
たとえば、『論語』に
【君子は徳を懐い(おもい)、小人は土(ど)を懐う】(君子は政治のための道徳を考えるが、小人は自己の利益につながる郷土のことを考える)という内容の一説があります。
つまり、相手や皆さんのことを考えるのか、自分のことだけを考えるのかということです。
自分のことだけ考えていては「つまらない人」になってしまいます。
その「つまらない人」のことを論語では「小人」という言葉で表現しています。
「小さい人間」という意味ですね。
上の写真は、1990年(28年前)に私がワープロで書いて出版した本ですが、在庫などはありません。
1冊だけ当院の本棚に並べてあるので、それを読んだ方々から、「再販しないの?」と聞かれました。
しかし、昔のワープロ原稿なので、フロッピーもないし、打ち込むとなると大変な作業になるので、そのままになっています。
今年から当院で勤め始めたスタッフが、
「先生、これ面白いし、わかりやすいので、再販しないんですか?」と言ってきました。
「あ、これねー。この本は駆け出しの時に書いた本だけど、意外に人気があって、何人もの方から再販を言われるのですが、打ち込む時間がないんです」と言うと、
「私が打ち込みましょうか」と言う。
「ほんとー? 大変ですよー」
「打ち込んでいいですか? これは患者さんにも役立つと思うので……」
「いいんですか? やってくれれば助かるけど……」
「はい。わかりました」
と、この本を打ち込み始めたのです。
起業するときに最初に考えるべきことは、販売する商品や事業のコンセプトなどですが、並行して、「顧客は何を求めているのか」ということも考えます。
それを考えるときに、「自分はどう思うのか」というのを基本にします。
つまり、「自分が考える商品はこのような商品」というのを基本にするわけです。
そのように考えながら起業したなら、それなりに伸びていくと言われます。
そして、そこに「君子の心」があれば、尚よしというわけです。
「こういうものがあったら、皆さんが助かるだろうなー」と考えることができるかどうかになるわけです。
「国民のことを考えて仕事をする」のは、政治家だけの問題ではありません。
我々も、人のことを考えながら仕事をすることが求められているのです。
それが「君子への道」だと考えるわけです。
スタッフがそれを行動で示してくれました。
治療の合間に打ち込んでいるので、時間はかかると思いますが、すでに行動に起こしていますので、出来上がるのは時間の問題です。
出来上がりましたら、またこのブログで紹介するつもりです。
そのときは、私ではなく、うちのスタッフを褒めてあげてください。


















