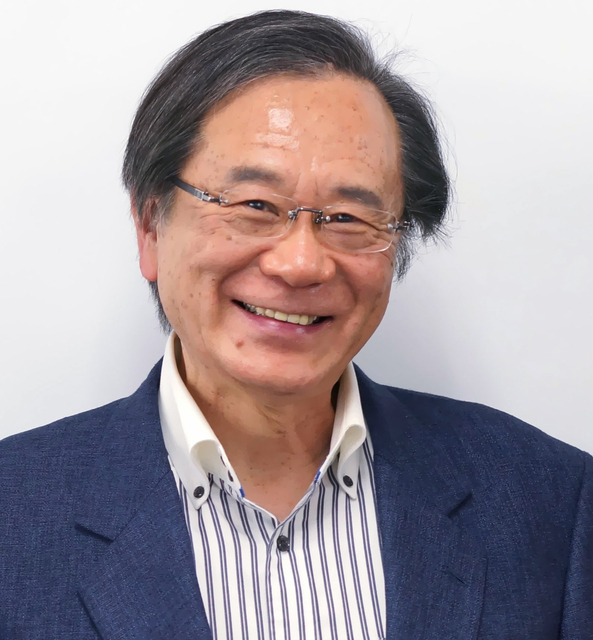目新しいものを追うのは、「恋知(哲学)」ではなく、「流行思想」でしかありませんが、今の日本には、どこにも恋知(哲学)はなく、無思想=反射的で紋切り型の言説か、流行思想の紹介しかありません。
ほんとうの恋知(哲学)とは何か?を1973年に88歳で亡くなったオットー・クレンペラーの音楽をヒントに考えてみたいと思います。
クレンペラーの音楽のひとつ目のキーワードは、「対比」。
管楽器と弦楽器、どちらも主従関係にならない。常に互角で、どちらかが譲るということがない。・・・・「有機と無機という対比」ついには「音と沈黙の対比」という境地を切り拓いた。
もうひとつは、「音の霊」。クレンペラーは「音そのものを鍛えぬいた男」で、音楽を感情の代弁に貶めない。「フレーズ」に意味を持たせず、あくまで「ひとつの音」単位で扱う。すべての音を平等に鳴らし、「音ひとつひとつのかけがえのない存在と意味」を追求した指揮者。だから彼の音楽には「音霊」が宿っている。
シューマンの交響曲4番を例にすると、すべての音がむきだしになっていて凄い迫力を生んでいる。人間の善も悪も、ためらわずに全部さらけ出している。それで失うものがあってもよい。悪いものも全部さらけだしていこうという姿勢。その率直さが胸を打つ。そうすることではじめてトータルな人格が現れ、人間は人間のまま気高くなれるのだ、ということを感じさせてくれる演奏。きれいごとのない世界・自然と真実の世界にひとは打ち震える。
クレンペラーは、誰のどの曲を演奏しても、根底に流れるものは同じ。持ち味はひとつ。それなのにどうして聞き飽きることがないのだろうか?――クレンペラーの魅力は「無限の永遠の変化」なのだ。海岸で波が砂浜に寄せては引いていくのをずっと眺めていくのを見ていても見飽きない、それと同じだ。単調に見える事象の中に「無限の永遠の変化」がある。クレンペラーは、あるがあままの「音」そのもので勝負する。だからこそ「無限の永遠の変化」を引き出すことができたのだ。
(以上は、「レコード芸術」10月号・喜多尾ゼミナールより、変更して引用)
クレンペラーの音楽の悠然たるテンポ。巨大な構築性。無類のリズム感のよさを支える上記の思想は、私には、ほんものの恋知(哲学)の条件そのものと思えます。取り繕い・辻褄合わせ・仮面の笑顔とは無縁の深く巨大な自由とエロースがあります。生は底まで落ち切り、その地点から上昇しているのです。生きるに値する生とはそういうものでしょう。
武田康弘