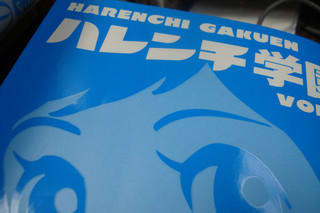そにしけんじの『猫ピッチャー』はまだ続いているのではないかとおもう。猫がニャイアンツ(どうみてもジャイアンツ)のピッチャーをやっている話である。
むろん、猫がかわいいというだけのまんがなので、野球まんがではないのではないかと思われるが、――それにしては長く続いている。読んでみると、案外無理矢理作った力こぶのようなものはむしろ「猫ラーメン」の方にある。こちらは猫が人間に近づかなくてはならなかったからである。「猫ピッチャー」はそうではない。猫のままで巨人のエースなのだ。
思うに、最近のプロ野球というのは、案外『猫ピッチャー』みたいな世界なのではないだろうか。それは、球場にマスコットがいるからではない。
落合博満氏はFAとか給料の面では、アメリカ風の個人事業主的な考え方を導入した人であったが、野球観は古風なひとのような感じがする。案外、浪花節的なところもあって、むしろ商業化するプロ野球の中で、ヤクザな素人的野球人として抵抗していた面がある。彼のファッションをみればそうだと思うし、だいたい、彼は「なんとか人生」みたいな演歌のレコードを出すような人なのである。(ほかの人も出してたが……)長嶋王の時代をよく知らないのであれなのだが、落合選手は、決して星野的熱血とも無縁ではない。ただ、極端に弱気で合理的だけだったように思われる。「ほら、おれこれ仕事だから」という彼の口癖は、自分に言い聞かせていた面が強いと思う。マスコミに対しても、あまりコントロールをしたがっているようにはみえなかった(結果的にマスコミは翻弄されていたが――)。ただ、彼が監督の後期に、ガンダムオタクであることを標榜しているのをみたとき、事態はこんがらがってきたぞと思った。
イチローはどうだったのであろうか。合理的な思考は落合と似ているが、彼のインタビューは結構コミュニカティブで、単につっけんどんではない。その意味で、野村監督や松井などと似ていてより「職業人」なのだと思った。のみならず、イチローは、ダウンタウンなどと一緒に番組のなかで遊んでしまう器用さを持ち合わせている。今回の引退会見で、「監督は絶対無理。僕は人望ないので」などと言っていたが、案外本当かもしれないのである。人望というのは、コミュニケーション能力とは全然別物である。
しかし、そのイチローも「最近の野球は頭を使わない方に行ってしまって、気持ち悪い」などと言っていた。マスコミはここを取り上げたがらないが、イチローが一番言いたかったことではなかろうか。外国人になってみて分かったことがあるといった発言は、たぶんそういう認識の一部をなしている。しかし、イチローも妻と犬に感謝する癒やし発言?までしてサービスしていた。犬でよかった。猫だったら……(いや、犬の方が妙な比喩を感じるからまずいのか……)
王も落合もイチローも職人的であって、その突き詰めた思考のありようからなにか人生訓みたいなことを求められたりもする。スポーツ選手の中には、政治家になったりする御仁もいるくらいだ。彼らをもちあげる心性がまともとはいえないにしても、そういう現象をあながち全否定はできない。われわれだいたい皆そんな素人状態で政治に関与することになるだろうからだ。したがって、ある個人がまともなことを言うためには、職分に縛られている状態でも、世間や社会がかれら(我々)を、きちんと教育できないといけないわけである。それは全く上手くいっていない。イチローが草野球がしたい、と言っていたのは、そういう問題に彼がたどり着いたことを示しているのかもしれない。
われわれは思ったよりも、自分の職業以外のことがわからなくなっている。オルテガが言うように、それが「大衆」としての大きな特徴だといえばそれまでだが、イチローからもそれを感じる。その意味では、イチローはまさに我々の極端な自画像であるような気がする。
結論:イチローとシロー、実に似ている。